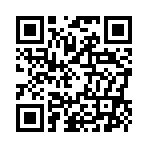2013年11月26日
県要約筆記者養成講座(報告)
25年度県要約筆記者養成講座 後期課程 第8回講座報告
要約筆記対策部
日 時 11月23日(土) 10時~15時
場 所 松本市総合福祉センター 4階大会議室
受講生 40名 (補講受講者を含む)
参加者(難協) 浜・窪田・竹重・中野・北村・宮崎
情報保障担当 飯田・木曽(手書き)
当 番 北村 (難協)
午前 共通講義 (補講対象講義) <テキスト第14章 要約筆記者のあり方①>
「心構えとモラル」 「通訳者の倫理」
学習目標・・・要約筆記者として通訳の倫理を学び、社会福祉従事者の専門性を確認する。
10時~11時 講師:山口智美さん
11時~12時 講師:田村善子さん
・難聴者を取り巻く社会環境
就労におけるバリア(職種の制限・昇進機会の剥奪・職場での孤立)
教育のバリア(情報不足による成績不振・コミュニケーション不全・いじめの対象)
・聞こえの程度によりコミュニケーション方法に違いが表れる。
障害が重くなるほど視覚情報が必要。
・障害者権利条約・・世界133か国で批准→一般的な認知度が低い。
・「倫理綱領」の必要性について(これがないと政見放送に手話や字幕をつけられない。)
・「倫理」とは? 人として守るべき道。
個人・・・誠意・献身・友愛・自立など
社会との関わり・・・公正・自治・正義・平等など
午後 共通講義 <テキスト第14章 要約筆記者のあり方②>
「社会福祉従事者としての専門性」
講師:安曇野市社会福祉課障害福祉担当 深井恵子さん(手話通訳士・社会福祉士)
・要約筆記者の役割(あるべき姿)
1、権利擁護のための要約筆記(これを必要とする聴覚障害者のための人権を擁護する
2、通訳としての要約筆記(聞こえない人に音声情報を何らかの形で伝える行為
・要約筆記者の到達目標
1、社会福祉の理念を理解していること。
2、「通訳」という行為に対する自覚的な理解をしていること。
3、要約筆記技術をもって通訳作業を実現できること。
4、聴覚障害者の権利擁護の観点から通訳できること
権利擁護のための要約筆記、通訳行為としての要約筆記を実現
・自己覚知の重要性
・自分自身の傾向、価値観などを理解することで活動の質が変わる。
・危機管理が可能になる。
※対人援助の仕事は、人を理解し支援する仕事
人との関わりの中でどのような関係を築き、調整することができるかが問われる。
※援助の中心は常に当事者であり、当事者と環境を調整し、本人が本人らしく選択し決定できるよう
決定までのプロセスを本人と共に考え支援する。
<感想>
・要約筆記者と難聴者の関係性が明確になった講義でした。
・要約筆記者のあるべき姿が見えたことで、私たち難聴者がどのような対応をとればよい関係を保ちながら最適な情報保障を得ることができるのか? 難聴者も共に考えるプロセスが必要だと感じます。今後の難聴者協会の活動で取り上げてほしいと思います。
次回講座は12月14日開催です。 以上報告 <浜・宮崎>
写真(↓)の提供は竹重さんです。



要約筆記対策部
日 時 11月23日(土) 10時~15時
場 所 松本市総合福祉センター 4階大会議室
受講生 40名 (補講受講者を含む)
参加者(難協) 浜・窪田・竹重・中野・北村・宮崎
情報保障担当 飯田・木曽(手書き)
当 番 北村 (難協)
午前 共通講義 (補講対象講義) <テキスト第14章 要約筆記者のあり方①>
「心構えとモラル」 「通訳者の倫理」
学習目標・・・要約筆記者として通訳の倫理を学び、社会福祉従事者の専門性を確認する。
10時~11時 講師:山口智美さん
11時~12時 講師:田村善子さん
・難聴者を取り巻く社会環境
就労におけるバリア(職種の制限・昇進機会の剥奪・職場での孤立)
教育のバリア(情報不足による成績不振・コミュニケーション不全・いじめの対象)
・聞こえの程度によりコミュニケーション方法に違いが表れる。
障害が重くなるほど視覚情報が必要。
・障害者権利条約・・世界133か国で批准→一般的な認知度が低い。
・「倫理綱領」の必要性について(これがないと政見放送に手話や字幕をつけられない。)
・「倫理」とは? 人として守るべき道。
個人・・・誠意・献身・友愛・自立など
社会との関わり・・・公正・自治・正義・平等など
午後 共通講義 <テキスト第14章 要約筆記者のあり方②>
「社会福祉従事者としての専門性」
講師:安曇野市社会福祉課障害福祉担当 深井恵子さん(手話通訳士・社会福祉士)
・要約筆記者の役割(あるべき姿)
1、権利擁護のための要約筆記(これを必要とする聴覚障害者のための人権を擁護する
2、通訳としての要約筆記(聞こえない人に音声情報を何らかの形で伝える行為
・要約筆記者の到達目標
1、社会福祉の理念を理解していること。
2、「通訳」という行為に対する自覚的な理解をしていること。
3、要約筆記技術をもって通訳作業を実現できること。
4、聴覚障害者の権利擁護の観点から通訳できること
権利擁護のための要約筆記、通訳行為としての要約筆記を実現
・自己覚知の重要性
・自分自身の傾向、価値観などを理解することで活動の質が変わる。
・危機管理が可能になる。
※対人援助の仕事は、人を理解し支援する仕事
人との関わりの中でどのような関係を築き、調整することができるかが問われる。
※援助の中心は常に当事者であり、当事者と環境を調整し、本人が本人らしく選択し決定できるよう
決定までのプロセスを本人と共に考え支援する。
<感想>
・要約筆記者と難聴者の関係性が明確になった講義でした。
・要約筆記者のあるべき姿が見えたことで、私たち難聴者がどのような対応をとればよい関係を保ちながら最適な情報保障を得ることができるのか? 難聴者も共に考えるプロセスが必要だと感じます。今後の難聴者協会の活動で取り上げてほしいと思います。
次回講座は12月14日開催です。 以上報告 <浜・宮崎>
写真(↓)の提供は竹重さんです。
Posted by 六万石 at 07:34│Comments(0)