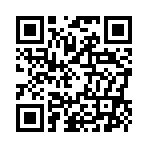2013年09月13日
手話の本
<つぶやき万華鏡>(寄稿)
手話の本
図書館からこのような本(手話の本=編集部註)を借りてきました。
たまたま新着図書コーナーにあったので、何気なく手にとって、いそいそと「自動貸出機」へ・・・
DVDが付録でついているので、家のパソコンで見れるなー(^^♪ と思いつつ。
ところが、肝心のDVDが本についていない!(取り外されている)
確かめてみたら、DVDの貸し出しは窓口へ申し出てください。とありました。あちゃ~~
それはともかく、最近では手話関係の本がすごく増えましたね。
大型書店に行くと1つの棚を占有するほど、ずら~りと。
しかし、ほとんどは同じような内容の入門書で、変り映えがしません。
この本もそのうちの1つです。
一通り、本の内容に沿って、おさらいの意味で手を動かしてみる。
ふだん、手話を使う環境に無いのでだんだんと忘れつつあるのですが・・・結構間違って覚えている手話も発見したりと、
それなりの収穫はありました。
legacy-tw(会員ブログ「信州の隠れ家」より)
2013年09月19日
難聴者と手話(東京事情)
<会員ブログより>(寄稿)
長野難聴の仲間の会員ブログ「信州の隠れ家より」(legacy-twさん)9月16日の記事をいただきました。
(編集部註) legacy-twさんは、以前に全難聴の仕事に関わっていらっしゃった方で、現在は帰郷して長野難聴の仲間となっております。ブログ「信州の隠れ家より」に掲載される情報には目が離せません。
長野難聴の仲間の会員ブログ「信州の隠れ家より」(legacy-twさん)9月16日の記事をいただきました。
手話については、世間一般の認識には、聴覚障害者は「手話」が使えるというのがあります。
聴覚障害者にもいろいろなタイプがありますが、”ろう者”は一般に手話を第一言語として使っています。
しかし、難聴者や中途失聴者は音声の日本語をベースに言語を獲得してきたので、手話という言語は後から意識的に学ばないと身につきません。
ろう者のほとんど(全部ではない)は手話を使えますが・・・逆に難聴者のほとんどは手話はできません。
その認識が世間にないというか、あまり行き渡っていないのが実態です。
難聴者が手話を身につけるきっかけとか必要性は、
・親族や関係者や友人にろう者がいて、コミュニケーションを取る環境にあった
・難聴者組織の活動などで、すでに手話を身につけた難聴者やろう者とのコミュニケーションが必要になった
・手話ブームの影響
・難聴者向けの手話講習会や手話サークルなど、手話を学ぶ機会が得られた
・・・といったところでしょうか?
個人的な経緯を暴露?しますと・・・
最初に手話本を買ったのは20年以上前になりますが、本を入手したものの独学で学ぶには無理があり、身につきませんでした。
次に手話を学ぶきっかけになたのは、東京で難聴者組織に加わってからです。
そこで活動をするには、なんとなく”手話が必須”みたいな雰囲気がありました。
最初は、NHKの「みんなの手話」という番組を、かじりつくように見て、ビデオにも録画して再生して、我流に覚えました。
そして、東京都では(都の税金を使って)中途失聴者・難聴者向けの「手話講習会」が開催されていました。これは30数年の歴史があります。
入門、初級、中級、上級の各コースを6ヶ月間で修了し、最短で2年間で卒業するしくみです。
講師は、手話通訳者と難聴者の講師が交互に担当するしくみで、その他に”助手”2人がついていました。
それら難聴の講師と助手は、講習会修了生のうちから、これは、と思える人がスカウトされます(笑)
初めて手話を学ぶ入門者(ほとんどは中途失聴者)にとっては、講師の話(音声)が通じませんので、要約筆記(OHP)が付けられています。
これは入門コースの6ヶ月間だけです。その次の段階の初級コースでは、要約筆記がつきませんから、まだはなはだ不十分な手話取得レベルでもって講義を受けざるを得ませんでした。
毎週1回、夜6時半からの開催で(勤め人も多いため)、1回2時間、1コースあたり22回程度のカリキュラムです。
2年間計で88回、176時間の講習を受けることになります。
それでも、ほとんどは高齢の受講生にとっては、習得できたというにはかなり不十分です。
もっとも、この講習会の開催目的は「手話の習得」ではなく、難聴者のコミュニケーションを含む知識の勉強と、心のケアにあります。
・・当然、この講習会は難聴協会が全面的にバックアップしています。修了生は協会への入会の”お得意様”でもあります(*^_^*)
私もそうでしたが、入会した会員は、そこで協会内の「手話サークル」に入ります。
それも地区、昼夜の別でいくつかのサークルがあります。
そこで、”手話”を媒介しての仲間づくり、活動、心のリハビリ・・・運動へ参画、と各自の進むべき道が定まっていくのです。
また、財団の助成金を得て、更に上級の「専門コース」講習会を運営したりしていました。
結局、難聴者にとっての手話の使い道というのは一般社会でのコミュニケーション手段としてではなくて、
仲間内でのちょっとした”会話”のためにあるといえます。
例えば聞こえる人が、隣近所の人にささやくように話す、ヒソヒソ話のようなことは難聴者にはできません。
声をある程度大きくしないと通じないこともあるし、身振りや筆談ではなにかと限界もあるからです。
そんなときに、片言でも良いから手話で意思疎通ができるのは何かと便利です。
仲間同士では、共通の話題・状況を共有しているので、”片言”でもほとんどの場合はこれで事足りるのです。
信州の場合は、・・・・難聴者が学ぶ手話講習会のような場がありません。
そのため、協会の会員にも手話が分からない人が結構いたりします。
だからといって、それで特段困るわけではないのでそれを問題視することはありません。
手話を使える人でも、”使う場がほとんど”という悩みも抱えています。
ボケ防止のためにも、手を動かしていると良いとも言われますが・・(-_-;)
legacy-tw
(編集部註) legacy-twさんは、以前に全難聴の仕事に関わっていらっしゃった方で、現在は帰郷して長野難聴の仲間となっております。ブログ「信州の隠れ家より」に掲載される情報には目が離せません。
2013年09月27日
難聴者のつぶやき・手話
<難聴者のつぶやき>(投稿記事)
難聴者が手話で悩むこと
(1) 手話辞典に記載されているイラストや説明が、本により異なる(場合がある)。
(2) ろう者によって、それぞれに違う。(癖がある)
(3) ゆっくりやってくれればわかるのに、わざと速くやる人がいる。。
(1)については、手話が身についている人にとっては、
「どっちでもいい」ような些細な問題かもしれないが、
初心者にとっては、大いに悩むことである。
(2) については、、ろう者の生まれ・育ち、年齢、
とりわけ出身ろう学校の違いにより、さまざま。
(3) について、こちらが読み取れないうちに、どんどん進める人がいる。
なんで、ちょっと待ってくれないのか。
そういう「困ったチャン」は難聴者で手話をやる人の中にもいる。 (Shuwa-Rin)
(1) 手話辞典に記載されているイラストや説明が、本により異なる(場合がある)。
(2) ろう者によって、それぞれに違う。(癖がある)
(3) ゆっくりやってくれればわかるのに、わざと速くやる人がいる。。
(1)については、手話が身についている人にとっては、
「どっちでもいい」ような些細な問題かもしれないが、
初心者にとっては、大いに悩むことである。
(2) については、、ろう者の生まれ・育ち、年齢、
とりわけ出身ろう学校の違いにより、さまざま。
(3) について、こちらが読み取れないうちに、どんどん進める人がいる。
なんで、ちょっと待ってくれないのか。
そういう「困ったチャン」は難聴者で手話をやる人の中にもいる。 (Shuwa-Rin)
2014年07月15日
難聴者の手話
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
過日(7月13日)のEテレで
中途失聴者・難聴者のための手話講習会の模様を放映していた。
小林順子さんが
「私たちは日本語という母語を持っています。
そういう者として、(手話で)介在者なく話したい」
という趣旨のことを言っておられた。
「日本手話」
とか、
「日本語対応手話」
とか、
そういう用語を、不用意に用いることなく、
うまく表現してくれたと思います。
(会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」から引用)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
医療の現場で・・・
医者はどうしても要約筆記者のほうに向かって話します。
通訳が美人だから仕方ないです。
女房ならそれは、ほんとういに仕方ないが、
要約筆記者は女房ではない。
「要約筆記者は医者に相槌をうったらダメ」
というようなことは、現場で、
実践で初めてわかること。
(ROKU) 2014.7.15
2014年07月25日
自己満足?(手話)

7/24の西の空 Photo by T.Sato
【掲示板】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第16回 関東ブロック女性部一泊研修 11月8日(土)~9日(日)
会場:片倉館
宿泊:朱白 http://www.suhaku.co.jp/
→画面左のサイドバーのカテゴリ「関東ブロック女性部一泊研修」」をクリックしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第20回全国中途失聴者・難聴者福祉大会in三重
☆ 開催年月日 平成26年10月25日(土)・26日(日)・27日(月-観光)
☆ 開催場所 四日市市文化会館
詳細は全難聴ホームページでご覧ください
→ http://www.zennancho.or.jp/special/mie/fukushi_mie2014.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆字幕付き映画のお知らせ
ポケットモンスター 2014 8月2日(土)~8月5日(火)
思い出のマーニー 8月9日(土)~8月12日(火)
エイトレンジャー2 8月23日(土)~26日(火)
GODZILLA ゴジラ(2D吹替版) 8月30日(土)~9月2日(土)
・長野グランドシネマズ(長野市) 電話:026-233-6060 FAX:026-233-6061
ホームページ:http://www.grandcinemas.net/
http://www.n-grandcinemas.net/(携帯版)
料金:障害者手帳を提示すると、本人と同伴者1名まで割引料金(1,000円)になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
ろう者の手話はすごく速いが、手話通訳の手話も、また、速い。
そうしないと聴者のナチュラルスピードの話に追いついて行けないからだ。
難聴者が手話を学ぶのは
コミュニケーションの一つの手がかりとして学ぶわけで、
別に手話通訳になるためではない。
にもかかわらず、
ちょっとばかり手話ができて、
やたらと格好をつけたがる者が(難聴者にも)いる。
速くやる必要のない指文字なども、
相手の理解かまわず、速くやりたがる。
ありゃあ、相手に伝えるためではなく、
自己満足のためにやっているとしか思えない。
(ROKU)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年08月19日
中途失聴・難聴者にとって手話とは
「やまびこドーム」(於 信州スカイパーク) Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014.8.19
<つぶやき万華鏡(投稿記事)>
中途失聴・難聴者にとって手話とは
聴覚障害者に関するいくつかの誤解のうち
「聴覚障害者=手話」
という誤解は、世の中の誤解(迷信)の最たるものであろう。
実際には、聴覚障害者のなかで、手話を第一言語とする者の割合は非常に少ない。
中途失聴・難聴者の大多数は手話ができない。
「手話ができない」
というよりも
「手話をやらない」。
実際に、中途失聴・難聴者が現実の社会・職場でやっていくなかで、、
「手話ができなければ困る」
という場面は、(特別なケースを除いては)ありえない。
「手話でなければ通じない病院」
とか、
「手話でなければ通じない役所」
などの話は、
現実には聞いたこともない。
地域や隣近所でも、手話は使われない。
家庭でも、ことに中途失聴・難聴者の家庭では、
家族が手話を使えない。
中途失聴・難聴者にとって手話は、
手話通訳(ろう者との仲介)をするためのものではなく、
仲間同士の、
コミュニケーションの手がかりとしての一手段にすぎない。
手話は、
中途失聴・難聴者が必ず学ばなければならないというものではない。
いくらかでも手話を知っていれば、
難聴者仲間同士の、
とりわけ、手話ができる聴者とのコミュニケーションで、
やはり便利で、
楽しいものであることを、、
私も大いに実感しています。
ただし、それは、私にとって、あくまで、
非日常
である。
手話は、
やらなきゃやらないでもすむことである。
手話は、(もしやるなら)
むしろ、遊び半分に、
大いに楽しめばいいと思う。
(ROKU)
2014年10月17日
難聴者の手話

特急「あずさ」(背景は高ボッチ高原) Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
難聴者が手話を学ぶのは通訳になるためではない
日曜日は Eテレ「ワンポイント手話」を見ています。
番組はインターネットで動画がアップされ、
何回でも復習することができるので、
ありがたいですね。
難聴者同士の手話の場合、
「パッパッパッ」
と速くやるのではなく、
相手の理解を確認しながら、
ゆっくりと進めると、
楽しいのではないかと思います。
(R)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年10月21日
手話は難しい
鎖川(くさりがわ)橋から北アルプス方面を望む
Photo by T.Sato
ここが、松本市 笹賀(ささが)と島立(しまだち)の堺です。
【鎖川】 朝日村の鉢盛山(はちもりやま)に源を発し松本市島立で奈良井川と合流する。
朝日村ではあさひプライムスキー場がある。
松本市に入ると大久保工業団地がある。
つりが盛んな川で渓流魚も多い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10月定例会のまとめ(速報)が長野難聴ホームページにアップされました。
ご覧ください。
http://nagano-nancho.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
≪手話はむずかしい≫
全国の聴覚障害の登録者(身体障害者手帳保持者)は約36万人。
そのうち手話を第一言語とされる方々(ろう者)は約20%と言われています。
高齢者など、登録していない聴障者を含めると、
耳の不自由な者は推定600万人を超える(WHO統計)、
補聴器販売店による統計では、1000万人という。
人生の途中まで確かに聞こえていたのだが、
どういうわけか途中から聞こえなくなった者たち、
「中途失聴・難聴者」と言います。
当然のことながら、
そのほとんどの者は手話ができません。
「こんにちは」
「私の名前は・・・」
「趣味は・・・」
そのくらいのところまでならなんとかなる。
しかし、そこから先が難しい。
ことに読み取りが難しい。
中途失聴・難聴者が手話をマスターするのは
至難の業です。
(R)
2015年01月24日
難聴者の筆談と手話
平成27年1月24日(土)

塩尻市内(並木通り)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
難聴者の筆談と手話
実際に、私は、
難聴者のくせに、
筆談はまったく苦手です。
聴者とのコミュニケーションでは、
ご面倒でも書いていただいている。
一方的に書いていただくわけで、
こちらから書くということは普通はありません。
相手が難聴者の場合は、
お互い、キーワードのみ、メモ書き程度の場合が多い。
「詳しくはあとで、メールでね!」
というわけで、
深入りするような話は、
ほとんどメールでやっています。
「今日はいい天気だね」
などの、日常のたわいない話は、
手話を使っています。
難聴者の場合、手話は、
情報保障の手段としてではなく、
仲間同士のちょっとした会話には便利です。
しかし、手話を情報保障の手段として使うということは、
難聴者にとっては困難である、
というのが普通だろうと思います。
2015.1.25
(ROKU)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩尻市内(並木通り)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
難聴者の筆談と手話
実際に、私は、
難聴者のくせに、
筆談はまったく苦手です。
聴者とのコミュニケーションでは、
ご面倒でも書いていただいている。
一方的に書いていただくわけで、
こちらから書くということは普通はありません。
相手が難聴者の場合は、
お互い、キーワードのみ、メモ書き程度の場合が多い。
「詳しくはあとで、メールでね!」
というわけで、
深入りするような話は、
ほとんどメールでやっています。
「今日はいい天気だね」
などの、日常のたわいない話は、
手話を使っています。
難聴者の場合、手話は、
情報保障の手段としてではなく、
仲間同士のちょっとした会話には便利です。
しかし、手話を情報保障の手段として使うということは、
難聴者にとっては困難である、
というのが普通だろうと思います。
2015.1.25
(ROKU)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月05日
手話の読み取り
JR篠ノ井線の車窓から・姨捨駅 (2/1定例会の帰途)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
手話の読み取り
かつて一生懸命に習った手話ですが・・・
だんだんと使う機会が減ってきて、我流の手話になりつつあります。
これは良くないこと、というのは頭ではよくわかっております。ハイ。
それにも増して、力が落ちてきたなと思うのは読み取り能力です。
自分で”手話の表現”をしている時には”自分の手話はまともなはずだ”とという自惚れがあります。
しかし、相手の手話を読み取る際には、自分の読み取り力が本当に試されます。
読めなかった手話でも、ちょっとした会話なら誤魔化すことも可能ですが、所詮会話は続きません。
顔なじみの人からでも、突然手話で語りかけられては、会話の予備知識が頭に準備できていないので、とっさには読めないことが多いものです。
また、テレビの手話ニュースや講演会などの手話同時通訳を、日常的に手話を使うろう者はきちんと読み取れているのでしょうか?
それらは、仲間同士の会話と違って、情報の事前共有がありませんし、”聞き返し”もできません。
実は案外読み取れていないのではないかと勘ぐっています。
”なんとなくわかった”というのが平均的な理解度でしょう。
(Legacy)
会員ブログ「信州の隠れ家より」から引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年04月12日
中途失聴・難聴者としての手話
≪つぶやき万華鏡≫
中途失聴・難聴者としての手話
手話は、個人的には、結構頑張っては、います。
でも、ろう者と同じように手話が使えるようになろうなんて思ってもいません。
また、日常の中で、普段は手話を使う場面はほとんどありません。
手話が有効であると実感した場面と言えば、
松本のA救急病院で看護師が手話を知っていらっしゃった、という場面。
「大丈夫!」とか、「待って!」とか、
入院中、ごく初歩的な手話でのコミュニケーションは、
(不謹慎な言い方ですが)、「楽しかった!」
手話の相手が聴者の場合、
こちらが読み取れさえすればコミュニケーションは成り立つわけで、
まずは、聴者の方の、初歩的な手話が読み取れるようになりたい、
というのが、当面の目標です。
講演会や講習会では、手話と要約筆記の両方がつく場合が多いが、
手話は読み取れない。
読み取れるように頑張らねば、という思いや努力は、もう、捨てた。
もうムリ!
日常の、ちょっとしたコミュニケーション手段として使えれば、
それでよい。
手話言語条例に関する私のスタンスは、あくまで後方支援。
ろう者の方々の活動を大いに応援している。
それ以上でも、それ以下でもない。
(ROKU)
2015.4.12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中途失聴・難聴者としての手話
手話は、個人的には、結構頑張っては、います。
でも、ろう者と同じように手話が使えるようになろうなんて思ってもいません。
また、日常の中で、普段は手話を使う場面はほとんどありません。
手話が有効であると実感した場面と言えば、
松本のA救急病院で看護師が手話を知っていらっしゃった、という場面。
「大丈夫!」とか、「待って!」とか、
入院中、ごく初歩的な手話でのコミュニケーションは、
(不謹慎な言い方ですが)、「楽しかった!」
手話の相手が聴者の場合、
こちらが読み取れさえすればコミュニケーションは成り立つわけで、
まずは、聴者の方の、初歩的な手話が読み取れるようになりたい、
というのが、当面の目標です。
講演会や講習会では、手話と要約筆記の両方がつく場合が多いが、
手話は読み取れない。
読み取れるように頑張らねば、という思いや努力は、もう、捨てた。
もうムリ!
日常の、ちょっとしたコミュニケーション手段として使えれば、
それでよい。
手話言語条例に関する私のスタンスは、あくまで後方支援。
ろう者の方々の活動を大いに応援している。
それ以上でも、それ以下でもない。
(ROKU)
2015.4.12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年05月05日
通じなかった手話

於 信州スカイパーク
噴水を 最も高め 子供の日 殿村菟絲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
手話が誤解のもとになることも
JR塩尻駅の窓口で
「耳が不自由です」
と書いてあるカードを見せながら
「簡易時刻表は200円ですか?」
と、手話を交えて質問した。
駅員は、手話を見て、
ガッテン!
とばかり
2冊の時刻表と、
「300円」の領収書を同時に渡してくれた。
(1冊150円×2=300円)
質問したとき、声もいくらか出したのだが、
不十分だったらしい。
なので
そのまま、二冊、買いこんできてしまいました。
(ROKU)
会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」より引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.5.5
2015年05月29日
手話を公用語化(パプアニューギニア)

於 フェリスクレール(塩尻)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
パプアニューギニア政府が聴覚障害者の知る権利を図るため、
手話を英語、ピジン英語、モツ語に次ぐ「4番目の公用語」に認定した。
こんなニュースを目にしました。
→ http://www.jiji.com/jc/zc?k=201505/2015052700630&g=int
地元の信濃毎日新聞(5/28)にも同様の記事がありました。
パプア・ニューギニア、すごいですね。
(Fumi)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.5.29
2015年07月19日
簡単な手話なら
≪つぶやき万華鏡≫
あるコンビニで
家の近くの、しばしば利用しているコンビニでのこと。
聴覚障害者にやさしい店員(女性)がいる。
お弁当をレジへ持っていくと店員が
レンジを指さして
「あたためますか?」
お箸を指さして
「お箸をつけますか?」
このように、そこにある現物を指さしながら言ってもらうと、
コミュニケーションができます。
こちらが手話で
「ありがとう」
とやると、
手話で「ありがとう」が返ってくる。
要約筆記者養成講座の
「聴覚障害者に対するコミュニケーション方法」
を、どこかで教わったことがあるのかな?
「手話はやりますか?」
と、聞いてみたら、
「いえ、いえ、全然!」
とのこと。
でも、その身振りが大きいので、
コミュニケーションは十分に成り立つ。
手話言語条例を制定したからといって、
世の中の人々が手話を使えるようになるとは、
到底思えないが
この程度の「手話」(コミュニケーション方法)なら
全国に広まるかもしれない。
手話をやらない難聴者でも、
「ありがとう」
の一つぐらいなら、
覚えられるだろうし、
とりあえずそれで十分だろう。
T.SATO
会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」7/16より引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.7.18 (SAT)
あるコンビニで
家の近くの、しばしば利用しているコンビニでのこと。
聴覚障害者にやさしい店員(女性)がいる。
お弁当をレジへ持っていくと店員が
レンジを指さして
「あたためますか?」
お箸を指さして
「お箸をつけますか?」
このように、そこにある現物を指さしながら言ってもらうと、
コミュニケーションができます。
こちらが手話で
「ありがとう」
とやると、
手話で「ありがとう」が返ってくる。
要約筆記者養成講座の
「聴覚障害者に対するコミュニケーション方法」
を、どこかで教わったことがあるのかな?
「手話はやりますか?」
と、聞いてみたら、
「いえ、いえ、全然!」
とのこと。
でも、その身振りが大きいので、
コミュニケーションは十分に成り立つ。
手話言語条例を制定したからといって、
世の中の人々が手話を使えるようになるとは、
到底思えないが
この程度の「手話」(コミュニケーション方法)なら
全国に広まるかもしれない。
手話をやらない難聴者でも、
「ありがとう」
の一つぐらいなら、
覚えられるだろうし、
とりあえずそれで十分だろう。
T.SATO
会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」7/16より引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.7.18 (SAT)
2015年11月16日
長野県手話言語条例(仮称)
長野県手話言語条例(仮称)
の骨子(案)について、県民意見公募手続(パブリックコメント)が開始されました。
詳細は、長野県ホームページをご覧ください。
→http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/shuwajorei/public.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.11.16 (MON)
の骨子(案)について、県民意見公募手続(パブリックコメント)が開始されました。
詳細は、長野県ホームページをご覧ください。
→http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/shuwajorei/public.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.11.16 (MON)
2016年03月15日
長野県議会の傍聴に参加して

報告 佐藤和宏 広報部長
3月14日、県庁にて長野県議会本会議の傍聴に参加してまいりました。
県議会で、手話言語条例が成立するとのことで、
聴覚障害者を中心に多くの傍聴者が集まりました。
県聴覚障害者協会関係者が100名経度、長野難聴は3名が参加しました。
他に盲ろう者が1名。計105名の傍聴者ということで最高記録だそうです。

13時からから始まった本会議で、いくつかの議案の説明と採決を経た後、
ようやく13時45分に中川議員(松本市選出)が
「長野県手話言語条例案」
の概要を説明し3分後には全会一致で採決されました。
その後、講堂にて傍聴者一同と県知事、条例制定に関わった3人
の議員などが一緒に記念撮影に収まりました。

17時からは、長野駅前の居酒屋で祝賀会が開催され、
44名が参加しました。
議員さん3名や、県の障がい者福祉担当職員なども参加され、
2時間半余りの盛会となりました。
なお、県レベルでの条例成立は鳥取、神奈川、群馬についで
4番目の早さです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【編註】この記事は、会員ブログ
「信州の隠れ家より」(3/15)から引用しました。(ROKU)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.3.15 (TUE)