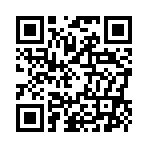2013年12月20日
障害者政策委員会 ニュースレター(No.16)
<全難聴からの配信です>
障害者政策委員会 ニュースレター(No.16)
2013.12.19
障害者政策委員会委員 全難聴副理事長 新谷友良
【第9回障害者政策委員会-障害者差別解消法基本方針の議論開始】
12 月13 日第9 回障害者政策委員会が開催され、障害者差別解消法(以下、解消法)の第6 条で決まっている基本方針の議論が始まり
ました。
議論に先立ち、12 月4 日国会で承認された障害者権利条約に関する説明が外務省からありました。条約は今後閣議承認を経て総理、
外務大臣の署名、天皇の認証後、批准書を国連事務総長へ寄託して30 日後に批准完了となるとの説明でした。
議論になったのは障害者政策委員会が条約33 条2 項の国内監視機関に当たるかという点です。岸田外務大臣は国会で「障害者政策委員会が条約にいう監視機関である」旨答弁していますが、外務省は「政策委員会は障害者基本計画への関与を通じて条約と関係する」と発言しました。
議論の末、外務省は「大臣答弁との間に齟齬はない」としましたが、障害者政策委員会が国内監視機関として明確に位置づけられるか、今後議論が必要な様子です。
その後、本題である解消法の基本方針の議論に入りましたが、基本方針の大きな枠組みについて、担当室から以下のポイントが示されました。
・対応要領、対応指針のばらつきを防ぐ
・法律、法案審議の政府答弁の範囲内で方針をまとめる
・個別事例を挙げるのではなく、要領・指針に盛り込むべきことを包括的に書く
議論の最初は、差別についての考え方でした。解消法を読んで頂くと分かりますが、解消法は差別の内容を規定していません。個別の要領・指針はある程度具体的な差別について書くことになりますので、基本指針では一般的な差別の規定が必要ではないかというのが問題の背景にあり、、障害者権利条約が差別についての規定を置いていますので、これに従うべきというのが委員の意見の大勢でした。
差別に関連しては、現在精神障害者の退院後収容施設を病院敷地内に作る計画が議論されています。この施策は差別的施策であり基本方針に何らかの方向性を示すべき、という意見が何人かの委員から出ましたが、基本方針でどのように記載されるかは不明です。
障害者差別解消法が個別分野を規定することなく、行政機関・事業者と切り分けたことによって、要領・指針で洩れる部分が出ることについて議論がありました。
解消法に先立つ障害者政策委員会の差別禁止部会意見は10 の分野を挙げて、分野ごとの差別の主体、具体的な差別の内容、求められる合理的配慮、差別を正当化する事由を規定しています。
この懸念に対して、省庁ごとに対象分野を特定して漏れを防ぐと担当室より説明がありました。
新谷よりは労働雇用分野での職務関連性の問題で発言しました。
私たち障害者は希望する会社に入れなかったり、就労後の異動などで希望する職種に付けないことが多くありますが、ほとんどの場合職務との関連性が理由にされます。
営業職の場合、失聴するとその仕事を外され他の業務に回されます。現在の職務を継続するために必要な合理的配慮が尽くされた上での止むを得ない措置がどうか、他の分野にも関連する課題と考えています。
※ サイドブログ「難聴者のアシタドーナル」に関連記事があります。
→ http://rokumangoku.naganoblog.jp/
障害者政策委員会 ニュースレター(No.16)
2013.12.19
障害者政策委員会委員 全難聴副理事長 新谷友良
【第9回障害者政策委員会-障害者差別解消法基本方針の議論開始】
12 月13 日第9 回障害者政策委員会が開催され、障害者差別解消法(以下、解消法)の第6 条で決まっている基本方針の議論が始まり
ました。
議論に先立ち、12 月4 日国会で承認された障害者権利条約に関する説明が外務省からありました。条約は今後閣議承認を経て総理、
外務大臣の署名、天皇の認証後、批准書を国連事務総長へ寄託して30 日後に批准完了となるとの説明でした。
議論になったのは障害者政策委員会が条約33 条2 項の国内監視機関に当たるかという点です。岸田外務大臣は国会で「障害者政策委員会が条約にいう監視機関である」旨答弁していますが、外務省は「政策委員会は障害者基本計画への関与を通じて条約と関係する」と発言しました。
議論の末、外務省は「大臣答弁との間に齟齬はない」としましたが、障害者政策委員会が国内監視機関として明確に位置づけられるか、今後議論が必要な様子です。
その後、本題である解消法の基本方針の議論に入りましたが、基本方針の大きな枠組みについて、担当室から以下のポイントが示されました。
・対応要領、対応指針のばらつきを防ぐ
・法律、法案審議の政府答弁の範囲内で方針をまとめる
・個別事例を挙げるのではなく、要領・指針に盛り込むべきことを包括的に書く
議論の最初は、差別についての考え方でした。解消法を読んで頂くと分かりますが、解消法は差別の内容を規定していません。個別の要領・指針はある程度具体的な差別について書くことになりますので、基本指針では一般的な差別の規定が必要ではないかというのが問題の背景にあり、、障害者権利条約が差別についての規定を置いていますので、これに従うべきというのが委員の意見の大勢でした。
差別に関連しては、現在精神障害者の退院後収容施設を病院敷地内に作る計画が議論されています。この施策は差別的施策であり基本方針に何らかの方向性を示すべき、という意見が何人かの委員から出ましたが、基本方針でどのように記載されるかは不明です。
障害者差別解消法が個別分野を規定することなく、行政機関・事業者と切り分けたことによって、要領・指針で洩れる部分が出ることについて議論がありました。
解消法に先立つ障害者政策委員会の差別禁止部会意見は10 の分野を挙げて、分野ごとの差別の主体、具体的な差別の内容、求められる合理的配慮、差別を正当化する事由を規定しています。
この懸念に対して、省庁ごとに対象分野を特定して漏れを防ぐと担当室より説明がありました。
新谷よりは労働雇用分野での職務関連性の問題で発言しました。
私たち障害者は希望する会社に入れなかったり、就労後の異動などで希望する職種に付けないことが多くありますが、ほとんどの場合職務との関連性が理由にされます。
営業職の場合、失聴するとその仕事を外され他の業務に回されます。現在の職務を継続するために必要な合理的配慮が尽くされた上での止むを得ない措置がどうか、他の分野にも関連する課題と考えています。
※ サイドブログ「難聴者のアシタドーナル」に関連記事があります。
→ http://rokumangoku.naganoblog.jp/
Posted by 六万石 at 16:04│Comments(0)
│全難聴