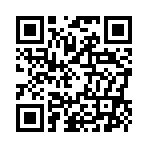2014年01月28日
障害者政策委員会ニュースレター(No.17)
全難聴より「障害者政策委員会ニュースレター(No.17)」 2014.1.23付 が発行されました。
【第10 回障害者政策委員会-障害者差別解消法基本方針団体ヒアリング】
1 月20 日第10 回障害者政策委員会が開催され、障害者差別解消法の基本方針について、8 つの障害者団体へのヒアリングが行われました。
ヒアリングに先立ち、外務省から、障害者権利条約の批准状況の報告がありました。これによりますと、1 月17 日国内公布の閣議決定があり、20 日に国連に付託して2 月19 日国内的に発効するとのことでした。
(その後、官報によって1 月20日が批准日となり、日本は141 番目の批准国となりました。)
今回のヒアリングに参加した団体は、
・弱視者問題研究会
・全国肢体不自由児者父母の会連合会
・全国失語症友の会連合会
・DPI 女性障害者ネットワーク
・日本ALS協会
・日本ダウン症協会
・日本てんかん協会(波の会)
・日本脳外傷友の会
で、障害者政策委員会に委員参加出来ていない団体が中心となりました。
それぞれの団体から、団体特有の差別的状況、必要な施策の説明がありました。なかでも、コミュニケーションに問題を抱える弱視者、失語症の方、脳機能障害の方からは、私たちと共通のコミュニケーション問題が提起され、コミュニケーションに係る課題の広がりが予想されます。弱視者の方から指摘された現行視覚障害の手帳判定基準の問題は、まさに我々中途失聴・難聴者の抱える手帳判定基準の問題と共通で、連帯した運動も必要ではないかと感じました。
障害者団体や関連団体へのヒアリングは次回2 月3 日開催の第11 回政策委員会でも継続されますが、それ以降のスケジュールは会議では示されませんでした。差別解消法の実効性は行政機関や事業者に対する対応要領、対応指針の出来具合に係りますが、その拠りどころとなるのが基本方針です。そのためのヒアリングには、企業・学校・医療など多方面の参加が必要と思い確認しましたが、地方自治体へのヒアリング実施以外のコメントは聞けませんでした。
なお、会議最後の意見交換の折手帳有無による差別の現れ方、サービスの受け方は解消法でも大きな問題となるので、基本方針の議論に含めるように発言しました。
基本方針の議論とは外れますが、差別解消法で地方に「障害者差別解消支援地域協議会」の設置が決まっています。これを具体化するために、内閣府より、有識者・経済団体・地方公共団体等と意見交換を行う「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」設置の提案がありました。
構成員を見ますと、8 人の委員のうち障害当事者はひとりで、政策委員より委員構成に疑問の声が出て決定とはなりませんでした。地方には法律の規定する障害関係の協議会が乱立気味で、目的・担当範囲を整理する意味でこのような検討会は必要とは思いますが、提案が唐突でした。
次回の政策委員会は2 月3 日です。
障害者政策委員会委員 全難聴副理事長 新谷友良
【第10 回障害者政策委員会-障害者差別解消法基本方針団体ヒアリング】
1 月20 日第10 回障害者政策委員会が開催され、障害者差別解消法の基本方針について、8 つの障害者団体へのヒアリングが行われました。
ヒアリングに先立ち、外務省から、障害者権利条約の批准状況の報告がありました。これによりますと、1 月17 日国内公布の閣議決定があり、20 日に国連に付託して2 月19 日国内的に発効するとのことでした。
(その後、官報によって1 月20日が批准日となり、日本は141 番目の批准国となりました。)
今回のヒアリングに参加した団体は、
・弱視者問題研究会
・全国肢体不自由児者父母の会連合会
・全国失語症友の会連合会
・DPI 女性障害者ネットワーク
・日本ALS協会
・日本ダウン症協会
・日本てんかん協会(波の会)
・日本脳外傷友の会
で、障害者政策委員会に委員参加出来ていない団体が中心となりました。
それぞれの団体から、団体特有の差別的状況、必要な施策の説明がありました。なかでも、コミュニケーションに問題を抱える弱視者、失語症の方、脳機能障害の方からは、私たちと共通のコミュニケーション問題が提起され、コミュニケーションに係る課題の広がりが予想されます。弱視者の方から指摘された現行視覚障害の手帳判定基準の問題は、まさに我々中途失聴・難聴者の抱える手帳判定基準の問題と共通で、連帯した運動も必要ではないかと感じました。
障害者団体や関連団体へのヒアリングは次回2 月3 日開催の第11 回政策委員会でも継続されますが、それ以降のスケジュールは会議では示されませんでした。差別解消法の実効性は行政機関や事業者に対する対応要領、対応指針の出来具合に係りますが、その拠りどころとなるのが基本方針です。そのためのヒアリングには、企業・学校・医療など多方面の参加が必要と思い確認しましたが、地方自治体へのヒアリング実施以外のコメントは聞けませんでした。
なお、会議最後の意見交換の折手帳有無による差別の現れ方、サービスの受け方は解消法でも大きな問題となるので、基本方針の議論に含めるように発言しました。
基本方針の議論とは外れますが、差別解消法で地方に「障害者差別解消支援地域協議会」の設置が決まっています。これを具体化するために、内閣府より、有識者・経済団体・地方公共団体等と意見交換を行う「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」設置の提案がありました。
構成員を見ますと、8 人の委員のうち障害当事者はひとりで、政策委員より委員構成に疑問の声が出て決定とはなりませんでした。地方には法律の規定する障害関係の協議会が乱立気味で、目的・担当範囲を整理する意味でこのような検討会は必要とは思いますが、提案が唐突でした。
次回の政策委員会は2 月3 日です。
障害者政策委員会委員 全難聴副理事長 新谷友良
Posted by 六万石 at 19:55│Comments(0)
│全難聴