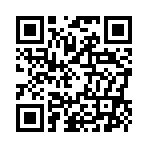2011年10月04日
第35回障がい者制度改革推進会議
<全難聴からの配信です>
障がい者制度改革推進会議だより(No.37) 2011.9.30
障がい者制度改革推進会議構成員全難聴常務理事新谷友良
第35 回制度改革推進会議
9 月26 日、第35 回制度改革推進会議が開催されました。前回も推進会議で障害者総合福祉法(仮称)の議論をしましたが、8月30日総合福祉部会が骨格提言の最終案をまとめましたので、今回はこの最終案に対する推進会議の議論でした。その結果、最終案は了承され18 時ごろ推進会議藤井議長代理より蓮舫障害者施策担当大臣に骨格提言を手交しました。
【骨格提言の概要と推進会議での質問】
骨格提言の正式な名前は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」となっており、「はじめ
に」に続いて、Ⅰ障害者総合福祉法の骨格提言、Ⅱ障害者総合福祉法の制定と実施への道程、Ⅲ関連する他の法律や分野との関係の3 部構成で、「おわりに」で締めくくられています。
障害者制度改革の趣旨を反映して、「谷間のない障害者サービスを構築し、支援を必要とするひとへ必要な支援を提供する」ことを目的とした提言となっています。
全難聴からは佐野事務局長が参加している55 名の総合福祉部会構成員の努力の成果です。本文121 ページの大部なものですが、みなさんも是非読んでいただきたいと思います。
推進会議で新谷は下記の3 点を質問しました。
1.私たち聴覚障害者は自立支援法の下で区分認定に基づくサービス利用を余りしていませんが、新法のもとでの「サービス利用計画」は、要約筆記利用や日常生活用具の支給申請にも必要とされるのか、と質問しました。これに対して、全てのサービスは「サービス利用計画」を前提とするが、それほど厳密なものとは考えず、サービス利用の必要性を優先したいと説明がありました。
2.提言では「サービス利用計画」に先立つ障害の認定のために、手帳にとどまらず医師の診断書、意見書でも良いとしています。これに対して、医師の診断書に「聴力の低下があり、日常生活に支障がある」という診断書を役所が受け取って果たして障害認定が出来るのか、身体障害者福祉法の障害認定にリンクしないと、役所も障害認定困るのではないか質問しましたが、これにたして、「日常生活に支障がある」ということを重視し、障害を判定することも可能という返事でした。
3.提言によると、従来実施してきた身体障害者実態調査に代わって「生活のしづらさ調査」実施されます。ご存じのように今までの調査では、日常生活でのコミュニケーション手段を聞いています。圧倒的多数は補聴器利用、次に筆談・要約筆記、手話利用は全体の20%以下というのは、この項目の調査結果です。「生活のしづらさ調査」ではこの設問がないので、従来調査の継続の必要性を聞きました。これに対して、新しい調査は準備を進めているのでこのまま進行すると考える、従来調査の扱いは厚労省が判断する、とコメントがありました。
障がい者制度改革推進会議だより(No.37) 2011.9.30
障がい者制度改革推進会議構成員全難聴常務理事新谷友良
第35 回制度改革推進会議
9 月26 日、第35 回制度改革推進会議が開催されました。前回も推進会議で障害者総合福祉法(仮称)の議論をしましたが、8月30日総合福祉部会が骨格提言の最終案をまとめましたので、今回はこの最終案に対する推進会議の議論でした。その結果、最終案は了承され18 時ごろ推進会議藤井議長代理より蓮舫障害者施策担当大臣に骨格提言を手交しました。
【骨格提言の概要と推進会議での質問】
骨格提言の正式な名前は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」となっており、「はじめ
に」に続いて、Ⅰ障害者総合福祉法の骨格提言、Ⅱ障害者総合福祉法の制定と実施への道程、Ⅲ関連する他の法律や分野との関係の3 部構成で、「おわりに」で締めくくられています。
障害者制度改革の趣旨を反映して、「谷間のない障害者サービスを構築し、支援を必要とするひとへ必要な支援を提供する」ことを目的とした提言となっています。
全難聴からは佐野事務局長が参加している55 名の総合福祉部会構成員の努力の成果です。本文121 ページの大部なものですが、みなさんも是非読んでいただきたいと思います。
推進会議で新谷は下記の3 点を質問しました。
1.私たち聴覚障害者は自立支援法の下で区分認定に基づくサービス利用を余りしていませんが、新法のもとでの「サービス利用計画」は、要約筆記利用や日常生活用具の支給申請にも必要とされるのか、と質問しました。これに対して、全てのサービスは「サービス利用計画」を前提とするが、それほど厳密なものとは考えず、サービス利用の必要性を優先したいと説明がありました。
2.提言では「サービス利用計画」に先立つ障害の認定のために、手帳にとどまらず医師の診断書、意見書でも良いとしています。これに対して、医師の診断書に「聴力の低下があり、日常生活に支障がある」という診断書を役所が受け取って果たして障害認定が出来るのか、身体障害者福祉法の障害認定にリンクしないと、役所も障害認定困るのではないか質問しましたが、これにたして、「日常生活に支障がある」ということを重視し、障害を判定することも可能という返事でした。
3.提言によると、従来実施してきた身体障害者実態調査に代わって「生活のしづらさ調査」実施されます。ご存じのように今までの調査では、日常生活でのコミュニケーション手段を聞いています。圧倒的多数は補聴器利用、次に筆談・要約筆記、手話利用は全体の20%以下というのは、この項目の調査結果です。「生活のしづらさ調査」ではこの設問がないので、従来調査の継続の必要性を聞きました。これに対して、新しい調査は準備を進めているのでこのまま進行すると考える、従来調査の扱いは厚労省が判断する、とコメントがありました。
Posted by 六万石 at 05:32│Comments(0)
│全難聴