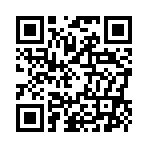2012年10月21日
長野難聴の防災ポスターから(4)
本日(21日)、県総合防災訓練が上田市で行われております。
災害情報展示パネルに提示しております協会の防災ポスターの内容をご紹介してきました。
内容は
(1)難聴者とは
(2)社会のバリアフリーとは
(3)難聴者の抱えるさまざまな問題
(4)特に、災害時における問題
となっています。4回に分割してご紹介してきましたが今回は、最終回で、(4)を掲載します。
ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。(広報部)
(4) 特に、災害発生時に支援していただきたいこと
普段の日常生活と異なり、災害などが発生したときには避難や災害支援を中心とする“的確な情報の把握”
がとても大切になります。
聞こえない人だけが大事な情報を知らないでいると、時には人命に係わることさえ起こりえます。
私たちは耳からの情報が入手することが困難というだけです。
ほとんどの場合、必要な情報が得られれば自立的に判断し、行動ができるのです。
そのためには・・・
■テレビ放送には日本語の“字幕”をつけて放映していただきたいということです。
最近はドラマやドキュメンタリー番組を中心に字幕放送が増えてきましたし、生放送のニュース番組にも字幕放送が徐々に付けられるようになってきました。
特に災害発生時には生放送で情報が伝えられることがほとんどです。
テレビ放送局による字幕制作体制などの充実と理解を求めます。
■避難所などにおいて、各種のお知らせなどの情報伝達は極力、文字による手段を併せて活用していただくことです。
たとえば、「この避難所に何々の支援物資の配給がある」というアナウンスの際に係員がハンドマイクのみで人々に伝えることが多いでしょう。その際、そのアナウンスに気づかない難聴者が不利益を蒙ることなどです。
後になって、周りの様子の変化に目で気づいても後の祭りだった・・・となってしまいます。
その際に、1 枚のメモやパネルや張り紙でもとにかく“文字”によって同等の情報を流してほしいのです。
そうすれば、大抵の場合は気づくでしょうし、平等に情報を得られるのです。
“音声情報”を難聴者に伝えるために・・・・
周りの誰にでもちょっとした気遣いで簡単にできる方法があるのです。
それは・・・「筆談」というものです。
手持ちのメモとペンで、難聴者が聞こえなくて困っている情報を内容をまとめて簡潔に記します。
その、ちょっとした行為によってその難聴者はどれほど助けられることでしょう。
少し詳しく情報を把握したいときには、筆談を何度か繰り返してコミュニケーションをとります。
また、難聴者に音声情報を文字に代えて伝える役目を果たす「要約筆記者」と呼ばれる人々がいます。
災害発生時にお願いしたいこと(まとめ)
1 テレビやラジオ、防災放送が分からないので文字情報がほしい
2 避難所では音声案内が分からないので黒板や電光掲示で文字で伝えて欲しい
3 ケガなどしたとき救命士や看護士、医師とのコミュニケーションが取れないので、カードや筆談で聞いてください
4 救急や避難所には要約筆記者も配備してください
5 自治体が設置する災害情報連絡網などを活用して、FAXや携帯メールで情報を受信出来る制度を広げてください
(終)
災害情報展示パネルに提示しております協会の防災ポスターの内容をご紹介してきました。
内容は
(1)難聴者とは
(2)社会のバリアフリーとは
(3)難聴者の抱えるさまざまな問題
(4)特に、災害時における問題
となっています。4回に分割してご紹介してきましたが今回は、最終回で、(4)を掲載します。
ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。(広報部)
(4) 特に、災害発生時に支援していただきたいこと
普段の日常生活と異なり、災害などが発生したときには避難や災害支援を中心とする“的確な情報の把握”
がとても大切になります。
聞こえない人だけが大事な情報を知らないでいると、時には人命に係わることさえ起こりえます。
私たちは耳からの情報が入手することが困難というだけです。
ほとんどの場合、必要な情報が得られれば自立的に判断し、行動ができるのです。
そのためには・・・
■テレビ放送には日本語の“字幕”をつけて放映していただきたいということです。
最近はドラマやドキュメンタリー番組を中心に字幕放送が増えてきましたし、生放送のニュース番組にも字幕放送が徐々に付けられるようになってきました。
特に災害発生時には生放送で情報が伝えられることがほとんどです。
テレビ放送局による字幕制作体制などの充実と理解を求めます。
■避難所などにおいて、各種のお知らせなどの情報伝達は極力、文字による手段を併せて活用していただくことです。
たとえば、「この避難所に何々の支援物資の配給がある」というアナウンスの際に係員がハンドマイクのみで人々に伝えることが多いでしょう。その際、そのアナウンスに気づかない難聴者が不利益を蒙ることなどです。
後になって、周りの様子の変化に目で気づいても後の祭りだった・・・となってしまいます。
その際に、1 枚のメモやパネルや張り紙でもとにかく“文字”によって同等の情報を流してほしいのです。
そうすれば、大抵の場合は気づくでしょうし、平等に情報を得られるのです。
“音声情報”を難聴者に伝えるために・・・・
周りの誰にでもちょっとした気遣いで簡単にできる方法があるのです。
それは・・・「筆談」というものです。
手持ちのメモとペンで、難聴者が聞こえなくて困っている情報を内容をまとめて簡潔に記します。
その、ちょっとした行為によってその難聴者はどれほど助けられることでしょう。
少し詳しく情報を把握したいときには、筆談を何度か繰り返してコミュニケーションをとります。
また、難聴者に音声情報を文字に代えて伝える役目を果たす「要約筆記者」と呼ばれる人々がいます。
災害発生時にお願いしたいこと(まとめ)
1 テレビやラジオ、防災放送が分からないので文字情報がほしい
2 避難所では音声案内が分からないので黒板や電光掲示で文字で伝えて欲しい
3 ケガなどしたとき救命士や看護士、医師とのコミュニケーションが取れないので、カードや筆談で聞いてください
4 救急や避難所には要約筆記者も配備してください
5 自治体が設置する災害情報連絡網などを活用して、FAXや携帯メールで情報を受信出来る制度を広げてください
(終)
Posted by 六万石 at 06:37│Comments(0)
│難聴者と災害