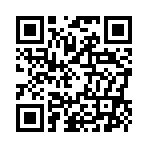2012年11月02日
男女共同参画フォーラムin長野(報告)
男女共同参画フォーラムin長野 (内閣府・長野県主催)
10月19日長野市で上記の集会がありました。
要約筆記付ということで、複数名の難聴者が参加しましたので報告します。
副会長 浜 富美子
日時:平成24年10月19日(金)12:30~16:00
場所:ホテルメトロポリタン長野
参加:300人強・県内外(難聴者2名)
来賓:阿部知事・平野県議会議長
内容
1,内閣府からの報告・・佐村知子内閣府男女共同参画局長(9/11局長に)
◆第3次男女共同参画基本計画の概要(H22,12に作られた)
「男女共同参画とは」男女が社会の対等な構成員として、
自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、
もって男女が均等に政治的、社会的、文化的利益を享受することができ、
かつ共に責任を担うべき社会・・
すなわち男性も女性も全ての個人が、喜びも責任も分かち合い、
その能力、個性を十分発揮することが出来る社会に。
◆3次重点分野・・15分野の内3分野(高齢者、障害者、外国人)等が安心して暮らせる環境の整備
科学技術、学術分野における男女共同参画
地域、防災、環境その他の分野における男女共同参画の推進
◆政策・方針決定過程への女性の参画拡大
指導的地位などに女性がしめる割合が1980年国家公務員2.5%30年かかって30%に。
政治分野では参議院で18.6その他は一桁。
◆政策・方針決定過程への女性の参画の拡大(ポジティブ・アクション)
政党への女性公認の働きかけ、
国家公務員・地方公共団体への要請、
公共契約を通じた女性の参画拡大
◆仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
男性も女性もあらゆる世代の誰もが、仕事や子育て、介護、自己啓発、地域活動など自分の希望するバランスで展開でき、仕事の充実と仕事以外の生活の充実の好循環をもたらす。
2,基調講演・・・・・・堂本暁子 前千葉県知事、元参議院議員
◆環境と災害――長野県は自然災害と森林、生物多様性の保全。
温暖化など人間活動による自然災害が増加
◆災害のリスク削減――被害を最小限にする。
(起きてからの支援ではなく予防・減災を深く考えていく)
◆3.11東日本大震災からの復興基本方針――
復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進する。
あわせて子供、障害者などあらゆる人々が住みよい共生社会を実現する。
高齢化や人口減少等に対応した新しい地域つくりを。
◆被災地視察――
浮き彫りになってきた避難所の課題 (間仕切りもなくプライバシーがない)
◆災害・復興ネットワ-クーー
2012年2月10日に「復興推進委員会」設置女性委員が4名に。
12箇所に男女共同参画担当部署設置
◆7防災・復興に関する法律・計画の改正――
女性が声をあげたことで「防災基本計画」改正、
2012年6月22日災害対策基本法が改正、
※災害時の性別役割分担の排除
(お金をもらえる場には男性が、無料での炊き出しなどへは女性がはおかしい)
※意志決定の場への女性の参画
(介護・乳幼児を持つお母さん、保健師、看護士、学校の先生等も)
※女性は災害のリジデス(回復力)――
コミ能力、底力・・
平時にやっていないことは災害時に出来ない。平時の地域社会つくりを。
3,パネルディスカッション「男女共同参画の視点に立って災害に強い地域つくり」
コーディネーター・・清原桂子「ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事」
パネリスト・・・宗片恵美子「NPOイコールネット仙台代表理事」
相沢博文「栄村復興支援機構「結い」代表
両角真由美「下諏訪町消防団女性消防隊隊長
清原:1995年1月17日の阪神・淡路大震災時兵庫県立女性センター所長。
県部長を経て現職に。
この災害時近所の人に助けられた人は77%、
防災関係者に助けられた人は23%。
近隣の重要性。多世代混住が繋いだ生きる力に。
協働型学習・・えらい人の話を聞く、仲間と話しあうだけではなく、
取り組みに関わることが大事。
協働の地域作り
1,まず行動を起こす(出来ない理屈より出来る方法)
2,何回もやり直す(前例にとらわれない)
3,具体的な目の前の目標(見える化と達成感)
4,否定しない・ケチを付けない・プラスをつける。
5,違いを楽しむ(意見感性の違いから)
6,今を楽しむ(タテマエ・タテジワ・タニンゴトのワナ)
7,持ち運べる人間関係(ネットワーク・個人と個人の信頼に裏打ちされた人間関係)
宗片:平成15年に男女共同参画の推進を目的に発足したNPO。
2011年3月11日東日本大震災発生当時避難所支援を。
体育館での避難生活が四ヶ月に。
リーダーが男性のため女性への配慮に欠けた。
プライベート空間(仕切りが無い、
更衣室、授乳室)子供年よりをつれての避難。
介護施設、保育所も被災女性が担うことに。
女性ならではの物資が届かない(下着、化粧品、パット)
障害者を抱えた人は壊れた自室に戻ると支援物資が届かない。
震災後は仮設住宅にサロン活動を。
「地域を守る・大切な人を守るために」目標提言
1,私達の街の防災計画つくり
2,防災訓練の見直し
3,地域の防災にかかわる資源の確認
4,避難所ワークショップのすすめ
5,女性が防災の主体になる仕組みつくり
相沢:栄村震災5日後に復興支援団体として立ち上げ(社協)会員40名。
当初7箇所の避難所に1700名が避難。
「今、どうなっているのか」
「これからどうなるか」
が最大の心の不安だった。
今何をするのか?家の片付けなどの判断は女性の方が早い。
地域の課題は地域で解決するためには疑問がある。
今までは常会に女性は居なかった、今は全ての住民の意見を聞く場に。
自助・共助・互助・博愛がこれからは必要。
「マキは一本では燃えない」
両角:人口22,000人、下社湯の町。消防団員280名7分団に。
女性団は平成17年に発足現在団員7名。
予防・広報活動、応急手当・救護活動も。
平成18年の土砂災害では自発的に現場に着き土嚢作りを手伝った。
「女性だから」から「女性でも」に変わり男性団員や住民に理解が広まった。
年間250回の活動をしている。6市町村の女性団員との連携、
ネットワーク(救護訓練・予防啓発・地域祭り)
Q&A
長野市から:合併で村部が入った。栄村で良かったことは?
相沢 :2300人31部落、自分の財布は自分で持とうと。
離れた集落との連絡が密になったこと。
人と人がここに残るという思いが一つになっていたこと。
松本市から:リーダーの育成とマニュアル化を効率良くするには?
A:リーダーの育成は継続した養成講座を。
養成された人の行政での活用の道筋をつけること。
行政での養成をやりっぱなしではなく、系統的に繋げていくこと。
名簿の公開・交流会でのつながりなど。
上田市から:原発被害者への支援は?
A:避難所での地域コミュニティーのあり方の再構築
(排除しない・孤立させない・情報の共有・前向きな支え合い)
長野市から:災害に強い街作りとして女性の活用の話をしているが、現状ではトップは男性。トップに聞く耳が無ければダメなのでは?
両角:「10分で自分の取るスケジュールを作る」
災害があったらではなく、災害はいつもある。
相沢:トップの判断は大事。トップのやることに不満を出す前に地域が
「こうやるよ」という顔のみえた関係があること。
非常時にそれぞれが自分の出来る事・やることの判断が出来る事。
行政・団体のグレーゾーンは協働になる。
子供の感受性はすごい、それらも尊重して。
宗片:トップが男性なら・女性ならと決めつけないで、
どうした形で避難所を運営するか?
平時にやってみるのも良い。
避難所の設営と運用は違う(人権を守る最低限は必要)。
以上
10月19日長野市で上記の集会がありました。
要約筆記付ということで、複数名の難聴者が参加しましたので報告します。
副会長 浜 富美子
日時:平成24年10月19日(金)12:30~16:00
場所:ホテルメトロポリタン長野
参加:300人強・県内外(難聴者2名)
来賓:阿部知事・平野県議会議長
内容
1,内閣府からの報告・・佐村知子内閣府男女共同参画局長(9/11局長に)
◆第3次男女共同参画基本計画の概要(H22,12に作られた)
「男女共同参画とは」男女が社会の対等な構成員として、
自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、
もって男女が均等に政治的、社会的、文化的利益を享受することができ、
かつ共に責任を担うべき社会・・
すなわち男性も女性も全ての個人が、喜びも責任も分かち合い、
その能力、個性を十分発揮することが出来る社会に。
◆3次重点分野・・15分野の内3分野(高齢者、障害者、外国人)等が安心して暮らせる環境の整備
科学技術、学術分野における男女共同参画
地域、防災、環境その他の分野における男女共同参画の推進
◆政策・方針決定過程への女性の参画拡大
指導的地位などに女性がしめる割合が1980年国家公務員2.5%30年かかって30%に。
政治分野では参議院で18.6その他は一桁。
◆政策・方針決定過程への女性の参画の拡大(ポジティブ・アクション)
政党への女性公認の働きかけ、
国家公務員・地方公共団体への要請、
公共契約を通じた女性の参画拡大
◆仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
男性も女性もあらゆる世代の誰もが、仕事や子育て、介護、自己啓発、地域活動など自分の希望するバランスで展開でき、仕事の充実と仕事以外の生活の充実の好循環をもたらす。
2,基調講演・・・・・・堂本暁子 前千葉県知事、元参議院議員
◆環境と災害――長野県は自然災害と森林、生物多様性の保全。
温暖化など人間活動による自然災害が増加
◆災害のリスク削減――被害を最小限にする。
(起きてからの支援ではなく予防・減災を深く考えていく)
◆3.11東日本大震災からの復興基本方針――
復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進する。
あわせて子供、障害者などあらゆる人々が住みよい共生社会を実現する。
高齢化や人口減少等に対応した新しい地域つくりを。
◆被災地視察――
浮き彫りになってきた避難所の課題 (間仕切りもなくプライバシーがない)
◆災害・復興ネットワ-クーー
2012年2月10日に「復興推進委員会」設置女性委員が4名に。
12箇所に男女共同参画担当部署設置
◆7防災・復興に関する法律・計画の改正――
女性が声をあげたことで「防災基本計画」改正、
2012年6月22日災害対策基本法が改正、
※災害時の性別役割分担の排除
(お金をもらえる場には男性が、無料での炊き出しなどへは女性がはおかしい)
※意志決定の場への女性の参画
(介護・乳幼児を持つお母さん、保健師、看護士、学校の先生等も)
※女性は災害のリジデス(回復力)――
コミ能力、底力・・
平時にやっていないことは災害時に出来ない。平時の地域社会つくりを。
3,パネルディスカッション「男女共同参画の視点に立って災害に強い地域つくり」
コーディネーター・・清原桂子「ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事」
パネリスト・・・宗片恵美子「NPOイコールネット仙台代表理事」
相沢博文「栄村復興支援機構「結い」代表
両角真由美「下諏訪町消防団女性消防隊隊長
清原:1995年1月17日の阪神・淡路大震災時兵庫県立女性センター所長。
県部長を経て現職に。
この災害時近所の人に助けられた人は77%、
防災関係者に助けられた人は23%。
近隣の重要性。多世代混住が繋いだ生きる力に。
協働型学習・・えらい人の話を聞く、仲間と話しあうだけではなく、
取り組みに関わることが大事。
協働の地域作り
1,まず行動を起こす(出来ない理屈より出来る方法)
2,何回もやり直す(前例にとらわれない)
3,具体的な目の前の目標(見える化と達成感)
4,否定しない・ケチを付けない・プラスをつける。
5,違いを楽しむ(意見感性の違いから)
6,今を楽しむ(タテマエ・タテジワ・タニンゴトのワナ)
7,持ち運べる人間関係(ネットワーク・個人と個人の信頼に裏打ちされた人間関係)
宗片:平成15年に男女共同参画の推進を目的に発足したNPO。
2011年3月11日東日本大震災発生当時避難所支援を。
体育館での避難生活が四ヶ月に。
リーダーが男性のため女性への配慮に欠けた。
プライベート空間(仕切りが無い、
更衣室、授乳室)子供年よりをつれての避難。
介護施設、保育所も被災女性が担うことに。
女性ならではの物資が届かない(下着、化粧品、パット)
障害者を抱えた人は壊れた自室に戻ると支援物資が届かない。
震災後は仮設住宅にサロン活動を。
「地域を守る・大切な人を守るために」目標提言
1,私達の街の防災計画つくり
2,防災訓練の見直し
3,地域の防災にかかわる資源の確認
4,避難所ワークショップのすすめ
5,女性が防災の主体になる仕組みつくり
相沢:栄村震災5日後に復興支援団体として立ち上げ(社協)会員40名。
当初7箇所の避難所に1700名が避難。
「今、どうなっているのか」
「これからどうなるか」
が最大の心の不安だった。
今何をするのか?家の片付けなどの判断は女性の方が早い。
地域の課題は地域で解決するためには疑問がある。
今までは常会に女性は居なかった、今は全ての住民の意見を聞く場に。
自助・共助・互助・博愛がこれからは必要。
「マキは一本では燃えない」
両角:人口22,000人、下社湯の町。消防団員280名7分団に。
女性団は平成17年に発足現在団員7名。
予防・広報活動、応急手当・救護活動も。
平成18年の土砂災害では自発的に現場に着き土嚢作りを手伝った。
「女性だから」から「女性でも」に変わり男性団員や住民に理解が広まった。
年間250回の活動をしている。6市町村の女性団員との連携、
ネットワーク(救護訓練・予防啓発・地域祭り)
Q&A
長野市から:合併で村部が入った。栄村で良かったことは?
相沢 :2300人31部落、自分の財布は自分で持とうと。
離れた集落との連絡が密になったこと。
人と人がここに残るという思いが一つになっていたこと。
松本市から:リーダーの育成とマニュアル化を効率良くするには?
A:リーダーの育成は継続した養成講座を。
養成された人の行政での活用の道筋をつけること。
行政での養成をやりっぱなしではなく、系統的に繋げていくこと。
名簿の公開・交流会でのつながりなど。
上田市から:原発被害者への支援は?
A:避難所での地域コミュニティーのあり方の再構築
(排除しない・孤立させない・情報の共有・前向きな支え合い)
長野市から:災害に強い街作りとして女性の活用の話をしているが、現状ではトップは男性。トップに聞く耳が無ければダメなのでは?
両角:「10分で自分の取るスケジュールを作る」
災害があったらではなく、災害はいつもある。
相沢:トップの判断は大事。トップのやることに不満を出す前に地域が
「こうやるよ」という顔のみえた関係があること。
非常時にそれぞれが自分の出来る事・やることの判断が出来る事。
行政・団体のグレーゾーンは協働になる。
子供の感受性はすごい、それらも尊重して。
宗片:トップが男性なら・女性ならと決めつけないで、
どうした形で避難所を運営するか?
平時にやってみるのも良い。
避難所の設営と運用は違う(人権を守る最低限は必要)。
以上
Posted by 六万石 at 05:39│Comments(0)
│活動報告