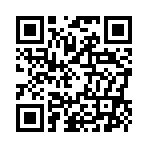2014年12月15日
全難聴福祉大会in三重(参加報告)
第20回全国中途失聴・難聴者福祉大会in三重 に参加して
浜 富美子
10月25日(土)から27日(月)まで三重県四日市市文化会館で、
20回目の全難聴福祉大会が行われ行ってきました。
私は女性部のお手伝いで前日の24日4時頃四日市に着き、
5時半から翌日に行うバザーの準備を手伝いました。
各協会の女性部から届いた手作り品などに名札を付け、
種類毎にまとめるなど9時頃まで作業が続きました。
第1日目25日は、朝からバザーの準備をし、売り子をしました。
13時から始まった分科会は、五つの分科会でした。
第1分科会は情報文化部主催の
「手書き文字通信、音声認識、こうすれば使える」
100名ほどの参加があったようです。
UD手書き音声認識アプリは1995年から青山大学や
シャムロックレコード社などで開発が進められてきた。
20年の研究で実用化に近づいたのはここ数年、
「難聴者が使うのでは無く、周りの健聴者に使ってもらう」
「出来ないことを出すより、どうしたら使えるか」
をやってきた。
自己完成度は80%。会議では男性の声の方が使いやすい、
誤変換があるなど、まだまだ問題はある。
第2分科会は要約筆記部
「要約筆記派遣事業の現状と厚生省モデル要綱の示す方向」
82名の参加.
派遣事業の「専門性・・・」が不明瞭、県や市町村のモデル要綱の紹介があった。
市町村は範囲が拡大された。
要約筆記の必要性の再検討、評価すべき。
要約筆記の倫理要綱の制定がされた。
群馬県が9月に出された。派遣要綱の中身を明確にしていかないといけない。
派遣費用の市町村格差も問題。
第3分科会女性部と制度改革主催
「難聴女性の差別解消を考える」
80名参加.。
難聴女性は「性」と「障害」と複合差別されている。
収入においても。
「データー無くして実績なし」事例の声を出していく必要がある。
普段の何気ない、おしゃべりの中に潜む心ない差別。
その解消は「差別」「不利益」に敏感に反応すること。
雇用障害者枠で入社しても実際には会議に通訳は認めないなど、
要約筆記への不理解や行政への参画にも電話のみとか理解されていないなど、
生活に根ざした発言が多く出された。
第4分科会補聴医療主催
「聞こえの健康支援センター」構想を深めて行こう
聞こえの支援センター構想について深めた。
病院側の「医療支援」と社会側の「社会支援」の連携に大きなギャップが問題。
国民の難聴者、特に中軽度の人への無理解。
生活のQOL評価の向上。
医療・社会支援との連携に貢献する資格の必要性などが討議された。
難聴者の疑似体験はむずかしい。
目は網膜、耳は脳。この違いが大きい。
第5分科会高年部と三重の共催
「まるごと三重」を体験しよう“
三重の取り組みの紹介と伊勢型紙体験” 68名参加
日本一バリアフリーの観光県だそうですが、聴覚障害者へのバリアーフリーは?
県立博物館は手で触れることが出来る展示、文字、犬のトイレなど。
観光バス用のループ、視覚表示情報などが推進されていると。
分科会では三重伝統工芸の伊勢型紙の切り絵体験もしました。
耳マーク部から
ループ設置場所を表示する「耳マーク」を作った。今後販売する。
今までの耳マークの右下にTの字を入れたマークです。
大会二日目
午前中、式典と前日の分科会の報告でした
来賓には「厚生労働省」「県知事」「四日市市長」「ろうあ連名」「全要研」など
25名ほどが壇上に並び爽快でした。
感謝状は前年の大会開催地沖縄難協に、
大会表彰は社会福祉厚生文化功労者に山口利勝氏、名倉順子氏、大野誠氏に贈られました。
大会宣言は開催地三重から。
大会決議は
記念講演
「合理的配慮がためされる社会を目指して」
障害者権利条約批准をうけと題し社会福祉法人AJU自立の家 専務理事 山田昭義氏の講演でした。
大会三日目
伊勢神宮参拝の観光
でしたが参加出来ませんでした。
伊勢には車で行ったことはあるが電車では初めてでした。
名古屋駅から近鉄の特急に乗って30分ぐらい、桑名の次でした。
近鉄乗り場や社内に電光掲示がなく心細い思いもしました。
今回は全難聴女性部の役員として、前日からのお手伝いでした。
女性部は先輩からの引き継ぎがよく繋がっていて、
活動資金集めのバザーも各協会から手作り品がたくさん提供されたのには驚きでした。
また、交流会中にバザーのPRをするなど一生懸命さには感服でした。
全体の流れはいつもと同じと思いますが、分科会になると一つしか出られないので、
あの分科会はどうだろうか?あそこの分科会はどんな内容だろう?と気にもなりました。
全国から仲間が集まりテーマに分かれて勉強、討議することは意義があることかもしれません。
親睦会もぎっしりでびっくりでした。
8名ほどのテーブルで北海道、福岡、名古屋の方など、初めてお会いする方々と一緒で、
協会の活動の様子などを聞く機会が出来てよかったと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
浜 富美子
10月25日(土)から27日(月)まで三重県四日市市文化会館で、
20回目の全難聴福祉大会が行われ行ってきました。
「ええじゃないか!伊勢の国」~のテーマで、全国から仲間が400名ほど参加して行われました。
一人ひとりの思いや願いを大切に出来る共生社会の実現を~
私は女性部のお手伝いで前日の24日4時頃四日市に着き、
5時半から翌日に行うバザーの準備を手伝いました。
各協会の女性部から届いた手作り品などに名札を付け、
種類毎にまとめるなど9時頃まで作業が続きました。
第1日目25日は、朝からバザーの準備をし、売り子をしました。
13時から始まった分科会は、五つの分科会でした。
第1分科会は情報文化部主催の
「手書き文字通信、音声認識、こうすれば使える」
100名ほどの参加があったようです。
UD手書き音声認識アプリは1995年から青山大学や
シャムロックレコード社などで開発が進められてきた。
20年の研究で実用化に近づいたのはここ数年、
「難聴者が使うのでは無く、周りの健聴者に使ってもらう」
「出来ないことを出すより、どうしたら使えるか」
をやってきた。
自己完成度は80%。会議では男性の声の方が使いやすい、
誤変換があるなど、まだまだ問題はある。
第2分科会は要約筆記部
「要約筆記派遣事業の現状と厚生省モデル要綱の示す方向」
82名の参加.
派遣事業の「専門性・・・」が不明瞭、県や市町村のモデル要綱の紹介があった。
市町村は範囲が拡大された。
要約筆記の必要性の再検討、評価すべき。
要約筆記の倫理要綱の制定がされた。
群馬県が9月に出された。派遣要綱の中身を明確にしていかないといけない。
派遣費用の市町村格差も問題。
第3分科会女性部と制度改革主催
「難聴女性の差別解消を考える」
80名参加.。
難聴女性は「性」と「障害」と複合差別されている。
収入においても。
「データー無くして実績なし」事例の声を出していく必要がある。
普段の何気ない、おしゃべりの中に潜む心ない差別。
その解消は「差別」「不利益」に敏感に反応すること。
雇用障害者枠で入社しても実際には会議に通訳は認めないなど、
要約筆記への不理解や行政への参画にも電話のみとか理解されていないなど、
生活に根ざした発言が多く出された。
第4分科会補聴医療主催
「聞こえの健康支援センター」構想を深めて行こう
聞こえの支援センター構想について深めた。
病院側の「医療支援」と社会側の「社会支援」の連携に大きなギャップが問題。
国民の難聴者、特に中軽度の人への無理解。
生活のQOL評価の向上。
医療・社会支援との連携に貢献する資格の必要性などが討議された。
難聴者の疑似体験はむずかしい。
目は網膜、耳は脳。この違いが大きい。
第5分科会高年部と三重の共催
「まるごと三重」を体験しよう“
三重の取り組みの紹介と伊勢型紙体験” 68名参加
日本一バリアフリーの観光県だそうですが、聴覚障害者へのバリアーフリーは?
県立博物館は手で触れることが出来る展示、文字、犬のトイレなど。
観光バス用のループ、視覚表示情報などが推進されていると。
分科会では三重伝統工芸の伊勢型紙の切り絵体験もしました。
耳マーク部から
ループ設置場所を表示する「耳マーク」を作った。今後販売する。
今までの耳マークの右下にTの字を入れたマークです。
大会二日目
午前中、式典と前日の分科会の報告でした
来賓には「厚生労働省」「県知事」「四日市市長」「ろうあ連名」「全要研」など
25名ほどが壇上に並び爽快でした。
感謝状は前年の大会開催地沖縄難協に、
大会表彰は社会福祉厚生文化功労者に山口利勝氏、名倉順子氏、大野誠氏に贈られました。
大会宣言は開催地三重から。
障害者権利条約が批准され、障害者基本法改正に続き障害者総合支援法が成立(2012年)障害者差別解消法成立(2013年)と国内法整備が進められました。制度の谷間にあった我々の福祉向上、社会的地位の確立を目指して今まで以上に難聴者運動を社会に広め、深めて行く必要がある。今こそ、学んだこと、気付いたことを社会に発信、還元することでお互いが新たな一歩を踏み出すことにつなげていこう。
大会決議は
「中途失聴・難聴者の権利に対する私達の取り組みの理念」8項目に亘って決議しました。
全ての中途失聴・難聴者が聞こえの程度に関係なく、一人の人間として尊重され、国民としての権利を享受し差別なく平等に地域社会の一員として認められることを目標としていきます」
記念講演
「合理的配慮がためされる社会を目指して」
障害者権利条約批准をうけと題し社会福祉法人AJU自立の家 専務理事 山田昭義氏の講演でした。
中学生の時、海水浴に行って飛び込みをしたときに頸骨を骨折して車いす生活になった。「福祉の町作り運動」に関わり、愛知県重度障害者の生活を良くする会で活動をしてきた。「鉄道もバスも店も車いすお断り」の時代、「エレベーターがほしい、トイレがほしいは」わがままと言われながらの活動だった。1981年の国際障害者年のテーマ「完全参加と平等」を機に障害者の概念も医療モデルから社会モデルに大きく変りバリアが少しずつ改善しはじめた。しかし、物理的バリアに目が向き、未だソフトの部分は旧態依然である。我が国のおいて一番問題点は、専門家が「障害とは」と言葉だけで繕うという言葉遊びでしか無い対応であること。これには今後の大きな課題が潜んでいる。このような講演だった。
障害者権利条約の理念はインクルーシブ社会の構築と合理的配慮を基盤として福祉の概念を医療的モデルから社会的モデルへの変換を強く求めるもので、障害を個人や家族の問題としてとらえるのでは無く、社会の問題として受け止める社会づくりを迫るものである。情報障害者には合理的配慮として、情報保障は社会が責任を持って進めることが求められ、一人一人への合理的配慮がためされない場合は、社会が差別していると解釈するべき。それが出来ない現在の社会を、私達の力で替えていくことが使命(ミッション)である。そして、いつまでに如何にどう変えるかの目標(ビジョン)を持つ事が団体の役割と思う。
大会三日目
伊勢神宮参拝の観光
でしたが参加出来ませんでした。
伊勢には車で行ったことはあるが電車では初めてでした。
名古屋駅から近鉄の特急に乗って30分ぐらい、桑名の次でした。
近鉄乗り場や社内に電光掲示がなく心細い思いもしました。
今回は全難聴女性部の役員として、前日からのお手伝いでした。
女性部は先輩からの引き継ぎがよく繋がっていて、
活動資金集めのバザーも各協会から手作り品がたくさん提供されたのには驚きでした。
また、交流会中にバザーのPRをするなど一生懸命さには感服でした。
全体の流れはいつもと同じと思いますが、分科会になると一つしか出られないので、
あの分科会はどうだろうか?あそこの分科会はどんな内容だろう?と気にもなりました。
全国から仲間が集まりテーマに分かれて勉強、討議することは意義があることかもしれません。
親睦会もぎっしりでびっくりでした。
8名ほどのテーブルで北海道、福岡、名古屋の方など、初めてお会いする方々と一緒で、
協会の活動の様子などを聞く機会が出来てよかったと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Posted by 六万石 at
02:06
│Comments(0)