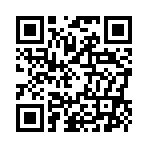2014年06月01日
サロンこだま「街中散策」報告
<地域活動>
サロンこだま 5月例会「街中散策」報告
こだまの会の5月例会は「民話に見る街中散策」でした。民話について調べて見たのですが、諏訪市内での特定な民話が見つからなかったので旧中山道沿いを歩くことにしました。
雨模様の26日。福祉センターを10時半頃出発。会員難聴者4名、要約筆記者4名の8名が最初の見学場所「貞松院」へ。初代高島藩主諏訪頼水公が開基婦人の院殿号をはいし廟所とした。家康の六男松平忠輝公も葬られている。庭には池の畔に、大きなしだれ桜があり花の時期にはライトアップされる。建物は古くお殿様の部屋や家老の部屋などを見ることが出来る。鶴の間、ウサギの間など唐紙で印されていた。諏訪百番霊場の西三十二番。由緒ある寺で有ることは知っていたが見学する機会はなかった。“貞かなる 松は寒きに色変えぬ
心を習へ頼む人々“(霊場詠歌)
昔ながら人だけが歩ける細い道を「手長神社」に向かう。上諏訪駅に ほど近い山側にあるこの神社は小さいが古い社。初代立川和四郎富棟による造営とか。神主の説明もおもしろかった。まず、礼拝の作法、手水の仕方、礼拝の仕方、石段の登り方など基本を知る。建物は火が怖いので彫刻には、水・海・波・貝などが掘られていると。また八岐大蛇を退治できたのはなぜか?現代でも八岐大蛇に置き換えてみると対策は立てられる。など神話から学ぶことは多くあるという。
18世紀にゴッホやセザンヌが活躍した時期に、日本ではすばらしい宮大工が活躍していた。立川流、大隅流はこの諏訪市の出身。遠くに行かなくても足下にすばらしい歴史・作品がある。と話してくださった。やはり、しっかりと説明などを聞くことでうっすらしか知らなかったことが分かり、本当に足下にもすばらしい物があることを知った例会でした。
手長・足長があり日本が作られていく民話。お酒の作り方、お酒のおかげで大蛇を退治することができたなど、民話への興味もかき立てられました。
歩いた範囲は2-3キロにこうした所があることを再確認する。小雨がぱらつきだし、早足で解散となりました。 (浜 記)
サロンこだま 5月例会「街中散策」報告
こだまの会の5月例会は「民話に見る街中散策」でした。民話について調べて見たのですが、諏訪市内での特定な民話が見つからなかったので旧中山道沿いを歩くことにしました。
雨模様の26日。福祉センターを10時半頃出発。会員難聴者4名、要約筆記者4名の8名が最初の見学場所「貞松院」へ。初代高島藩主諏訪頼水公が開基婦人の院殿号をはいし廟所とした。家康の六男松平忠輝公も葬られている。庭には池の畔に、大きなしだれ桜があり花の時期にはライトアップされる。建物は古くお殿様の部屋や家老の部屋などを見ることが出来る。鶴の間、ウサギの間など唐紙で印されていた。諏訪百番霊場の西三十二番。由緒ある寺で有ることは知っていたが見学する機会はなかった。“貞かなる 松は寒きに色変えぬ
心を習へ頼む人々“(霊場詠歌)
昔ながら人だけが歩ける細い道を「手長神社」に向かう。上諏訪駅に ほど近い山側にあるこの神社は小さいが古い社。初代立川和四郎富棟による造営とか。神主の説明もおもしろかった。まず、礼拝の作法、手水の仕方、礼拝の仕方、石段の登り方など基本を知る。建物は火が怖いので彫刻には、水・海・波・貝などが掘られていると。また八岐大蛇を退治できたのはなぜか?現代でも八岐大蛇に置き換えてみると対策は立てられる。など神話から学ぶことは多くあるという。
18世紀にゴッホやセザンヌが活躍した時期に、日本ではすばらしい宮大工が活躍していた。立川流、大隅流はこの諏訪市の出身。遠くに行かなくても足下にすばらしい歴史・作品がある。と話してくださった。やはり、しっかりと説明などを聞くことでうっすらしか知らなかったことが分かり、本当に足下にもすばらしい物があることを知った例会でした。
手長・足長があり日本が作られていく民話。お酒の作り方、お酒のおかげで大蛇を退治することができたなど、民話への興味もかき立てられました。
歩いた範囲は2-3キロにこうした所があることを再確認する。小雨がぱらつきだし、早足で解散となりました。 (浜 記)
Posted by 六万石 at 20:57│Comments(0)
│地域活動