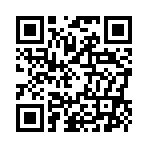2011年10月28日
来年度県要約筆記講座カリキュラム(案)
平成24年度 県要約筆記講座のカリキュラム(案)
報告 浜富美子
難聴者と要約筆記は「車の両輪」とまで言われ、全国的な流れと共に長野県中途失聴・難聴者協会でも要約筆記の普及と要約筆記奉仕員の養成に関わってきました。
特に1999年(平成11年)の厚生省からの「要約筆記奉仕員養成カリキュラム」が通達、2000年(平成12年)の「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改編され、要約筆記事業が第二種社会福祉事業として法定化された事で、要約筆記奉仕員養成の基礎・応用52時間のテキストが作成され、要約筆記奉仕員や要約筆記が一般社会に広がり始めました。
それに伴い利用者である私達も多くの社会的な場に出られるようになりました。各利用者のニーズも多様になり通訳者の身分保障も含め「奉仕員」ではなく「通訳者」を求める運動も同時にしてきました。
今年2011年(平成23年)3月30日付けで厚生労働省から社会福祉法の一部「要約筆記事業」の改正が通達されました。この通達により「要約筆記奉仕員」と「要約筆記者」とが明文化され、長野県でも来年度から要約筆記者養成に変更される予定です。
2年間で84時間の講座となり、通訳者として社会福祉に貢献できる通訳者を養成することになりました。
<平成24年度開講予定>前期カリキュラム(案)
第1回 1章 聴覚障害者の基礎知識・聴覚生理
難聴者のコミ・現状の課題
第2回 2章 要約筆記の基礎知識・難聴者の運動と要約筆記の歴史
要約筆記事業の位置づけ・通訳としての要約筆記
第3回 3章 日本語の基礎知識日本語の特徴・表記
日本語の語彙と用法・練習問題
第4回 4章 要約筆記の目的・三原則
要約筆記の表記・練習問題
第5回 実習 手書きコース・パソコンコース
手書きコース・パソコンコース
第6回 5章 話し言葉の学習・話し言葉の特徴・同時性・練習問題
短く表現する技術・共通情報
第7回 実習 手書きコース・パソコンコース
手書きコース・パソコンコース
第8回 6章 社会福祉の基礎知識・憲法と基本的人権・社会福祉の理念と歴史
日本の社会福祉・障害者福祉の概念
第9回 実習 手書きコース・パソコンコース
手書きコース・パソコンコース
第10回 7章 障害者運動と手話
8章 社会福祉事業の知識
<各回 午前2時間・午後2時間 計40時間>
・・・・ ご検討ください。
報告 浜富美子
難聴者と要約筆記は「車の両輪」とまで言われ、全国的な流れと共に長野県中途失聴・難聴者協会でも要約筆記の普及と要約筆記奉仕員の養成に関わってきました。
特に1999年(平成11年)の厚生省からの「要約筆記奉仕員養成カリキュラム」が通達、2000年(平成12年)の「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改編され、要約筆記事業が第二種社会福祉事業として法定化された事で、要約筆記奉仕員養成の基礎・応用52時間のテキストが作成され、要約筆記奉仕員や要約筆記が一般社会に広がり始めました。
それに伴い利用者である私達も多くの社会的な場に出られるようになりました。各利用者のニーズも多様になり通訳者の身分保障も含め「奉仕員」ではなく「通訳者」を求める運動も同時にしてきました。
今年2011年(平成23年)3月30日付けで厚生労働省から社会福祉法の一部「要約筆記事業」の改正が通達されました。この通達により「要約筆記奉仕員」と「要約筆記者」とが明文化され、長野県でも来年度から要約筆記者養成に変更される予定です。
2年間で84時間の講座となり、通訳者として社会福祉に貢献できる通訳者を養成することになりました。
<平成24年度開講予定>前期カリキュラム(案)
第1回 1章 聴覚障害者の基礎知識・聴覚生理
難聴者のコミ・現状の課題
第2回 2章 要約筆記の基礎知識・難聴者の運動と要約筆記の歴史
要約筆記事業の位置づけ・通訳としての要約筆記
第3回 3章 日本語の基礎知識日本語の特徴・表記
日本語の語彙と用法・練習問題
第4回 4章 要約筆記の目的・三原則
要約筆記の表記・練習問題
第5回 実習 手書きコース・パソコンコース
手書きコース・パソコンコース
第6回 5章 話し言葉の学習・話し言葉の特徴・同時性・練習問題
短く表現する技術・共通情報
第7回 実習 手書きコース・パソコンコース
手書きコース・パソコンコース
第8回 6章 社会福祉の基礎知識・憲法と基本的人権・社会福祉の理念と歴史
日本の社会福祉・障害者福祉の概念
第9回 実習 手書きコース・パソコンコース
手書きコース・パソコンコース
第10回 7章 障害者運動と手話
8章 社会福祉事業の知識
<各回 午前2時間・午後2時間 計40時間>
・・・・ ご検討ください。
Posted by 六万石 at 17:31│Comments(0)
│情報保障