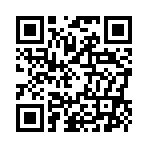2013年01月24日
全難聴要約筆記事業研修会の報告
全難聴 要約筆記事業研修会の報告
要約筆記対策部長 浜富美子
2013年1月12日~13日
静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」
参加者は90数名(要約筆記者と施設従事者・難聴者)
1,改正障害者基本法及び総合支援法における要約筆記事業の位置づけ
講師:厚生労働省情報支援専門官 田口雅之氏
「障害者総合支援法の意思疎通支援事業」がH25,4,1から施行される。
都道府県・政令都市、市町村の必須事業として4事業「手話通訳者派遣事業」「要約筆記者派遣事業」「手話通訳者設置事業」「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」が始まる。
・都道府県・政令都市の必須事業に「手話通訳者・要約筆記者の養成」「盲ろう者向け通訳、介助員の養成」がある。
・市町村の必須事業に「手話通訳者派遣」「要約筆記者派遣」「手話奉仕員養成」がある。「要約筆記奉仕員」の養成は任意事業として実施は妨げない。基本は「要約筆記奉仕員養成」はなくなった。
・知識、技能向上のための研修や養成は特別支援事業として「手話通訳者・士養成ステップアップ研修事業」「要約筆記者養成ステップアップ研修事業」「コミ支援従事者養成研修促進事業」「盲ろう者社会参加促進事業」などが「地域生活支援事業」として都道府県・市町村で行うようになった。
・国は指導者養成を団体に委託して行う「全国手話研修センター」「聴力障害者情報文化センター」「全国盲ろう者協会」「国立障害者リハビリテーションセンター」へ。
・障害者団体派遣については市町村が出来ない場合等への派遣は都道府県で。都道府県や市町村の要綱や単価の違いがあるので、国としての派遣要綱のガイドラインとを作成予定。市町村の裁量が大きい。
2,要約筆記事業に対する全難聴の取り組・総合支援法に対する協会の対応
講師:高岡正 理事長
「障害者総合支援法」の趣旨:障害者制度推進本部における検討を踏まえて、地域社会に於ける共生の実現に向け障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保険福祉施策を講ずるものとする。
基本理念:法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われる事を法律の基本理念として新たに掲げる。
骨格提言:1)必要な支援を受ける権利を確保する。2)全ての障害者を対象とする「谷間や空白の解消」3)市町村の財政力格差などによる格差是正。4)社会的入院等の「放置できない社会問題の解決」5)障害程度区分の廃止、6)これらの実施のため「安定した予算の確保」
要約筆記事業はどうか変わるか?
1)「コミ支援事業」から「意思疎通支援事業」に。
2)意思疎通支援を行う者の養成に、養成は都道府県の必須事業。
3)派遣は市町村必須+都道府県必須に。
4)広域派遣・団体派遣も。
5)聴覚障害者が集まる場への派遣
質疑の中で、奉仕員養成講座のカリは廃止。奉仕員養成を者の養成にすることはないと国の通知にある。サポーターとして難聴者活動に関わってもらう人を増やす取り組みも。
3,障害者福祉の動向
講師:新谷友良 副理事長
「障害者政策委員会の役割」・・21年に障害者制度改革推進会議の構成員として障害者権利条約の批准、障害者自立支援法の廃止を目指して法整備に取り組んでこられた。
制度改革推進会議で審議された大きな柱
1,障害者基本法」
2,障害者差別禁止法H25年4月国会提出」
3,障害者総合支援法H25年4月施行」
23年4月「障害者基本法改正案」を国会に上程。23年9月「骨格提言」を本部に提出、24年3月「障害者総合支援法」が閣議決定された。
24年5月障害者政策委員会が発足、24年6月「障害者総合支援法」が3党修正で可決成立。24年12月「新障害者基本計画」を委員会として意見取りまとめ。
「障害者基本法改正」での新旧対比の細部説明があった。情報コミュニケーション関連法規では総合支援レベルではなく基本法に書かれる。(情報の利用におけるバリアフリー等)第22条国及び地方公共団体は障害者が円滑に情報を取得し、利用し、その意志を表示し、並びに他人との意思疎通を計ることが出来るようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置、その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報アクセスと言語コミュニケーションの保障の地域社会における共生等)第3条三全て障害者は可能な限り言語(手話含)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が保障されると共に情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
「障害者差別禁止法」などかなり難しい内容での説明で1時間半では理解するところまではいきませんでした。
4,派遣要綱の読み方、考え方
講師:佐野昇 事務局長
○静岡モデル「手話通訳者派遣実施要綱を別に作成した理由」
1障碍者自立支援法で手話通訳者の養成事業・派遣事業とは全く違っていた
2手話通訳者派遣事業は平成18年障碍者自立支援法がスタートする前に県下全市町村で実施されていた
3手話通訳者派遣実施要綱がベースになっていたが根本から見直しして策定にすすめた。
○要約筆記者派遣実施要綱
1、H21年4月1日者の養成に基づく県の実施要綱の策定と県の通知
2、者養成への転機で派遣実施自治体での要綱策定へ
3、H23年市町モデル要綱の策定・通知
4、市町職員への意見交換会実施・・県主催
○実施要綱策定市町モデル
1,目的・・・・誰のため、何のため
2,用語の定義・聴覚障害者、事業の法的根拠、要約筆記者の規定
3,派遣の範囲・対象
4,他市町村等との相互通訳依頼
5,運営委員会の設置・・・・難協、要連、全要研支部
「私達抜きで私達事を決めないで」の気持ち。実施要綱は事業を行う場合の指針となるもの。委託をうける法人あるいは団体の意向で決められる事では無い。利用者団体又は担い手の要約筆記者関係が事業実施に関わり福祉制度の更なる前進を進めることが肝心。各地域の要綱を比較してみてほしい。
5,奉仕員から者への移行の取り組みの紹介○
名古屋市の様子・・・・・・・・名古屋市:荒川清美
1,23年3月の国から通知に会わせ23年度は「者の養成」「奉仕員から者への移行のための補講」「認定試験」三つの取り組みをしてきた
2,18年に「名古屋市要約筆記奉仕員連絡会」を解散し「名古屋市登録要約筆記者の会」を発足。養成講座時間も48時間から段階的に84時間までアップしてきた。受講料は2万円で推移している。
3,独自試験・・19年から奉仕員講座終了者に対し「筆記試験」と「実技試験」「面接試験」を実施。試験は合否ではなく実力の確認と難聴者への配慮についてのみであった。独自試験には市の担当者も立ち会う。全国統一試験には慎重姿勢。23年度の受験者手書きが38名合格19名。パソコン24名合格9名。
4,全国統一試験に合格した人は23年度24名。受験資格者は100~120名。
5,者事業の整備を完結するために・・「現任研修の補講」の継続実施1回500円の受講料をもらう。「制度の整備」奉仕員登録廃止、認定試験合格者の登録、派遣要綱を者に変更、派遣手当の単価の見直し
者の派遣がスタートしたばかりだが、要約筆記者のがんばりに支えられ何とか運営出来ている。いつかは者になると信じてその時のために準備してきた。
愛知、名古屋は要約筆記の始まりが早かった地域であることや大都市ということもあり、先を読んだ取り組みが出来ていたと感じた。
○静岡県の様子・・・・・・・・・・・静岡県 :佐野昇
1,委託事業委員会・・H11年に県立聴覚障害者情報センターが開所、要約筆記事業を受託してきた。H18年に県支部・県要連・静難協で「静岡県委託要約筆記事業委員会」の設立をセンターに報告。委員会からは108時間カリを要望。20年に補修パック研修を実施、市町職員との意見交換会の実施24年度まで継続実施、派遣要綱検討委員会を実施する。
2,19年度もセンターで養成を実施、20年から108時間カリが実施される。
3,23年度24年度と者の養成講座を開講、静岡市・三島市・浜松市なども実施。指導者講座への受講の取り組みと全国統一試験に取り組み24年2月の全国統一試験には29名が参加手書き7名、パソコン3名が合格。受験資格者は180名位いる。
6,要約筆記事業における難聴者・難聴者協会の役割 講師:高岡芳江氏
1,要約筆記をする人・・・スタートは文字に寄る支援、よき理解者だった。運動の支援者でもあった。
2,仕事内容が整理されボラ活動から情報保障へ(社会参加促進事業)
3,権利擁護の担い手へ・・・23年のカリが通知され法に基づく通訳へと(社会福祉、法律、権利擁護、など専門知識のある通訳者へ)
4,利用者として要約筆記に何を求めるのか「要約筆記通訳と筆談の二つの活動を持つ事を理解すること」「要約筆記の説明を自分の声で相手に会わせて説明出来ること」「自らの聴き管理を行えること」
5,難聴者の権利意識は向上したか「公的派遣が行われる意味」「行政へは要約筆記を付け目に見える形で示す」「現場経験で学ぶことは多い」「利用が少ないと説得力に欠ける」
6,今後の養成と派遣「権利の担い手の養成」「コーディネートの重要性」「運動団体としての役割」
7,難聴者講師の役割と難聴者運動の歴史・ 講師:藤谷弘晃要約筆記部長
1,国の指導者研修・・目的は者の養成を担う人を養成すること。受講者数23年度173名(内チシ者17名)24年度152名(内22名)計325名(21都府県)
2,課題・・・要約筆記者にとって・難聴者にとって要約筆記を学ぶ場ではない、要約筆記の知識を持っていて利用経験もあること。指導者としての認定の位置づけではないが地域での合意で選んでもらう。
3,求められる難聴者講師像・・「養成目標を理解していること」「要約筆記を利用し社会参加やコミでの充実感・達成感をもっている」「指導案・指導資料が作成できる」「指導力・説明力・質疑に答えられる」
4,求められる要約筆記者講師・・「知識・技術にかかわる専門性」「指導者としての適性」「受講生との信頼感の構築力」「リーダーシップと協調性」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
藤谷さんの模擬講義もありましたが、やはり利用する中で多くの事を学んでいる様子が伺え見習いたいと思いました。
二日間の研修に参加し法に守られている事はしっかり知る必要を感じました。法的に利用できることは利用者として声に出して行かなくてはいけないと強く感じました。会員の皆さんももっともっと、このような研修に参加していただきたいと思います。長い講義でまとめるのがうまく出来ませんでしたが、わずかでも知っていただけたら幸いです。(報告 浜富美子 H25,1)
要約筆記対策部長 浜富美子
2013年1月12日~13日
静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」
参加者は90数名(要約筆記者と施設従事者・難聴者)
1,改正障害者基本法及び総合支援法における要約筆記事業の位置づけ
講師:厚生労働省情報支援専門官 田口雅之氏
「障害者総合支援法の意思疎通支援事業」がH25,4,1から施行される。
都道府県・政令都市、市町村の必須事業として4事業「手話通訳者派遣事業」「要約筆記者派遣事業」「手話通訳者設置事業」「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」が始まる。
・都道府県・政令都市の必須事業に「手話通訳者・要約筆記者の養成」「盲ろう者向け通訳、介助員の養成」がある。
・市町村の必須事業に「手話通訳者派遣」「要約筆記者派遣」「手話奉仕員養成」がある。「要約筆記奉仕員」の養成は任意事業として実施は妨げない。基本は「要約筆記奉仕員養成」はなくなった。
・知識、技能向上のための研修や養成は特別支援事業として「手話通訳者・士養成ステップアップ研修事業」「要約筆記者養成ステップアップ研修事業」「コミ支援従事者養成研修促進事業」「盲ろう者社会参加促進事業」などが「地域生活支援事業」として都道府県・市町村で行うようになった。
・国は指導者養成を団体に委託して行う「全国手話研修センター」「聴力障害者情報文化センター」「全国盲ろう者協会」「国立障害者リハビリテーションセンター」へ。
・障害者団体派遣については市町村が出来ない場合等への派遣は都道府県で。都道府県や市町村の要綱や単価の違いがあるので、国としての派遣要綱のガイドラインとを作成予定。市町村の裁量が大きい。
2,要約筆記事業に対する全難聴の取り組・総合支援法に対する協会の対応
講師:高岡正 理事長
「障害者総合支援法」の趣旨:障害者制度推進本部における検討を踏まえて、地域社会に於ける共生の実現に向け障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保険福祉施策を講ずるものとする。
基本理念:法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われる事を法律の基本理念として新たに掲げる。
骨格提言:1)必要な支援を受ける権利を確保する。2)全ての障害者を対象とする「谷間や空白の解消」3)市町村の財政力格差などによる格差是正。4)社会的入院等の「放置できない社会問題の解決」5)障害程度区分の廃止、6)これらの実施のため「安定した予算の確保」
要約筆記事業はどうか変わるか?
1)「コミ支援事業」から「意思疎通支援事業」に。
2)意思疎通支援を行う者の養成に、養成は都道府県の必須事業。
3)派遣は市町村必須+都道府県必須に。
4)広域派遣・団体派遣も。
5)聴覚障害者が集まる場への派遣
質疑の中で、奉仕員養成講座のカリは廃止。奉仕員養成を者の養成にすることはないと国の通知にある。サポーターとして難聴者活動に関わってもらう人を増やす取り組みも。
3,障害者福祉の動向
講師:新谷友良 副理事長
「障害者政策委員会の役割」・・21年に障害者制度改革推進会議の構成員として障害者権利条約の批准、障害者自立支援法の廃止を目指して法整備に取り組んでこられた。
制度改革推進会議で審議された大きな柱
1,障害者基本法」
2,障害者差別禁止法H25年4月国会提出」
3,障害者総合支援法H25年4月施行」
23年4月「障害者基本法改正案」を国会に上程。23年9月「骨格提言」を本部に提出、24年3月「障害者総合支援法」が閣議決定された。
24年5月障害者政策委員会が発足、24年6月「障害者総合支援法」が3党修正で可決成立。24年12月「新障害者基本計画」を委員会として意見取りまとめ。
「障害者基本法改正」での新旧対比の細部説明があった。情報コミュニケーション関連法規では総合支援レベルではなく基本法に書かれる。(情報の利用におけるバリアフリー等)第22条国及び地方公共団体は障害者が円滑に情報を取得し、利用し、その意志を表示し、並びに他人との意思疎通を計ることが出来るようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置、その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報アクセスと言語コミュニケーションの保障の地域社会における共生等)第3条三全て障害者は可能な限り言語(手話含)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が保障されると共に情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
「障害者差別禁止法」などかなり難しい内容での説明で1時間半では理解するところまではいきませんでした。
4,派遣要綱の読み方、考え方
講師:佐野昇 事務局長
○静岡モデル「手話通訳者派遣実施要綱を別に作成した理由」
1障碍者自立支援法で手話通訳者の養成事業・派遣事業とは全く違っていた
2手話通訳者派遣事業は平成18年障碍者自立支援法がスタートする前に県下全市町村で実施されていた
3手話通訳者派遣実施要綱がベースになっていたが根本から見直しして策定にすすめた。
○要約筆記者派遣実施要綱
1、H21年4月1日者の養成に基づく県の実施要綱の策定と県の通知
2、者養成への転機で派遣実施自治体での要綱策定へ
3、H23年市町モデル要綱の策定・通知
4、市町職員への意見交換会実施・・県主催
○実施要綱策定市町モデル
1,目的・・・・誰のため、何のため
2,用語の定義・聴覚障害者、事業の法的根拠、要約筆記者の規定
3,派遣の範囲・対象
4,他市町村等との相互通訳依頼
5,運営委員会の設置・・・・難協、要連、全要研支部
「私達抜きで私達事を決めないで」の気持ち。実施要綱は事業を行う場合の指針となるもの。委託をうける法人あるいは団体の意向で決められる事では無い。利用者団体又は担い手の要約筆記者関係が事業実施に関わり福祉制度の更なる前進を進めることが肝心。各地域の要綱を比較してみてほしい。
5,奉仕員から者への移行の取り組みの紹介○
名古屋市の様子・・・・・・・・名古屋市:荒川清美
1,23年3月の国から通知に会わせ23年度は「者の養成」「奉仕員から者への移行のための補講」「認定試験」三つの取り組みをしてきた
2,18年に「名古屋市要約筆記奉仕員連絡会」を解散し「名古屋市登録要約筆記者の会」を発足。養成講座時間も48時間から段階的に84時間までアップしてきた。受講料は2万円で推移している。
3,独自試験・・19年から奉仕員講座終了者に対し「筆記試験」と「実技試験」「面接試験」を実施。試験は合否ではなく実力の確認と難聴者への配慮についてのみであった。独自試験には市の担当者も立ち会う。全国統一試験には慎重姿勢。23年度の受験者手書きが38名合格19名。パソコン24名合格9名。
4,全国統一試験に合格した人は23年度24名。受験資格者は100~120名。
5,者事業の整備を完結するために・・「現任研修の補講」の継続実施1回500円の受講料をもらう。「制度の整備」奉仕員登録廃止、認定試験合格者の登録、派遣要綱を者に変更、派遣手当の単価の見直し
者の派遣がスタートしたばかりだが、要約筆記者のがんばりに支えられ何とか運営出来ている。いつかは者になると信じてその時のために準備してきた。
愛知、名古屋は要約筆記の始まりが早かった地域であることや大都市ということもあり、先を読んだ取り組みが出来ていたと感じた。
○静岡県の様子・・・・・・・・・・・静岡県 :佐野昇
1,委託事業委員会・・H11年に県立聴覚障害者情報センターが開所、要約筆記事業を受託してきた。H18年に県支部・県要連・静難協で「静岡県委託要約筆記事業委員会」の設立をセンターに報告。委員会からは108時間カリを要望。20年に補修パック研修を実施、市町職員との意見交換会の実施24年度まで継続実施、派遣要綱検討委員会を実施する。
2,19年度もセンターで養成を実施、20年から108時間カリが実施される。
3,23年度24年度と者の養成講座を開講、静岡市・三島市・浜松市なども実施。指導者講座への受講の取り組みと全国統一試験に取り組み24年2月の全国統一試験には29名が参加手書き7名、パソコン3名が合格。受験資格者は180名位いる。
6,要約筆記事業における難聴者・難聴者協会の役割 講師:高岡芳江氏
1,要約筆記をする人・・・スタートは文字に寄る支援、よき理解者だった。運動の支援者でもあった。
2,仕事内容が整理されボラ活動から情報保障へ(社会参加促進事業)
3,権利擁護の担い手へ・・・23年のカリが通知され法に基づく通訳へと(社会福祉、法律、権利擁護、など専門知識のある通訳者へ)
4,利用者として要約筆記に何を求めるのか「要約筆記通訳と筆談の二つの活動を持つ事を理解すること」「要約筆記の説明を自分の声で相手に会わせて説明出来ること」「自らの聴き管理を行えること」
5,難聴者の権利意識は向上したか「公的派遣が行われる意味」「行政へは要約筆記を付け目に見える形で示す」「現場経験で学ぶことは多い」「利用が少ないと説得力に欠ける」
6,今後の養成と派遣「権利の担い手の養成」「コーディネートの重要性」「運動団体としての役割」
7,難聴者講師の役割と難聴者運動の歴史・ 講師:藤谷弘晃要約筆記部長
1,国の指導者研修・・目的は者の養成を担う人を養成すること。受講者数23年度173名(内チシ者17名)24年度152名(内22名)計325名(21都府県)
2,課題・・・要約筆記者にとって・難聴者にとって要約筆記を学ぶ場ではない、要約筆記の知識を持っていて利用経験もあること。指導者としての認定の位置づけではないが地域での合意で選んでもらう。
3,求められる難聴者講師像・・「養成目標を理解していること」「要約筆記を利用し社会参加やコミでの充実感・達成感をもっている」「指導案・指導資料が作成できる」「指導力・説明力・質疑に答えられる」
4,求められる要約筆記者講師・・「知識・技術にかかわる専門性」「指導者としての適性」「受講生との信頼感の構築力」「リーダーシップと協調性」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
藤谷さんの模擬講義もありましたが、やはり利用する中で多くの事を学んでいる様子が伺え見習いたいと思いました。
二日間の研修に参加し法に守られている事はしっかり知る必要を感じました。法的に利用できることは利用者として声に出して行かなくてはいけないと強く感じました。会員の皆さんももっともっと、このような研修に参加していただきたいと思います。長い講義でまとめるのがうまく出来ませんでしたが、わずかでも知っていただけたら幸いです。(報告 浜富美子 H25,1)
Posted by 六万石 at 09:22│Comments(0)
│要約筆記