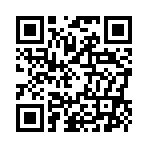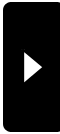2011年12月03日
信州大学「地震調査グループ」
<長野難聴会員ブログ「六万石」からの転載です>
信州大学「6.30松本地震」振動調査グループが広範囲の地域住民を対象に、22項目にわたるかなり大掛かりなアンケート行っている。
「6.30松本地震」では、震源から離れていても大きく揺れて被害が集中したなど、地域ごとにゆれ方がかなり違っていたことが明らかになっているが、今回の調査で、「地盤と揺れ方との関係を明らかにし、その結果を今後の防災対策に活用」しよう、というねらい。
地元の大学が研究室に閉じこもることなく地域に出て、地域に密着した研究・調査をするということで、わが常会でもこの調査に大いに協力しようということになった。
アンケートの提出先は常会長となっているが、当常会では、組長がこれを回収することになった。区長→常会長→組長という組織の系統は、かなり強力で、このルートを利用して、アンケートの回収率は飛躍的にあがるものと思われる。
地域の地震の解明が少しでも進むよう、信大振動調査グループの先生方には頑張ってもらいたい。(2011/11/30)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<参考:長野難聴会員ブログ「六万石」7/3の記事の転載です>
ご心配いただいています当地の地震について、正確な震源地が、まだ確定していないみたいです。
(1)気象庁が30日に発表した暫定値によると、震源地は中山霊園付近であると推測される。
この場合は牛伏寺断層ということになる。
(2)一方で、芳川村井、芳川小屋、笹賀周辺が震源地であるという見方もある。
この場合は、牛伏寺断層とは違う断層で、糸魚川静岡構造線という可能性もある。
普通、地震があれば、そこにたまっていたエネルギーが解放されるはず。
今回の地震はマグニチュード5.4。だから、きっと、かなりのエネルギーが解放されて、少し安心できる方向に向かったのではないか、希望的な方向もありうるとも、私は考えていたのですが・・・・
「牛伏寺断層に現在、M8レベルのエネルギーがたまっている状態だとすると、今回のM5.4という規模は、
現在たまっているエネルギーの4000分の1にすぎない」(=「タウン情報」塚原弘昭・信大名誉教授)
わ! 4000分の1ですと?!
今回、どのぐらいのエネルギーが解放されたのだろうか?
8ー5.4=2.6で、残りは2.6ってことかなあ?
などとノーテンキなことを考えていた自分の無知が恥ずかしい。
「(震源が確定するまでは何とも言えないが)むしろ危険な方向へ向かっていると考えた方がよい」(塚原弘昭氏)
とも!
大変です。これは。
ちなみに、地震のエネルギーはマグニチュードの数字が1増えると32倍に、2増えると32×32で1024倍になるそうです。たとえば、M8の地震は、M6の地震の約1000倍ものエネルギーということになるんだそうです。
(2011.7.3 )
信州大学「6.30松本地震」振動調査グループが広範囲の地域住民を対象に、22項目にわたるかなり大掛かりなアンケート行っている。
「6.30松本地震」では、震源から離れていても大きく揺れて被害が集中したなど、地域ごとにゆれ方がかなり違っていたことが明らかになっているが、今回の調査で、「地盤と揺れ方との関係を明らかにし、その結果を今後の防災対策に活用」しよう、というねらい。
地元の大学が研究室に閉じこもることなく地域に出て、地域に密着した研究・調査をするということで、わが常会でもこの調査に大いに協力しようということになった。
アンケートの提出先は常会長となっているが、当常会では、組長がこれを回収することになった。区長→常会長→組長という組織の系統は、かなり強力で、このルートを利用して、アンケートの回収率は飛躍的にあがるものと思われる。
地域の地震の解明が少しでも進むよう、信大振動調査グループの先生方には頑張ってもらいたい。(2011/11/30)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<参考:長野難聴会員ブログ「六万石」7/3の記事の転載です>
ご心配いただいています当地の地震について、正確な震源地が、まだ確定していないみたいです。
(1)気象庁が30日に発表した暫定値によると、震源地は中山霊園付近であると推測される。
この場合は牛伏寺断層ということになる。
(2)一方で、芳川村井、芳川小屋、笹賀周辺が震源地であるという見方もある。
この場合は、牛伏寺断層とは違う断層で、糸魚川静岡構造線という可能性もある。
普通、地震があれば、そこにたまっていたエネルギーが解放されるはず。
今回の地震はマグニチュード5.4。だから、きっと、かなりのエネルギーが解放されて、少し安心できる方向に向かったのではないか、希望的な方向もありうるとも、私は考えていたのですが・・・・
「牛伏寺断層に現在、M8レベルのエネルギーがたまっている状態だとすると、今回のM5.4という規模は、
現在たまっているエネルギーの4000分の1にすぎない」(=「タウン情報」塚原弘昭・信大名誉教授)
わ! 4000分の1ですと?!
今回、どのぐらいのエネルギーが解放されたのだろうか?
8ー5.4=2.6で、残りは2.6ってことかなあ?
などとノーテンキなことを考えていた自分の無知が恥ずかしい。
「(震源が確定するまでは何とも言えないが)むしろ危険な方向へ向かっていると考えた方がよい」(塚原弘昭氏)
とも!
大変です。これは。
ちなみに、地震のエネルギーはマグニチュードの数字が1増えると32倍に、2増えると32×32で1024倍になるそうです。たとえば、M8の地震は、M6の地震の約1000倍ものエネルギーということになるんだそうです。
(2011.7.3 )
タグ :六万石
2012年01月24日
「近所」=「近助」
1月22日のNHK「ろう・難聴を生きる」の番組で、全難聴の小川光彦さんが出ていました。
災害時の情報伝達について、東日本大震災の教訓として、一つのシステムがダメならそれで終わりということにならないように、多様なシステムを整えておくことの重要性を語っておりました。
また、無線や携帯といった機械のシステムを整えることの重要性とともに、近所の人が助け合う、「近助」・「共助」ということの大切さも強調していました。
「災害が起きた→それ、通訳を派遣しろ」ではなくて、普段から、日頃から、要約筆記通訳派遣制度を利用して、ある程度勇気を出して、地域にとけこんでおくことが大切だと思います。
そのためには、日頃の通訳派遣に際して、自治体のご理解とご支援が必須です。
==posted by ROKU==
災害時の情報伝達について、東日本大震災の教訓として、一つのシステムがダメならそれで終わりということにならないように、多様なシステムを整えておくことの重要性を語っておりました。
また、無線や携帯といった機械のシステムを整えることの重要性とともに、近所の人が助け合う、「近助」・「共助」ということの大切さも強調していました。
「災害が起きた→それ、通訳を派遣しろ」ではなくて、普段から、日頃から、要約筆記通訳派遣制度を利用して、ある程度勇気を出して、地域にとけこんでおくことが大切だと思います。
そのためには、日頃の通訳派遣に際して、自治体のご理解とご支援が必須です。
==posted by ROKU==
2012年01月28日
第37回障がい者制度改革推進会議
<全難聴からの配信です>
障がい者制度改革推進会議だより(No.40) 2012.1.27
障がい者制度改革推進会議構成員 全難聴常務理事 新谷友良
第37 回制度改革推進会議「災害と障害者」
1月23日「災害と障害者」のテーマで第37回の推進会議を開催されました。
12 月に推進会議メンバーが現地調査を実施したことは前号で紹介しましたが、今回の会議では現地の活動の中核を担う
西浦(南相馬市健康福祉部長)
小野(JDF 宮城支援センター)、
小山(きょうされん岩手支援センター)、
白石(JDF 支援センターふくしま)、
八幡(ゆめ風基金)
の5 名の方の報告を中心に議論しました。
①要援護者支援の取組みをめぐって、
②安否の確認と支援ニーズの把握について、
③災害直後における障害者支援の仕組みの在り方について、
④復興にむけた障害者支援、
の4 つのテーマに分けて会議は進められましたが、基調となったのは今回の災害での障害者の死亡割合が一般の方の2 倍に上っているという衝撃的な事実です。
障害があるがために亡くなる人が多かった、また災害後の避難生活で過酷な状況を強いられている、その事実をどのように評価し、今後どのように対応していくのか、障害者を取り巻く課題が、災害という危機的な状況の中で凝縮して現われてきました。
要援護者支援については、南相馬市は「災害時要援護者名簿は個人情報について同意の得られた方を対象に策定し、民生委員、区長、消防団等に配布してあるが、今回の震災では地域全員の市民が避難となったため、機能しなかった。」と報告されました。
また、「個人情報保護法で制約があるが、特例があるので情報開示し、安否確認とニーズ把握できた。」と南相馬市から説明がありましたが、宮城県からは「被災している基礎自治体では手一杯。安否確認は自治体には困難」という報告もありました。安否確認という人の生死の事実に個人情報保護の壁があることに釈然としない思いが続いています。
災害直後の障害者支援に関しては福祉避難所のあり方が議論になりました。「県として制度がなかった。国、県等が主体として広域的に制度として福祉避難所の指定が必要」という報告と共に、「福祉避難所がどこにあってどのような障害者が避難しているか全く分からない。」という声もありました。
発災時には、福祉避難所の設置は現実には非常に困難であり、迅速に設置されていく一般避難所を災害弱者の存在を踏まえたものにしていくのが本来の姿ではないかと思います。
復興の問題は地域差が大きくあります。「地域で長く暮らせる復興計画を」という構成員の意見もありましたが、新谷よりは「福島の原発問題をどう考えるか。特区に止まらず、中通り・浜通りを大きな復興対象の地域考える必要がある。広島の20~30 個分の放射能。その影響受けた子どもたちが何代かつづく。世界ではじめての経験する歴史的な事業。大きな目で福島の議論が必要」と発言しました。
なお、会議でも再三議論になりましたが、現行の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」は活用されませんでした。この改善について1月31日に開催されます中央防災会議「災害時の避難に関する専門委員会」に問題を提起予定です。
次回会議は3 月12 日です。
障がい者制度改革推進会議だより(No.40) 2012.1.27
障がい者制度改革推進会議構成員 全難聴常務理事 新谷友良
第37 回制度改革推進会議「災害と障害者」
1月23日「災害と障害者」のテーマで第37回の推進会議を開催されました。
12 月に推進会議メンバーが現地調査を実施したことは前号で紹介しましたが、今回の会議では現地の活動の中核を担う
西浦(南相馬市健康福祉部長)
小野(JDF 宮城支援センター)、
小山(きょうされん岩手支援センター)、
白石(JDF 支援センターふくしま)、
八幡(ゆめ風基金)
の5 名の方の報告を中心に議論しました。
①要援護者支援の取組みをめぐって、
②安否の確認と支援ニーズの把握について、
③災害直後における障害者支援の仕組みの在り方について、
④復興にむけた障害者支援、
の4 つのテーマに分けて会議は進められましたが、基調となったのは今回の災害での障害者の死亡割合が一般の方の2 倍に上っているという衝撃的な事実です。
障害があるがために亡くなる人が多かった、また災害後の避難生活で過酷な状況を強いられている、その事実をどのように評価し、今後どのように対応していくのか、障害者を取り巻く課題が、災害という危機的な状況の中で凝縮して現われてきました。
要援護者支援については、南相馬市は「災害時要援護者名簿は個人情報について同意の得られた方を対象に策定し、民生委員、区長、消防団等に配布してあるが、今回の震災では地域全員の市民が避難となったため、機能しなかった。」と報告されました。
また、「個人情報保護法で制約があるが、特例があるので情報開示し、安否確認とニーズ把握できた。」と南相馬市から説明がありましたが、宮城県からは「被災している基礎自治体では手一杯。安否確認は自治体には困難」という報告もありました。安否確認という人の生死の事実に個人情報保護の壁があることに釈然としない思いが続いています。
災害直後の障害者支援に関しては福祉避難所のあり方が議論になりました。「県として制度がなかった。国、県等が主体として広域的に制度として福祉避難所の指定が必要」という報告と共に、「福祉避難所がどこにあってどのような障害者が避難しているか全く分からない。」という声もありました。
発災時には、福祉避難所の設置は現実には非常に困難であり、迅速に設置されていく一般避難所を災害弱者の存在を踏まえたものにしていくのが本来の姿ではないかと思います。
復興の問題は地域差が大きくあります。「地域で長く暮らせる復興計画を」という構成員の意見もありましたが、新谷よりは「福島の原発問題をどう考えるか。特区に止まらず、中通り・浜通りを大きな復興対象の地域考える必要がある。広島の20~30 個分の放射能。その影響受けた子どもたちが何代かつづく。世界ではじめての経験する歴史的な事業。大きな目で福島の議論が必要」と発言しました。
なお、会議でも再三議論になりましたが、現行の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」は活用されませんでした。この改善について1月31日に開催されます中央防災会議「災害時の避難に関する専門委員会」に問題を提起予定です。
次回会議は3 月12 日です。
2012年05月07日
つくばで竜巻
突風:つくばで竜巻か 30人以上けが 50棟以上損壊
http://mainichi.jp/select/news/20120506k0000e040154000c.html?inb=tw
つくば技術大学から4,5kmしか離れてないですね。関係者の皆さん大丈夫だったでしょうか。
地震と同様、竜巻も予測困難です。聴覚障害者は気づかないうちに巻き込まれてしまいそうです。(全難聴のブログから引用)
補聴器を外していれば、なにがなんだかわからないうちに巻き込まれることだろう。
補聴器を通して聞こえる風の音は、機械音になって聞こえるから、余計にこわいことだろう。
(ROKU)
2012年07月11日
県北部の地震
中野・木島平で震度5弱
昨日(7月10日)、県北部(中野・木島平)で、震度5弱の地震がありました。
震度5弱というのは、昨年の松本地震と同程度で、
かなり大きな揺れだったろうと推測します。
報道によると、建物の被害はあったものの、けが人なし、とのことですが、
長野市、須坂市の協会員、北信地区要約筆記のみなさん、
大丈夫だったでしょうか。
(編集部)
昨日(7月10日)、県北部(中野・木島平)で、震度5弱の地震がありました。
震度5弱というのは、昨年の松本地震と同程度で、
かなり大きな揺れだったろうと推測します。
報道によると、建物の被害はあったものの、けが人なし、とのことですが、
長野市、須坂市の協会員、北信地区要約筆記のみなさん、
大丈夫だったでしょうか。
(編集部)
2012年07月11日
県北部の地震・コメント
<長野市の仲間から>
Mさん、早速コメントをいれていただきありがとうございました。
(編集部)
地震の起きたときはお昼休みで「梅ちゃん先生」を見てました。
くつろいでいたので、びっくりしましたが短時間で収まったので被害などはありませんでした。
震源地周辺でガラスが割れるなどしたようですが、昨年の松本市地震 に比べ、
被害は小さかったみたいです。
遠方の協会員からもメールを頂き、ありがとうございました。
Posted by 長野市 <М> at 2012年07月11日
Mさん、早速コメントをいれていただきありがとうございました。
(編集部)
2012年08月04日
県防災訓練への参加について(副会長)
田沢会長、お疲れ様でした。
昨年の県の訓練(安曇野市)で、私が「怪我人」になった方法ですね。
こうした訓練は是非継続してやって欲しいです。
どなたか、ぜひ立候補お願いしたいです。 (副会長 浜 富美子)
昨年の県の訓練(安曇野市)で、私が「怪我人」になった方法ですね。
こうした訓練は是非継続してやって欲しいです。
どなたか、ぜひ立候補お願いしたいです。 (副会長 浜 富美子)
2012年09月19日
災害用ビブス
【地域難聴者の会】
塩尻市で、災害時に使用するビブスについてアンケートがありました。
昨年度、松本で作成したビブスにならい、
「聞こえません」
という文字がプリントされたものというのが原案です。
難聴者としては、「聞こえません」という文字よりも、
「耳が不自由です」
という文字の方が、より適切ではないか、という提案(要望)を出しました。
ビブスの文字については、
もちろん、地域で異なっても別に困ることはないのですが、
一応、報告しておきたいと思います。(S)
塩尻市で、災害時に使用するビブスについてアンケートがありました。
昨年度、松本で作成したビブスにならい、
「聞こえません」
という文字がプリントされたものというのが原案です。
難聴者としては、「聞こえません」という文字よりも、
「耳が不自由です」
という文字の方が、より適切ではないか、という提案(要望)を出しました。
ビブスの文字については、
もちろん、地域で異なっても別に困ることはないのですが、
一応、報告しておきたいと思います。(S)
2012年09月20日
災害用ビブスの文字
昨日の記事「災害ビブスの文字」について、副会長の浜さんからコメントをいただきました。
災害時のビブスですが、やはり「聞こえません」には抵抗がありますね。
昨日茅野市に行ったとき、茅野市でもビブスの要望をだすと言っていました。
文字については聞かなかった。
「耳が不自由です」の方が良いですね。
耳マークで出している文字を浸透させていく方向が良いかと思います。
役所から事前に声がかかった、という塩尻市の福祉行政に敬服します。
やはり、市に通訳者を置く事が必要ですね。
委託職員であってもその課の事でチシ者に関することには意見を言ってもらえますものね。
2012年09月27日
県防災訓練全体会議
県防災訓練全体会議
会長 田沢 秀喜
活動お疲れ様です
本日、県防災訓練全体会議に出席してきました。
訓練ナンバー20.23
難聴協会から3名は直接訓練参加
タンカに乗る役:1名 歩ける人の役:2名
集合時間: 消防 6:00~ 自治会 8:20~ 参加者 8:40~
消防本部 9:00~開始(隊長命令発令)
会場: 上田駅(お城口)
災害発生と同時に各駅の方から各駅の状況を伝えてもらう。
警察 配置員 指揮所へ
状況確認後 しなの鉄道誘導のもと、中へ入る
勝手に入場しないこと!
上空からヘリで撮影してる。
負傷者役 8:40に、しなの鉄道改札口付近の通路に集合
説明通訳者は付く
9:05に救助隊が来て避難開始
トリアージ 手当 重症者は実際に救急車で運ばれる。
残りの方は見学してください
☆ 資料は両面印刷で1cm近くあるので要約筆記のログを参考に報告しました。
不明な点がありましたら役員メールで。よろしくお願いします。
会長 田沢 秀喜
活動お疲れ様です
本日、県防災訓練全体会議に出席してきました。
訓練ナンバー20.23
難聴協会から3名は直接訓練参加
タンカに乗る役:1名 歩ける人の役:2名
集合時間: 消防 6:00~ 自治会 8:20~ 参加者 8:40~
消防本部 9:00~開始(隊長命令発令)
会場: 上田駅(お城口)
災害発生と同時に各駅の方から各駅の状況を伝えてもらう。
警察 配置員 指揮所へ
状況確認後 しなの鉄道誘導のもと、中へ入る
勝手に入場しないこと!
上空からヘリで撮影してる。
負傷者役 8:40に、しなの鉄道改札口付近の通路に集合
説明通訳者は付く
9:05に救助隊が来て避難開始
トリアージ 手当 重症者は実際に救急車で運ばれる。
残りの方は見学してください
☆ 資料は両面印刷で1cm近くあるので要約筆記のログを参考に報告しました。
不明な点がありましたら役員メールで。よろしくお願いします。
2012年10月01日
要約筆記のデモ(県防災訓練)
<長要連から>
県防災訓練(10月21日・上田市)で今年度も
要約筆記のデモンストレーション
を行います。
来てくださる方には
「要約筆記とは何ぞや」
をお知らせして、
できたら難聴者と筆談を体験していただけると良いかと思っています。
展示内容はだいたい例年通り。
☆県内要約筆記グループの場所を書いた地図、
☆難聴がどんな時に困るのか(ちらし)
☆支援グッズ
などです。
よろしくお願いします。
(長要連 Y)
県防災訓練(10月21日・上田市)で今年度も
要約筆記のデモンストレーション
を行います。
来てくださる方には
「要約筆記とは何ぞや」
をお知らせして、
できたら難聴者と筆談を体験していただけると良いかと思っています。
展示内容はだいたい例年通り。
☆県内要約筆記グループの場所を書いた地図、
☆難聴がどんな時に困るのか(ちらし)
☆支援グッズ
などです。
よろしくお願いします。
(長要連 Y)
2012年10月02日
災害時における難聴者への対応
【地域難聴者の会・塩尻】発
下記は、塩尻地区難聴者の会が、市のボランティア講座(10月6日)で発表する骨子です。
災害時における難聴者への対応について(案)
塩尻 難聴者の会
1.難聴者はどこにもいます。
身体障害者手帳を所持している者(聴力70デシベル以上損失者)は全国で約36万人。そのうち、ろう者(手話を第一言語とする者)は、約6万人。WHO(世界保健機関)による基準(聴力40デシベル以上損失)の難聴者は推定600万人。補聴器店の統計では1000万人をこえています。一つの常会の中に難聴者が、平均、複数名以上いるということです。そしてそのほとんどは、手話ができません。
2.補聴器は避難所のような場所では十分に機能しません。
補聴器は、静かなところでの1対1の会話では有効ですが、避難所のようなところでは、あまり機能しません。高性能の補聴器でも、3メートル以上離れると、会話が成り立ちません。後ろから呼ばれても気が付きません。ことに放送の音声は、補聴器では割れてしまい、言葉として聞き取れません。
3.まず、文字情報掲示板
緊急避難場所が設定されたら、掲示板を設置することが第一です。 放送の内容は、逐一、掲示板に示されないと、伝わりません。この最も簡単な伝達方法がもっとも対応が遅くなるのを、今までの区や常会の防災訓練で私たちは、何度も経験してきています。
4.耳が不自由であることを示すビブスなどが必要です。
聴障者がこれをつけていれば ボランティアや関係者だけでなく、どなたにも一目瞭然です。また、要約筆記者、手話通訳者も、一目でわかるようなビブスを着用することが必要です。(ビブスについては現在、福祉課で検討中)
5.筆談は、誰でもできます。
要約筆記者でなくても筆談はできます。いつでも、だれでも、どこでも使用できるように、筆談用具を避難所にも備えておくことが必要です。塩尻要約筆記グループが考案・作成した「筆談ホワイトボードノート」などの活用が望まれます。
6.情報機器の設置
難聴者にとってラジオはまったく機能しません。テレビも、字幕がついていないと機能しません。避難所には、塩尻市災害行政無線・文字表示機の設置が必要です。また、CS障害者放送デジタル受信機&文字・字幕放送デコーダー(商品名「アイドラゴン」)の設置も望まれます。
長野難聴塩尻難聴者の会「難聴者のアシタドーナル」から転載。
下記は、塩尻地区難聴者の会が、市のボランティア講座(10月6日)で発表する骨子です。
災害時における難聴者への対応について(案)
塩尻 難聴者の会
1.難聴者はどこにもいます。
身体障害者手帳を所持している者(聴力70デシベル以上損失者)は全国で約36万人。そのうち、ろう者(手話を第一言語とする者)は、約6万人。WHO(世界保健機関)による基準(聴力40デシベル以上損失)の難聴者は推定600万人。補聴器店の統計では1000万人をこえています。一つの常会の中に難聴者が、平均、複数名以上いるということです。そしてそのほとんどは、手話ができません。
2.補聴器は避難所のような場所では十分に機能しません。
補聴器は、静かなところでの1対1の会話では有効ですが、避難所のようなところでは、あまり機能しません。高性能の補聴器でも、3メートル以上離れると、会話が成り立ちません。後ろから呼ばれても気が付きません。ことに放送の音声は、補聴器では割れてしまい、言葉として聞き取れません。
3.まず、文字情報掲示板
緊急避難場所が設定されたら、掲示板を設置することが第一です。 放送の内容は、逐一、掲示板に示されないと、伝わりません。この最も簡単な伝達方法がもっとも対応が遅くなるのを、今までの区や常会の防災訓練で私たちは、何度も経験してきています。
4.耳が不自由であることを示すビブスなどが必要です。
聴障者がこれをつけていれば ボランティアや関係者だけでなく、どなたにも一目瞭然です。また、要約筆記者、手話通訳者も、一目でわかるようなビブスを着用することが必要です。(ビブスについては現在、福祉課で検討中)
5.筆談は、誰でもできます。
要約筆記者でなくても筆談はできます。いつでも、だれでも、どこでも使用できるように、筆談用具を避難所にも備えておくことが必要です。塩尻要約筆記グループが考案・作成した「筆談ホワイトボードノート」などの活用が望まれます。
6.情報機器の設置
難聴者にとってラジオはまったく機能しません。テレビも、字幕がついていないと機能しません。避難所には、塩尻市災害行政無線・文字表示機の設置が必要です。また、CS障害者放送デジタル受信機&文字・字幕放送デコーダー(商品名「アイドラゴン」)の設置も望まれます。
長野難聴塩尻難聴者の会「難聴者のアシタドーナル」から転載。
2012年10月04日
災害と難聴者
<投稿記事>
「難聴者はどこにでもいる(はずな)のだが、どこにいるのかがわからない」
といわれます。
実は私も、常会長を経験するまでは、
わが常会に耳の不自由な者は私一人だけ、
と思っていました。
要約筆記をつけて常会の仕事に取り組むうちに、
「実はうちの人も耳が不自由」
「家内が耳が不自由で・・」
と、申し出る方が何人かいらっしゃって、びっくりした経験があります。
「できることなら隠しておきたい」というのが、難聴者の心理です。
日常生活を送るだけならば、それでなんとかなるかもしれない。
しかし、避難所で団体で生活を共にするという際には、
隠していることは、本人が大変な不利益を被ることはもちろん、、
思いがけないトラブルの原因になったりすることも考えられます。
「要支援者」を「身体障害者手帳を持つ者」だけに矮小化してとらえるのではなく、
「常会には耳の不自由なものが必ず存在する」、
ということを前提として、災害に備えていかなくてはならないと思います。
(R)
「難聴者はどこにでもいる(はずな)のだが、どこにいるのかがわからない」
といわれます。
実は私も、常会長を経験するまでは、
わが常会に耳の不自由な者は私一人だけ、
と思っていました。
要約筆記をつけて常会の仕事に取り組むうちに、
「実はうちの人も耳が不自由」
「家内が耳が不自由で・・」
と、申し出る方が何人かいらっしゃって、びっくりした経験があります。
「できることなら隠しておきたい」というのが、難聴者の心理です。
日常生活を送るだけならば、それでなんとかなるかもしれない。
しかし、避難所で団体で生活を共にするという際には、
隠していることは、本人が大変な不利益を被ることはもちろん、、
思いがけないトラブルの原因になったりすることも考えられます。
「要支援者」を「身体障害者手帳を持つ者」だけに矮小化してとらえるのではなく、
「常会には耳の不自由なものが必ず存在する」、
ということを前提として、災害に備えていかなくてはならないと思います。
(R)
2012年10月17日
県総合防災訓練の情報
県総合防災訓練の情報(外部リンク)
協会ホームページに、21日開催の県総合防災訓練の情報(外部リンク)を掲載しました。
http://nagano-nancho.com/
協会も参加者リストに掲載されています。
ご一読ください。 <広報部長 佐藤和宏>
協会ホームページに、21日開催の県総合防災訓練の情報(外部リンク)を掲載しました。
http://nagano-nancho.com/
協会も参加者リストに掲載されています。
ご一読ください。 <広報部長 佐藤和宏>
2012年10月18日
長野難聴の防災ポスターから(1)
県総合防災訓練(10月21日)の際に災害情報展示パネルに提示予定の協会の防災ポスターの内容をご紹介していきます。
内容は
1.難聴者とは
2.社会のバリアフリーとは
3.難聴者の抱えるさまざまな問題
4.特に、災害時における問題
となっています。
4回に分割してご紹介していきますので、ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。
よろしくご検討の程をお願いします。(広報部)
(続く)
内容は
1.難聴者とは
2.社会のバリアフリーとは
3.難聴者の抱えるさまざまな問題
4.特に、災害時における問題
となっています。
4回に分割してご紹介していきますので、ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。
よろしくご検討の程をお願いします。(広報部)
1.難聴者とは?
日常生活、災害発生時にどんなことで困るのでしょうか?
耳が聞こえにくい人が地域の中に意外とたくさんいます。
自身では“難聴者”と自覚していない高齢者が多いのが実情です。
高齢になると一般に身体の衰えが進行しますが、聴力も当然徐々衰えてきます。
しかしそのことを日常生活で常に感じることは少なく、とりたてて不便も感じていないという方がほとんどです。
しかし、生まれつきあるいは若年のころから耳が聞こえない人は、はっきりと“難聴者”を自覚しているので、社会生活のさまざまな局面で聞こえないことの不利益を蒙っています。
そのため、聞こえに関する社会のバリアを少しでも解消しようとする当事者の取り組みが進められてきました。
私たちの「長野県中途失聴・難聴者協会」はその名称の通り、県内の難聴者を中心に結成されている当事者の団体です。
(続く)
2012年10月19日
長野難聴の防災ポスターから(2)
県総合防災訓練(10月21日)の際に災害情報展示パネルに提示予定の協会の防災ポスターの内容をご紹介しています。
内容は
(1)難聴者とは
(2)社会のバリアフリーとは
(3)難聴者の抱えるさまざまな問題
(4)特に、災害時における問題
となっています。4回に分割してご紹介していますが今回は、(2)を掲載します。
ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。(広報部)
(続く)
内容は
(1)難聴者とは
(2)社会のバリアフリーとは
(3)難聴者の抱えるさまざまな問題
(4)特に、災害時における問題
となっています。4回に分割してご紹介していますが今回は、(2)を掲載します。
ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。(広報部)
(2) “社会のバリア”とは具体的に何を指すのでしょうか。
例を挙げると・・・
●テレビの音声が聞き取りづらいので、面白い場面が出てきても家族と一緒に笑えない。
→ せっかく地デジ対応のテレビがあるんだら字幕放送をもっと増やしてくれればいいのに!
●事故発生時に電車のアナウンスがわからないので乗り換えに失敗した。
→ 車両のドアの上などに電光掲示板のような案内を流してもらえればいいのに・・・
●病院での呼び出しがわからなくて順番を後回しにされた・恥をかいた。また、診察の際に看護師の指示や医師の説明が
よくわからず、いやな思いを引きずったまま病院を後にした・・・
→ 番号掲示板の設置や、看護師が直接呼びに来てくれるように配慮してくれれば・・
●気に入った講演会に申し込みたいのだが、電話でしか受け付けてくれない仕組みになっている。
→ FAXでの受付くらい対応してほしいわ!またメールでの受付もあればいいね。
・・・これらの例はいずれも、私たちごく一部の当事者だけではなく、高齢者を中心にちょっと耳が遠いかなぁと感じている多くの人々にとっても必要な“社会の共有資源”のはずです。
(続く)
2012年10月21日
長野難聴の防災ポスターから(4)
本日(21日)、県総合防災訓練が上田市で行われております。
災害情報展示パネルに提示しております協会の防災ポスターの内容をご紹介してきました。
内容は
(1)難聴者とは
(2)社会のバリアフリーとは
(3)難聴者の抱えるさまざまな問題
(4)特に、災害時における問題
となっています。4回に分割してご紹介してきましたが今回は、最終回で、(4)を掲載します。
ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。(広報部)
(4) 特に、災害発生時に支援していただきたいこと
普段の日常生活と異なり、災害などが発生したときには避難や災害支援を中心とする“的確な情報の把握”
がとても大切になります。
聞こえない人だけが大事な情報を知らないでいると、時には人命に係わることさえ起こりえます。
私たちは耳からの情報が入手することが困難というだけです。
ほとんどの場合、必要な情報が得られれば自立的に判断し、行動ができるのです。
そのためには・・・
■テレビ放送には日本語の“字幕”をつけて放映していただきたいということです。
最近はドラマやドキュメンタリー番組を中心に字幕放送が増えてきましたし、生放送のニュース番組にも字幕放送が徐々に付けられるようになってきました。
特に災害発生時には生放送で情報が伝えられることがほとんどです。
テレビ放送局による字幕制作体制などの充実と理解を求めます。
■避難所などにおいて、各種のお知らせなどの情報伝達は極力、文字による手段を併せて活用していただくことです。
たとえば、「この避難所に何々の支援物資の配給がある」というアナウンスの際に係員がハンドマイクのみで人々に伝えることが多いでしょう。その際、そのアナウンスに気づかない難聴者が不利益を蒙ることなどです。
後になって、周りの様子の変化に目で気づいても後の祭りだった・・・となってしまいます。
その際に、1 枚のメモやパネルや張り紙でもとにかく“文字”によって同等の情報を流してほしいのです。
そうすれば、大抵の場合は気づくでしょうし、平等に情報を得られるのです。
“音声情報”を難聴者に伝えるために・・・・
周りの誰にでもちょっとした気遣いで簡単にできる方法があるのです。
それは・・・「筆談」というものです。
手持ちのメモとペンで、難聴者が聞こえなくて困っている情報を内容をまとめて簡潔に記します。
その、ちょっとした行為によってその難聴者はどれほど助けられることでしょう。
少し詳しく情報を把握したいときには、筆談を何度か繰り返してコミュニケーションをとります。
また、難聴者に音声情報を文字に代えて伝える役目を果たす「要約筆記者」と呼ばれる人々がいます。
災害発生時にお願いしたいこと(まとめ)
1 テレビやラジオ、防災放送が分からないので文字情報がほしい
2 避難所では音声案内が分からないので黒板や電光掲示で文字で伝えて欲しい
3 ケガなどしたとき救命士や看護士、医師とのコミュニケーションが取れないので、カードや筆談で聞いてください
4 救急や避難所には要約筆記者も配備してください
5 自治体が設置する災害情報連絡網などを活用して、FAXや携帯メールで情報を受信出来る制度を広げてください
(終)
災害情報展示パネルに提示しております協会の防災ポスターの内容をご紹介してきました。
内容は
(1)難聴者とは
(2)社会のバリアフリーとは
(3)難聴者の抱えるさまざまな問題
(4)特に、災害時における問題
となっています。4回に分割してご紹介してきましたが今回は、最終回で、(4)を掲載します。
ご意見やご要望がありましたらご指摘いただきたいと思います。(広報部)
(4) 特に、災害発生時に支援していただきたいこと
普段の日常生活と異なり、災害などが発生したときには避難や災害支援を中心とする“的確な情報の把握”
がとても大切になります。
聞こえない人だけが大事な情報を知らないでいると、時には人命に係わることさえ起こりえます。
私たちは耳からの情報が入手することが困難というだけです。
ほとんどの場合、必要な情報が得られれば自立的に判断し、行動ができるのです。
そのためには・・・
■テレビ放送には日本語の“字幕”をつけて放映していただきたいということです。
最近はドラマやドキュメンタリー番組を中心に字幕放送が増えてきましたし、生放送のニュース番組にも字幕放送が徐々に付けられるようになってきました。
特に災害発生時には生放送で情報が伝えられることがほとんどです。
テレビ放送局による字幕制作体制などの充実と理解を求めます。
■避難所などにおいて、各種のお知らせなどの情報伝達は極力、文字による手段を併せて活用していただくことです。
たとえば、「この避難所に何々の支援物資の配給がある」というアナウンスの際に係員がハンドマイクのみで人々に伝えることが多いでしょう。その際、そのアナウンスに気づかない難聴者が不利益を蒙ることなどです。
後になって、周りの様子の変化に目で気づいても後の祭りだった・・・となってしまいます。
その際に、1 枚のメモやパネルや張り紙でもとにかく“文字”によって同等の情報を流してほしいのです。
そうすれば、大抵の場合は気づくでしょうし、平等に情報を得られるのです。
“音声情報”を難聴者に伝えるために・・・・
周りの誰にでもちょっとした気遣いで簡単にできる方法があるのです。
それは・・・「筆談」というものです。
手持ちのメモとペンで、難聴者が聞こえなくて困っている情報を内容をまとめて簡潔に記します。
その、ちょっとした行為によってその難聴者はどれほど助けられることでしょう。
少し詳しく情報を把握したいときには、筆談を何度か繰り返してコミュニケーションをとります。
また、難聴者に音声情報を文字に代えて伝える役目を果たす「要約筆記者」と呼ばれる人々がいます。
災害発生時にお願いしたいこと(まとめ)
1 テレビやラジオ、防災放送が分からないので文字情報がほしい
2 避難所では音声案内が分からないので黒板や電光掲示で文字で伝えて欲しい
3 ケガなどしたとき救命士や看護士、医師とのコミュニケーションが取れないので、カードや筆談で聞いてください
4 救急や避難所には要約筆記者も配備してください
5 自治体が設置する災害情報連絡網などを活用して、FAXや携帯メールで情報を受信出来る制度を広げてください
(終)
2012年10月22日
防災訓練お疲れ様でした(広報部から)
昨日の防災訓練は大変お疲れ様でした。
広報部長 佐藤 和宏
当日はすばらしい晴天に恵まれました。
協会のパネル展示と会報バックナンバー配布も予定通り行いました。
お昼はすぐ近くの上田城跡公園で、
要約筆記者と一緒に歓談しながら交流できて
とてもよかったです。
協会HPの「活動報告」(10月定例会)に速報(写真)を掲載してあります。
是非、ご覧になってください。
田澤(会長)さんお大事になさってください。
広報部長 佐藤 和宏
当日はすばらしい晴天に恵まれました。
協会のパネル展示と会報バックナンバー配布も予定通り行いました。
お昼はすぐ近くの上田城跡公園で、
要約筆記者と一緒に歓談しながら交流できて
とてもよかったです。
協会HPの「活動報告」(10月定例会)に速報(写真)を掲載してあります。
是非、ご覧になってください。
田澤(会長)さんお大事になさってください。
2012年10月24日
県防災訓練に参加して(詳報)
県総合防災訓練に参加して
副会長 浜 富美子
今年の県総合防災訓練が上田市で行われました。
難聴者協会も10月例会として10名が参加しました。
主会場は「上田市千曲川市民緑地公園上堀グランド」、
サブ会場は城址公園体育館・信州上田医療センター・上田駅・うえだみなみ敬老園。
私達難聴者協会と長要連は上田駅での
「駅ホームでの怪我人救助」
と公園体育館での
「展示・福祉避難所作り」
二班に分かれて参加しました。
朝8時50分から駅での訓練に怪我人役2名、見学2名の協会員と通訳者3名で参加。
駅訓練への参加は私達の他に地元町内会の方々が30名ほどいました。
地震があり駅のホームにいた人達の中で「怪我人が出た」という想定です。
その中で動けない人3名、歩けるが怪我した人10名とい設定で、
歩けない3名の中に田沢会長が入り、筆談で初期のやりとりを駅ホーム内で行った。
その後彼は担架で救護テントに運ばれました。
私は左手から血を流しているという想定役でした。
長野鉄道改札口前での全体説明には要約筆記者がつきましたので、
おおよその事は理解しました。
「駅ホームで出たら自分で対応してください」
と言われました。
そこからは通訳者無し。
怪我役には手のひらに入る小さな紙に怪我の状況が書かれている物を渡され、
後は個人演技でと。
ホームにブルーシートが敷かれ重傷者が横たわります。
責任者の方の説明があり、駅員が4-5名つきました。
救急隊員が現れ重傷者の対応を始めました。
私達3名と重傷の難聴者一人を残して町内会の方々と駅員が帰っていきました。
私達3名は担架で運ばれる仲間をズーと見ていました。
その後駅外へ出てみると町内会の10名ほどが固まって座っているのです。
「あれー、私も怪我人役だったのにあそこに入らなくていけないのかなあ」
とやっと気づいたのです。
あわてて、そこにいた消防隊員に聞いてみました。
彼は「俺たちは違う任務だから分らない」と。
そこでずかずかと怪我人の所にいる隊員に声を書けてみました。
「私怪我人役ですがどうしたらいいでしょうか」
そこで初めて、聞き取りが始まり
「聞こえないので質問がわかりません」
そばにいた通訳者が通訳をしてくださり
“トリアージ”の札を手に着けてもらうことが出来ました。
この訓練で聞こえない事で取り残される事を実感しましたと同時に、
駅員が何もしない。ただ、そこに立っているだけで周りの乗客に声を掛ける出もなく、
ましてや「ボードに書く」事などしませんでした。
その後隊員だけの「異臭発生訓練」でも見物人に対して駅員は何もしないのです。
このことがはっきり分ったので、次回には生かして欲しいと思いました。
「展示・避難所」会場ではドコモの「171災害用伝言ダイヤル」の実体験もしました。
「携帯電話やパソコンに慣れないので、いざ の時使えないかも?」と話したら
「毎月1日と15日に体験して慣れてください」とのことでした。
みんなさんも体験してみてください。(使い方のパンフ頂いてきました)
福祉避難所作りには参加出来ませんでしたが感想発表に参加できました。
チシ・視覚・知障の3障害団体が参加していて、
・床のシートはアルミが良い、
・受付に手話通訳を、
・障害別の色分けテープを、
・通路のスペースを、
・そこにいる人の名前をだしたら、
・障害別色分けにしては?
・名前まで出す必要があるか?
・助けて欲しいのでたすきを常に持ち歩いている、
・足裏の感覚で分るように道しるべがほしい、
・目や耳から入ってくる情報を処理できない事もあるので囲いにはカーテンで見えないよう囲った。
などそれぞれの障害で要望や危険を出し合う事は他の障害を知る機会になりました。
今回は会場が大きく分散されていたことや会場への交通手段がなかったなど、
他会場の様子を見ることが出来なく残念に思いました。
米どころの上田らしく今までにない大きなおむすびを頂きました。
上空にはヘリコプターや駅前のビル・パレオの6階立ての屋上に、
はしご車の先端にバケットに乗った隊員が大きく揺れる中、
救助するところも見る事が出来すごいなあと思いました。
展示終了後は城址公園で難協・長要連の参加者みんなでおむすびを頂き、
普段出来ないおしゃべりをすることが出来よい例会になりました。
来年は諏訪が会場とのこと。今年の反省を来年に生かしていきたいと思います。
参加の皆さんお疲れ様でした。
☆気づいた事
1)駅舎内で聞こえない者は孤立してしまう。
駅員の積極的参加をお願いしたいのは、
○ ホームや駅内にいる人みんなに,分るように声・音声放送だけではなく,
ボードなどに書くなりしてほしい。
○ そこにいる多くの人に声かけしてほしい。
「大丈夫ですか?」「怪我しませんか?」など今回は一言もなかった。
○ ホームに通訳者がいなかった事はよい経験になった
○ 隊員の「書いて伝える」は、すばらしかった
○ 救護所には通訳は必要と感じた
2)福祉避難所工夫
そこにある物を使って自分たちの座るところを作るのも必要かとは思いますが、
はじめから介助者同伴での設営でなく、
避難所に到着した所から介助者に繋げられる様な
横の訓練も必要ではないかと感じました。
副会長 浜 富美子
今年の県総合防災訓練が上田市で行われました。
難聴者協会も10月例会として10名が参加しました。
主会場は「上田市千曲川市民緑地公園上堀グランド」、
サブ会場は城址公園体育館・信州上田医療センター・上田駅・うえだみなみ敬老園。
私達難聴者協会と長要連は上田駅での
「駅ホームでの怪我人救助」
と公園体育館での
「展示・福祉避難所作り」
二班に分かれて参加しました。
朝8時50分から駅での訓練に怪我人役2名、見学2名の協会員と通訳者3名で参加。
駅訓練への参加は私達の他に地元町内会の方々が30名ほどいました。
地震があり駅のホームにいた人達の中で「怪我人が出た」という想定です。
その中で動けない人3名、歩けるが怪我した人10名とい設定で、
歩けない3名の中に田沢会長が入り、筆談で初期のやりとりを駅ホーム内で行った。
その後彼は担架で救護テントに運ばれました。
私は左手から血を流しているという想定役でした。
長野鉄道改札口前での全体説明には要約筆記者がつきましたので、
おおよその事は理解しました。
「駅ホームで出たら自分で対応してください」
と言われました。
そこからは通訳者無し。
怪我役には手のひらに入る小さな紙に怪我の状況が書かれている物を渡され、
後は個人演技でと。
ホームにブルーシートが敷かれ重傷者が横たわります。
責任者の方の説明があり、駅員が4-5名つきました。
救急隊員が現れ重傷者の対応を始めました。
私達3名と重傷の難聴者一人を残して町内会の方々と駅員が帰っていきました。
私達3名は担架で運ばれる仲間をズーと見ていました。
その後駅外へ出てみると町内会の10名ほどが固まって座っているのです。
「あれー、私も怪我人役だったのにあそこに入らなくていけないのかなあ」
とやっと気づいたのです。
あわてて、そこにいた消防隊員に聞いてみました。
彼は「俺たちは違う任務だから分らない」と。
そこでずかずかと怪我人の所にいる隊員に声を書けてみました。
「私怪我人役ですがどうしたらいいでしょうか」
そこで初めて、聞き取りが始まり
「聞こえないので質問がわかりません」
そばにいた通訳者が通訳をしてくださり
“トリアージ”の札を手に着けてもらうことが出来ました。
この訓練で聞こえない事で取り残される事を実感しましたと同時に、
駅員が何もしない。ただ、そこに立っているだけで周りの乗客に声を掛ける出もなく、
ましてや「ボードに書く」事などしませんでした。
その後隊員だけの「異臭発生訓練」でも見物人に対して駅員は何もしないのです。
このことがはっきり分ったので、次回には生かして欲しいと思いました。
「展示・避難所」会場ではドコモの「171災害用伝言ダイヤル」の実体験もしました。
「携帯電話やパソコンに慣れないので、いざ の時使えないかも?」と話したら
「毎月1日と15日に体験して慣れてください」とのことでした。
みんなさんも体験してみてください。(使い方のパンフ頂いてきました)
福祉避難所作りには参加出来ませんでしたが感想発表に参加できました。
チシ・視覚・知障の3障害団体が参加していて、
・床のシートはアルミが良い、
・受付に手話通訳を、
・障害別の色分けテープを、
・通路のスペースを、
・そこにいる人の名前をだしたら、
・障害別色分けにしては?
・名前まで出す必要があるか?
・助けて欲しいのでたすきを常に持ち歩いている、
・足裏の感覚で分るように道しるべがほしい、
・目や耳から入ってくる情報を処理できない事もあるので囲いにはカーテンで見えないよう囲った。
などそれぞれの障害で要望や危険を出し合う事は他の障害を知る機会になりました。
今回は会場が大きく分散されていたことや会場への交通手段がなかったなど、
他会場の様子を見ることが出来なく残念に思いました。
米どころの上田らしく今までにない大きなおむすびを頂きました。
上空にはヘリコプターや駅前のビル・パレオの6階立ての屋上に、
はしご車の先端にバケットに乗った隊員が大きく揺れる中、
救助するところも見る事が出来すごいなあと思いました。
展示終了後は城址公園で難協・長要連の参加者みんなでおむすびを頂き、
普段出来ないおしゃべりをすることが出来よい例会になりました。
来年は諏訪が会場とのこと。今年の反省を来年に生かしていきたいと思います。
参加の皆さんお疲れ様でした。
☆気づいた事
1)駅舎内で聞こえない者は孤立してしまう。
駅員の積極的参加をお願いしたいのは、
○ ホームや駅内にいる人みんなに,分るように声・音声放送だけではなく,
ボードなどに書くなりしてほしい。
○ そこにいる多くの人に声かけしてほしい。
「大丈夫ですか?」「怪我しませんか?」など今回は一言もなかった。
○ ホームに通訳者がいなかった事はよい経験になった
○ 隊員の「書いて伝える」は、すばらしかった
○ 救護所には通訳は必要と感じた
2)福祉避難所工夫
そこにある物を使って自分たちの座るところを作るのも必要かとは思いますが、
はじめから介助者同伴での設営でなく、
避難所に到着した所から介助者に繋げられる様な
横の訓練も必要ではないかと感じました。
2012年11月11日
地デジTVに河川情報
<これも知っとこ情報>
地デジTVに河川情報
国土交通省天竜川上流事務所と県などは、地上デジタルテレビ(データー放送)を使った河川水位と雨量情報の提供を始めた。長野放送局を配信局に、水位、雨量のデーターを配信。
「迅速な避難判断と避難行動に役立ててほしい」
と呼びかけている。
NHK総合の画面からリモコンで「データー放送」を選択し、「あなたのまちから」の項目へ。
メニュー内の「河川水位・雨量」を選ぶとリアルタイムに確認出来る。
情報は10分間隔で更新。
とあります。 (F)
地デジTVに河川情報
国土交通省天竜川上流事務所と県などは、地上デジタルテレビ(データー放送)を使った河川水位と雨量情報の提供を始めた。長野放送局を配信局に、水位、雨量のデーターを配信。
「迅速な避難判断と避難行動に役立ててほしい」
と呼びかけている。
NHK総合の画面からリモコンで「データー放送」を選択し、「あなたのまちから」の項目へ。
メニュー内の「河川水位・雨量」を選ぶとリアルタイムに確認出来る。
情報は10分間隔で更新。
とあります。 (F)