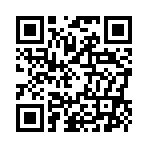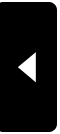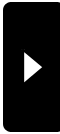2013年07月03日
県総合防災訓練は11月3日(日)
25年度の県総合防災訓練は11月3日(日)8時から13時まで、
諏訪市のイベント広場周辺で行われます。
例年通り協会として参加を予定したいと思います。
53項目の訓練が行われますが、昨年同様にいくつかの項目に参加できたらと思います。
・集団避難誘導訓練
・住民による救急救命訓練
・異臭事案による避難誘導訓練
・福祉避難所設置運営訓練
・救護所の開設・救護訓練
・災害などパネル展示
参加できそうな項目は以上の通りです。
どの項目に何人ぐらい参加可能か?
7月9日までに参加項目(人数)を県に提出します。
ご意見お願いします。
(副会長 浜)
続きを読む
諏訪市のイベント広場周辺で行われます。
例年通り協会として参加を予定したいと思います。
53項目の訓練が行われますが、昨年同様にいくつかの項目に参加できたらと思います。
・集団避難誘導訓練
・住民による救急救命訓練
・異臭事案による避難誘導訓練
・福祉避難所設置運営訓練
・救護所の開設・救護訓練
・災害などパネル展示
参加できそうな項目は以上の通りです。
どの項目に何人ぐらい参加可能か?
7月9日までに参加項目(人数)を県に提出します。
ご意見お願いします。
(副会長 浜)
続きを読む
2013年07月18日
県防災訓練(2)
県防災訓練打ち合わせ会
8月2日の第2回打ち合わせ会(諏訪市)に協会から、
浜副会長と佐藤(和)広報部長が代表で参加することになりました。
協会員皆様の、具体的な提案や要望等をお寄せください。

8月2日の第2回打ち合わせ会(諏訪市)に協会から、
浜副会長と佐藤(和)広報部長が代表で参加することになりました。
「具体的に自分達がやりたいことを持って参加したい」(浜副会長)
協会員皆様の、具体的な提案や要望等をお寄せください。
2013年09月02日
防災週間
防災週間です。(毎年8月30日~9月5日)。
1959年伊勢湾台風で受けた大被害をきっかけに、
翌1960年に、関東大震災の発生日(1923年9月1日)にちなんで定められたもの。
昨日は「防災の日」とあって、政府や自治体が全国で防災訓練などに取り組み、
マスコミでも報道されておりました。
聴覚障害者にとっては、何と言っても情報アクセスの不安があります。
県では、聴覚障害者を対象とした「防災行政無線文字表示器」を導入している自治体もありますが、全県的には、まだまだ広がっておりません。
我々の声を一層大きくしていく必要があると思います。(ROKU)

(塩尻市で導入されている防災行政無線文字表示器 2013.9.2現在)
1959年伊勢湾台風で受けた大被害をきっかけに、
翌1960年に、関東大震災の発生日(1923年9月1日)にちなんで定められたもの。
昨日は「防災の日」とあって、政府や自治体が全国で防災訓練などに取り組み、
マスコミでも報道されておりました。
聴覚障害者にとっては、何と言っても情報アクセスの不安があります。
県では、聴覚障害者を対象とした「防災行政無線文字表示器」を導入している自治体もありますが、全県的には、まだまだ広がっておりません。
我々の声を一層大きくしていく必要があると思います。(ROKU)
(塩尻市で導入されている防災行政無線文字表示器 2013.9.2現在)
2013年09月05日
地域防災計画
<投稿記事>

防災週間とあって、わが地域でも広報には防災に関する記事が満載。
おまけに、(付録として)
地域防災計画ダイジェスト(保存版)も地域住民に配布された。
内容は、
○防災の基本
○自助・共助
○災害への備え
○避難について
など、防災の基本となることがマニュアル的に書いてはある。
しかし、もっとも頼りになるはずの「ミニ防災」については、
具体的に書いてない。
だからこれを読んでも、いざと言うときの行動が
ダイナミックにイメージされない(できない)のではないかな。
(一言居士)

2013年09月06日
難聴者のつぶやき・「地震・雷・火事・津波」手話
<つぶやき万華鏡>(投稿記事)
「地震」
「雷(かみなり)」
「火事」
「津波」
の手話単語は難聴者も覚えるべきだ。
いや、国民みんなが覚えるべきだ。
学校教育で教えるべきだ。
(SHUWAリン)
2013年09月08日
木曽で震度3
災害の手話(9/7の記事)へのコメントが、要約筆記者(Yさん)からメールで入りました。
Yさん、ありがとうございました。
私も外出しておりまして、気が付きませんでしたが、
孫に聞いてみたら揺れを少し感じたと言っていました。(ROKU)
「地震」の手話:両手掌を上へ向けて並べて置き、同時に前後する
(私は外出していましたが)
今日木曽で震度3の地震があったそうですね。
夫は「けっこう揺れた」と言ってました。
地震のときには、やはり身振り・手話で伝えた方が早いですね。
やはり、地震!の身振り・手話は、大切だと思います。(Y)
(註)気象庁によると8日 午前9時30分ごろ、長野県南部でM3.4の地震が発生し、長野県木曽町で震度3の揺れを観測した。この地震の震源地は長野県南部で、震源の深さは約10キロ。
Yさん、ありがとうございました。
私も外出しておりまして、気が付きませんでしたが、
孫に聞いてみたら揺れを少し感じたと言っていました。(ROKU)
「地震」の手話:両手掌を上へ向けて並べて置き、同時に前後する
2013年09月16日
特別警報
台風18号の接近・上陸に伴い四国から東北にかけて降り続いている大雨で気象庁は本日16日、京都府、滋賀県、福井県に
大雨特別警報
を発表した。
テレビでは
” これまでに経験したことのないような大雨 ”
と言っている。
英語の表現では
・・・ we have ever experienced
であって、「これまでに経験したうちの(最大の)」となります。
・・・ we heve never experienced
という言い方は、あまり見かけない。
気象庁の「特別警報」の文言では
" 数十年に一度の "
という表現が使われている。
いずれにせよ、
「やまだかってない」
ということか。
いや、こういう時に冗談は不謹慎。
編集子は、雨の音、風の音が全く聞こえない。
「聞こえないから怖くないでしょう」
と、言われることがあるが、
とんでもない。
聞こえない方が不気味で、もっと怖い。
窓外を見ると、
雨が屋根をたたきつけ、
木々が大きく揺れて
樋から大量の水が溢れ出している。
2013.9.16 a.m. (ROKU)
大雨特別警報
を発表した。
テレビでは
” これまでに経験したことのないような大雨 ”
と言っている。
英語の表現では
・・・ we have ever experienced
であって、「これまでに経験したうちの(最大の)」となります。
・・・ we heve never experienced
という言い方は、あまり見かけない。
気象庁の「特別警報」の文言では
" 数十年に一度の "
という表現が使われている。
いずれにせよ、
「やまだかってない」
ということか。
いや、こういう時に冗談は不謹慎。
編集子は、雨の音、風の音が全く聞こえない。
「聞こえないから怖くないでしょう」
と、言われることがあるが、
とんでもない。
聞こえない方が不気味で、もっと怖い。
窓外を見ると、
雨が屋根をたたきつけ、
木々が大きく揺れて
樋から大量の水が溢れ出している。
2013.9.16 a.m. (ROKU)
2013年09月25日
県防災訓練
県防災訓練最終打ち合わせ(報告)
副会長 浜 富美子
県防災訓練
日時 11月3日(祝) 8時から13時まで。
場所 諏訪市イベント広場周辺
長野難聴として参加団体に入れてもらいます。
参加種目
1,「住民による救急救命訓練」これは見学だけになりました。
2,「福祉避難所設置訓練」
3,「災害時のパネル展示」・・例年通りの展示を行う
4,周辺で行われる他の訓練や展示を要約筆記者と共に見学・・通訳の様子
5,「終了式」出来るだけ参加
昨年の様な「けが人役」や「聴覚障害者」への伝達などが取り入れて貰えませんでした。
弱者である障害者団体が打ち合わせ段階からの参加は当協会のみ。
救助専門団体の訓練が主体で、障害弱者を知って貰えるような訓練は
避難所・福祉避難所ぐらいしか受け付けてもらえないのが残念。
避難所では「聞こえない」ことを最大にアピールし、それに対する扱いを体験したいと思います。
53種の訓練があり、参加団体も100近い団体が参加します。
地域特性の訓練では「遊覧船からの救助」「霧ヶ峰からの救助」などもあります。
駐車場の制約などありますので、参加募集の案内を後日FAXねっとで出します。
副会長 浜 富美子
県防災訓練
日時 11月3日(祝) 8時から13時まで。
場所 諏訪市イベント広場周辺
長野難聴として参加団体に入れてもらいます。
参加種目
1,「住民による救急救命訓練」これは見学だけになりました。
2,「福祉避難所設置訓練」
3,「災害時のパネル展示」・・例年通りの展示を行う
4,周辺で行われる他の訓練や展示を要約筆記者と共に見学・・通訳の様子
5,「終了式」出来るだけ参加
昨年の様な「けが人役」や「聴覚障害者」への伝達などが取り入れて貰えませんでした。
弱者である障害者団体が打ち合わせ段階からの参加は当協会のみ。
救助専門団体の訓練が主体で、障害弱者を知って貰えるような訓練は
避難所・福祉避難所ぐらいしか受け付けてもらえないのが残念。
避難所では「聞こえない」ことを最大にアピールし、それに対する扱いを体験したいと思います。
53種の訓練があり、参加団体も100近い団体が参加します。
地域特性の訓練では「遊覧船からの救助」「霧ヶ峰からの救助」などもあります。
駐車場の制約などありますので、参加募集の案内を後日FAXねっとで出します。
2013年10月07日
災害用ビブス
写真のビブスがこのたび、塩尻市の聴覚障害者に配布されました。
胸と背中に記された文字は
① 「耳が不自由です」
② 「聞こえません」
の2種類のバージョンがあり、自分の希望するほうをもらえます。
ビブスの表示文字について、いろいろいきさつがありました。その経緯を、
サイドブログ「アシタドーナル」から(少し長くなりますが)引用いたします。
2012年9月17日の記事より
このたび、福祉課より、ろう者団体・難聴者団体・手話通訳団体・要約筆記団体に対して
アンケートがありました。
原案はビブス(ゼッケン)型のものです。問題はビブスにプリントされる文字。
通訳の方々のものには要約筆記者とか手話通訳者とかが、見てわかるような文字が入ります。
私たち聴覚障害者の着用するビブスの文字としては(福祉課の案では)
「聞こえません」
というのが原案となっております。
昨年の松本のものを踏襲したものと推察します。
アンケートの回答にあたり、難聴者としては、
「聞こえません」
という文字に違和感があることを伝えました。
「耳が不自由です」
という文字にしてもらえないか、という要望を出しました。
ろう者の方々がどういう要望か、また、違った案があるかもしれません。
昨年、松本で作成した際に、難聴者からの要望を入れてつくったのかどうか、
そのへんの事情はよくわかりません。
とにかく、難聴者としては、上記のような要望を出しておきました。
2012年9月18日の記事より
災害時のビブスについて、通訳の方からのコメント(メール)
災害時のビブスのこと、通訳者の会にもアンケートが来ています。
「聞えません」には、私も違和感を感じていました。
なんか挑戦的というか、拒否してるみたいな感じで。
まあ、それでも、通訳者のビブスも含めて、
作る前に意見を求められるようになったのは、いいことですよね。
派遣通訳者の会でも、意見を集約して提出する予定です。
ではまた。
匿名は ミニトマトで。
さらに、同日、富山県の西さんからのコメント。
文句ばっかり言っている私ですが、
「聞こえません」に、
ここでもやはり難聴者が置き去りにされかねないと懸念致します。
聞こえませんに対する答えは手話通訳という事になりかねず、
文字情報の必要性(重要性)が忘れられてしまう。
今まで何度か震災ボランティアに参加してきました。
緊急避難場所が設定された瞬間、
聴者にとっても有意義な文字情報を掲示場所(掲示板)が設置すべきですが、
この最も簡単な伝達方法がもっとも対応が遅くなるのを今まで何度も経験してきています。
「聞こえません」ではなく「耳が不自由です」と耳マークの複合表記にすれば
聴覚ボランティアや社会福祉協議会関係者にも一目瞭然だと思うのです。
その上で、手話ですか?文字ですか?と当事者に聞く事が出来れば最高の対応なのかなと
何度か参加した震災ボランティアで感じました。
Posted by 西 at 2012年09月18日
「耳が不自由」という用語は、
1.義務教育でも教えられており、世間一般に知られている。
2.身体障害者手帳を持っていない、耳の不自由な高齢者にもあてはまり、汎用性がある。
3.なにより、それを身に着ける本人が、抵抗感なく身に着けられる。
以上の観点から、要望しました。
ミニトマトさんのコメントにもあるとおり、今回、
作成する前に、当事者の意見をきくという行政の姿勢には感謝しています。(ROKU)
・・・・以上のような経緯があり、今回、ビブスの文字表示に反映されたものです。
このたびの塩尻市福祉課の見識を高く評価し、感謝しております。(ROKU)
2013年10月20日
県防災訓練
11月3日(日) 県主催総合防災訓練
集合 9時
諏訪市イベント広場「バルーンシェルター」
(旧東洋バルブ工場。諏訪市文化センター隣)
難聴者参加訓練種目:避難所受付から福祉避難所設置訓練
☆ 9時に集合して受付後、担当者の指示に従い「福祉避難所」に移動。
福祉避難所設置訓練及び防災展示見学。
その他の訓練の見学(要約筆記者同行)・・協会のPRを兼ねる
☆ 耳が不自由なこと(聞こえにくいこと)が外から分かるようなものを身につけるのが望ましい。
13時修了式参列。解散となります。 (副会長 浜)
集合 9時
諏訪市イベント広場「バルーンシェルター」
(旧東洋バルブ工場。諏訪市文化センター隣)
難聴者参加訓練種目:避難所受付から福祉避難所設置訓練
☆ 9時に集合して受付後、担当者の指示に従い「福祉避難所」に移動。
福祉避難所設置訓練及び防災展示見学。
その他の訓練の見学(要約筆記者同行)・・協会のPRを兼ねる
☆ 耳が不自由なこと(聞こえにくいこと)が外から分かるようなものを身につけるのが望ましい。
13時修了式参列。解散となります。 (副会長 浜)
2013年11月03日
県総合防災訓練
県総合防災訓練(2013/11/3 於 諏訪市)
とりあえず速報をお伝えします。

県知事と諏訪市長が上空から視察。

丁寧な誘導に従って移動。「耳が不自由です」のビブスが有効に機能した。

要約筆記者に書いてもらって、初めて、サイレンが鳴っていると知った。

福祉避難所で、説明会。要望を述べる機会もありました。
長野県総合防災訓練に行ってきました。
長野難聴協会員ならびに長要連要約筆記者が多数参加しました。
とりあえず速報でした。
後程、さらに詳しくお伝えします。
とりあえず速報をお伝えします。
県知事と諏訪市長が上空から視察。
丁寧な誘導に従って移動。「耳が不自由です」のビブスが有効に機能した。
要約筆記者に書いてもらって、初めて、サイレンが鳴っていると知った。
福祉避難所で、説明会。要望を述べる機会もありました。
長野県総合防災訓練に行ってきました。
長野難聴協会員ならびに長要連要約筆記者が多数参加しました。
とりあえず速報でした。
後程、さらに詳しくお伝えします。
2013年11月04日
県総合防災訓練(2)
写真を追加します。

長野県中の「おらほ」の消防車が結集

「戦車?」も

死者?
リアルすぎて・・・遠くから撮りました。
なお、legacy-twさんの「信州の隠れ家より」(会員ブログ)に、
別の角度から、当ブログを補強する写真・記事がありますのでごらんください。
→http://alps8.blog.fc2.com/
長野県中の「おらほ」の消防車が結集
「戦車?」も
死者?
リアルすぎて・・・遠くから撮りました。
なお、legacy-twさんの「信州の隠れ家より」(会員ブログ)に、
別の角度から、当ブログを補強する写真・記事がありますのでごらんください。
→http://alps8.blog.fc2.com/
2013年11月05日
県総合防災訓練(参加報告)
平成25年度長野県総合防災訓練(参加報告)
副会長 浜 富美子
11月3日諏訪市で県総合防災訓練が旧東バルブ諏訪工場跡地を主会場に行われました。
県や市、陸上自衛隊、警察、消防、自主防災組織など108の機関、団体から3000人が参加して行われました。当協会からは8名が参加。
地震などで工場災害や遊覧船の衝突事故等を想定し、50項目の訓練が行われました。
私たちは一般の避難所に収容され、そこで「要援護者」「耳が不自由です」などのビブスをつけて福祉避難所まで誘導して貰いました。
福祉避難所とはどういう所か?どのようにするかなどを東日本大震災の映像などを使っての説明や質疑応答、車いすの扱い方など、今までの福祉避難所設営ではなく、実務説明がありより福祉避難所を理解するのに有意義な内容でした。
また、長要連と共に協会のPR展示やグッズの展示も行いました。
今回の会場がコンパクトにまとまっていたので
「地震体験車」
「煙体験」
「後方支援の災害車(ベット、台所、シャワー、休憩室などを備えた車)」
も試乗することが出来ました。
福祉避難所には地元の二つの区から60名ぐらいの参加があり、車いすでの移動など、より実質的な避難所体験が出来たのは良かった。
最後に例年通り知事の巡回があり難聴者の立場や文字情報の必要性をアピールすることが出来ました。
来年は大町市での開催予定とのこと。
引き続きアピールの機会とでなることを願います。
副会長 浜 富美子
11月3日諏訪市で県総合防災訓練が旧東バルブ諏訪工場跡地を主会場に行われました。
県や市、陸上自衛隊、警察、消防、自主防災組織など108の機関、団体から3000人が参加して行われました。当協会からは8名が参加。
地震などで工場災害や遊覧船の衝突事故等を想定し、50項目の訓練が行われました。
私たちは一般の避難所に収容され、そこで「要援護者」「耳が不自由です」などのビブスをつけて福祉避難所まで誘導して貰いました。
福祉避難所とはどういう所か?どのようにするかなどを東日本大震災の映像などを使っての説明や質疑応答、車いすの扱い方など、今までの福祉避難所設営ではなく、実務説明がありより福祉避難所を理解するのに有意義な内容でした。
また、長要連と共に協会のPR展示やグッズの展示も行いました。
今回の会場がコンパクトにまとまっていたので
「地震体験車」
「煙体験」
「後方支援の災害車(ベット、台所、シャワー、休憩室などを備えた車)」
も試乗することが出来ました。
福祉避難所には地元の二つの区から60名ぐらいの参加があり、車いすでの移動など、より実質的な避難所体験が出来たのは良かった。
最後に例年通り知事の巡回があり難聴者の立場や文字情報の必要性をアピールすることが出来ました。
来年は大町市での開催予定とのこと。
引き続きアピールの機会とでなることを願います。
2013年11月06日
今後も共に頑張りましょう(コメント)
副会長メッセージ(11/5)へのコメント
副会長さん、地元での開催、本当にお疲れ様でした。
お陰様で、いろいろな情報を得ることができました。
来年の大町も貴協会ともども長要連も参加いたします(予定)。
今後とも、よろしくお願いします。
県知事が
「次回から健康福祉部にも関わってもらうよう…」
と、あの場で指示されていました。
副会長のおかげです\(^o^)/
Posted by ろぜっと山口at 2013年11月05
2013年12月03日
災害に備えよう
今日も千葉・茨城で震度4の地震がありました。(午後3時58分頃)
車はどうする???
運転者の避難4大原則
1.道路の左側に寄せて停車。
2.エンジンは切り、キーはつけたままにする。
3.窓を閉め、ドアロックはしない。
4.貴重品を置き去りにしない。
※ あわてずに、落ち着いて!
※ 警察等の指示がある場合は、指示に従う。
※ むやみに停車することで、渋滞や金融車輛の通行に支障をきたす場合があるので、気を付けましょう。
(災害マニュアルより)
2013年12月29日
2013年12月30日
2013年12月31日
2014年01月12日
県総合防災訓練の実施結果
昨年11月3日諏訪市を主会場に実施された「県総合防災訓練」の実施結果が、
県危機管理部長名で郵送されてきました。(12月26日付け)
両面コピーで12枚ほどになりますので、抜き書きでお伝えします。
副会長 浜 富美子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成25年度長野県総合防災訓練の実施結果
☆実施結果を踏まえ、今後の会議の運営等について関係市町村との調整を行い、以下の点について改善を図っていきたい。
1)会議の運営
・参加団体の負担を考慮し、全体会議を効果的に開催できるように検討します。
・開催回数について、必要数実施する方向で検討します。
・訓練項目について、訓練場所も含め全体会議で早めに示せるようにします。
・会議資料は、重複しないよう選定して提供します。
2)当日の運営
・アナウンスは、展示会場への誘導、現在実施している訓練の案内等、わかりやすいように工夫します。
・一般参加者が、災害体験、展示スペースに参加出来るよう工夫します。
3)その他
・パンフレットを早めに配布し、一般市民への参加を周知します。
・その他の改善等についても、開催市等と検討し実施可能な限り対応します。
☆訓練別の実施結果
・映像伝達・・・・情報伝達訓練はTVによる生放送を行いモニターリングを実施、多くの視聴者にご覧いただいた。
・集団避難・・・・参加区民が落ち着いて整然と二次避難所まで避難できた。集団の先頭の歩き方が早く最後尾との間隔が幌勝手しまった。
・福祉避難所・・・一般避難所に集合し、障害表示ビブスをつけて福祉避難所に誘導。一般避難所、福祉避難所に文字表示や誰もが見て分かる表示が全くなかった。人の後について行くだけだった。人が集まってく所には、目で見て分かる表示を手書きで良いので作るべき。事前に打ち合わせた内容が諏訪市に十分通じず、説明・展示のみとなってしまった。社協では、各市町村社協と協働でして、災害ボラセンの立ち上げ、支え合えマップなどの活用した訓練を実施しているので総合訓練でもこのノウハウを活用したい。
・展示・・・・・スペースが狭かった。訓練所と離れすぎて入場者が少なかった。当日の紹介アナウンスの実施、見学者の導線に合わせた展示などが課題。多くの住民に非常食や防災用品の啓発活動を実施するために、会場をサブからメイン会場への変更と非常食の販売もお願いしたい。(以上)
県危機管理部長名で郵送されてきました。(12月26日付け)
両面コピーで12枚ほどになりますので、抜き書きでお伝えします。
副会長 浜 富美子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成25年度長野県総合防災訓練の実施結果
☆実施結果を踏まえ、今後の会議の運営等について関係市町村との調整を行い、以下の点について改善を図っていきたい。
1)会議の運営
・参加団体の負担を考慮し、全体会議を効果的に開催できるように検討します。
・開催回数について、必要数実施する方向で検討します。
・訓練項目について、訓練場所も含め全体会議で早めに示せるようにします。
・会議資料は、重複しないよう選定して提供します。
2)当日の運営
・アナウンスは、展示会場への誘導、現在実施している訓練の案内等、わかりやすいように工夫します。
・一般参加者が、災害体験、展示スペースに参加出来るよう工夫します。
3)その他
・パンフレットを早めに配布し、一般市民への参加を周知します。
・その他の改善等についても、開催市等と検討し実施可能な限り対応します。
☆訓練別の実施結果
・映像伝達・・・・情報伝達訓練はTVによる生放送を行いモニターリングを実施、多くの視聴者にご覧いただいた。
・集団避難・・・・参加区民が落ち着いて整然と二次避難所まで避難できた。集団の先頭の歩き方が早く最後尾との間隔が幌勝手しまった。
・福祉避難所・・・一般避難所に集合し、障害表示ビブスをつけて福祉避難所に誘導。一般避難所、福祉避難所に文字表示や誰もが見て分かる表示が全くなかった。人の後について行くだけだった。人が集まってく所には、目で見て分かる表示を手書きで良いので作るべき。事前に打ち合わせた内容が諏訪市に十分通じず、説明・展示のみとなってしまった。社協では、各市町村社協と協働でして、災害ボラセンの立ち上げ、支え合えマップなどの活用した訓練を実施しているので総合訓練でもこのノウハウを活用したい。
・展示・・・・・スペースが狭かった。訓練所と離れすぎて入場者が少なかった。当日の紹介アナウンスの実施、見学者の導線に合わせた展示などが課題。多くの住民に非常食や防災用品の啓発活動を実施するために、会場をサブからメイン会場への変更と非常食の販売もお願いしたい。(以上)