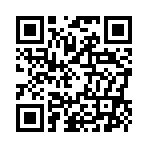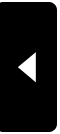2015年02月08日
会報の印刷作業
≪活動報告≫
長野難聴会報「アルプス」の印刷・発送準備作業


2月7日(土)、上田市ふれいあい福祉センターにて、
3か月に1回の”定例行事”・・・会報の印刷作業を行いました。
いつもの場所で、いつもの手順で、いつものメンバー(4名)で・・・
淡々と(黙々と)作業をこなしました。
ただ1つだけ違っていたのは、
輪転機の紙送りがご機嫌悪く、両面印刷時に紙がくっついて排出されたりして手間取ったことでした。
いつもとは違うお店でコピー用紙を調達したために、
紙質が違っていたためだろうと思います。
(LEGACY)
<会員ブログ「信州の隠れ家より」から>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長野難聴会報「アルプス」の印刷・発送準備作業


2月7日(土)、上田市ふれいあい福祉センターにて、
3か月に1回の”定例行事”・・・会報の印刷作業を行いました。
いつもの場所で、いつもの手順で、いつものメンバー(4名)で・・・
淡々と(黙々と)作業をこなしました。
ただ1つだけ違っていたのは、
輪転機の紙送りがご機嫌悪く、両面印刷時に紙がくっついて排出されたりして手間取ったことでした。
いつもとは違うお店でコピー用紙を調達したために、
紙質が違っていたためだろうと思います。
(LEGACY)
<会員ブログ「信州の隠れ家より」から>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月08日
アルミシート(防災グッズ)
≪つぶやき万華鏡≫
保温用アルミシート (防災グッズ)
昨年末の仙山線(せんざんせん)の車輛事故で、
・・・・・・・・・・・・・・・・


100円ショップで、防災グッズを買ってきました。
保温用アルミシートです。
このアルミシート、
広げると、畳一畳分ぐらいの大きさで、
普段は布団の下に敷いて使っている。
災害時は避難所へも持っていけるし、防災グッズとして、
多目的に。
に使える。
「身体をくるむ」
で、思い出したのが女子マラソンのQちゃん
大阪学院大学を卒業後、リクルートに入社。
陸上部では、歓迎会で新人は何か芸をやるという慣例があった。、
新人の高橋さんは、全身にアルミホイルを巻きつけて登場、
♪ おばけのQQQ ぼ~くは おばけのQ太郎ぉ~
と歌い、
踊った。
Qちゃんのあだ名がついた。
その後の活躍はご存じのとおり。。
なるほど、アルミは多目的に使える。
(ROKU)
<会員ブログ「アシタドーナル」2914/12/30記事から>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保温用アルミシート (防災グッズ)
昨年末の仙山線(せんざんせん)の車輛事故で、
停電した電車に閉じ込められていた乗客に、アルミシートが配布され、乗客はこれで全身をくるむことにより、かなり寒さをしのぐことができた、というニュースはいまだ記憶に新しい。
・・・・・・・・・・・・・・・・
100円ショップで、防災グッズを買ってきました。
保温用アルミシートです。
このアルミシート、
広げると、畳一畳分ぐらいの大きさで、
普段は布団の下に敷いて使っている。
災害時は避難所へも持っていけるし、防災グッズとして、
多目的に。
に使える。
「身体をくるむ」
で、思い出したのが女子マラソンのQちゃん
大阪学院大学を卒業後、リクルートに入社。
陸上部では、歓迎会で新人は何か芸をやるという慣例があった。、
新人の高橋さんは、全身にアルミホイルを巻きつけて登場、
♪ おばけのQQQ ぼ~くは おばけのQ太郎ぉ~
と歌い、
踊った。
Qちゃんのあだ名がついた。
その後の活躍はご存じのとおり。。
なるほど、アルミは多目的に使える。
(ROKU)
<会員ブログ「アシタドーナル」2914/12/30記事から>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月07日
「土砂災害警戒区域」に我が家が
2015.2.7 SAT.
≪つぶやき万華鏡≫
「土砂災害警戒区域」に、我が家が・・・(>_<)
職場近くの国道端に、「土砂災害警戒区域」のパネル表示板が設置されました。
衛星写真に、土砂災害(河川、急斜面の崩落)の危険地域を
赤や黄色で示しています。
同時に地域の避難所も明示されています。
それはともかく、衛星写真を眺めているだけで地域の様子が
手に取るようにわかるのもGood!です。
もちろん、我が家もはっきりと映っています(*^_^*)
家の屋根も庭も畑も道路もよくわかります。
・・・しかし、すぐ近くを流れている沢には真っ赤な線が・・\(◎o◎)/!
「土砂災害警戒区域」に指定されているようです(>_<)
(LEGACY)
<会員ブログ「信州の隠れ家より」2.6記事から引用>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

何? これ ! 2/1 定例会の会場近くにありました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
「土砂災害警戒区域」に、我が家が・・・(>_<)
職場近くの国道端に、「土砂災害警戒区域」のパネル表示板が設置されました。
衛星写真に、土砂災害(河川、急斜面の崩落)の危険地域を
赤や黄色で示しています。
同時に地域の避難所も明示されています。
それはともかく、衛星写真を眺めているだけで地域の様子が
手に取るようにわかるのもGood!です。
もちろん、我が家もはっきりと映っています(*^_^*)
家の屋根も庭も畑も道路もよくわかります。
・・・しかし、すぐ近くを流れている沢には真っ赤な線が・・\(◎o◎)/!
「土砂災害警戒区域」に指定されているようです(>_<)
(LEGACY)
<会員ブログ「信州の隠れ家より」2.6記事から引用>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
何? これ ! 2/1 定例会の会場近くにありました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月06日
難聴者「2000万人」
≪つぶやき万華鏡≫
「難聴者2000万人」という、数字。
読売新聞(YOMIURI ONLINE)に、昨年12月に東京で行われたセミナー
字幕付きCM(民放連など主催)
の情報がありました。
http://www.yomiuri.co.jp/culture/tv/tnews/20150107-OYT8T50144.html
字幕付きCMについては、
「家族が集まっても自分だけ分からない。私たちも消費者の一人なのに(CMに字幕をつけないのは)失礼だと思いませんか」の言葉にあるとおりです。
=松森果林・ユニバーサルデザインアドバイザー(Eテレ・ワンポイント手話の方)
ところで、上記の記事で、
総務省などの報告によると、障害や高齢のため耳が聞こえにくい人は約2000万人、とありました。
私の今までの知識では、
身体障害者手帳登録者(70dB以上損失者)約36万人。というものでしたが・・・。
そのうち手話を第一言語とする者は約6万人。
WHOの基準(40dB基準)では、約600万人、
補聴器店の統計などによると、約1000万人。
この数値、
総務省などの報告によるととありますが、
2000万人という数値は、初めて目にしました。
いずれにせよ、
デシベルダウン運動
が急務です。
(ROKU)
<会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」1/21記事より引用>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しなの鉄道 クモハ115 於 長野駅
3月14日より「しなの鉄道北しなの線」に。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月05日
手話の読み取り
JR篠ノ井線の車窓から・姨捨駅 (2/1定例会の帰途)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
手話の読み取り
かつて一生懸命に習った手話ですが・・・
だんだんと使う機会が減ってきて、我流の手話になりつつあります。
これは良くないこと、というのは頭ではよくわかっております。ハイ。
それにも増して、力が落ちてきたなと思うのは読み取り能力です。
自分で”手話の表現”をしている時には”自分の手話はまともなはずだ”とという自惚れがあります。
しかし、相手の手話を読み取る際には、自分の読み取り力が本当に試されます。
読めなかった手話でも、ちょっとした会話なら誤魔化すことも可能ですが、所詮会話は続きません。
顔なじみの人からでも、突然手話で語りかけられては、会話の予備知識が頭に準備できていないので、とっさには読めないことが多いものです。
また、テレビの手話ニュースや講演会などの手話同時通訳を、日常的に手話を使うろう者はきちんと読み取れているのでしょうか?
それらは、仲間同士の会話と違って、情報の事前共有がありませんし、”聞き返し”もできません。
実は案外読み取れていないのではないかと勘ぐっています。
”なんとなくわかった”というのが平均的な理解度でしょう。
(Legacy)
会員ブログ「信州の隠れ家より」から引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月04日
耳の日フェスティバル

【主催】松本市聴覚障害者社会参加支援協会
※ このフェスティバルには長野難聴の仲間も直接に関わっています。
ふるってご参加ください。
2015.2.4 WED.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Posted by 六万石 at
07:50
│Comments(0)
2015年02月03日
情報保障のタイムラグ
JR長野駅 2015.2.1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき万華鏡≫
情報保障のタイムラグ
2月定例会のデフネット長野の啓発事業:山田千津子先生の講演は
その内容が大変良かったと思います。
これから書く文章は、その内容に関する話ではなく、
情報保障の角度から検証してみようというもので、
企画にケチをつけるとか、そういう意図は毛頭ありません。(念のため)
ろう者と難聴者が同時に参加するわけだから、
情報保障は手話通訳と要約筆記通訳の両方がつく。
講演者は、講演慣れをしていらっしゃって、
話の盛り上げ方も心得たものだった。
こういう場合には、手話通訳はリアルタイムに話に追いついていくが、
要約筆記は、物理的に、ワンテンポ遅れるものである。
そのことは十分承知している。
この日の要約筆記は、手書きだったが、なかなかの技術で、
一生懸命に話に追いついてくださっていた。
しかし、どうしても困ってしまうのが、
講演者が会場の参加者に挙手させる場面。
たとえば、
① 離れている人
② くっついている人
などと、挙手する場面では、ろう者は
①の人・・・ 「ハイ」、
②の人・・・ 「ハイ」
と、間髪を入れず手をあげる。
難聴者はと言うと、手をあげるタイミングがつかめず、
もそもそとしている。
私は、今までに何度もこういう場面を経験している。
手はあげず、様子を見ているだけである。
そうせざるを得ない。
こういうとき私(=難聴者)は、
どう反応してよいのかわからず
まるで借りてきた猫のようになってしまう。
これを解決するには、
難聴者の存在を(講演者に)意識してもらう以外にない、
事前に(講演者に)お願いして配慮してもらう以外にないと思っています。
(ROKU)
<会員ブログ「アシタドーナル」2/2 記事より>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月02日
2月定例会(速報)
長野市障害者福祉センター (長野難聴2月定例会会場)
長野難聴2月定例会が2月1日(日)、長野市障害者福祉センターで行われ、
成功裏に終わりました。
午前の部「デフネットながの」主催の啓発事業:山田千津子先生(筆跡心理士)の
「筆跡心理:なりたい自分になるための文字の書き方」は、とりわけ大好評でした。
午後は来年度の定例会開催地について話し合い、来年度への展望が開けました。
会員ブログ「信州の隠れ家より」(2/2)に関連記事があります。
→ http://alps8.blog.fc2.com/blog-entry-712.html
※ 近日中にホームページで写真速報を掲載予定です。お楽しみに。<広報部>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
JR長野駅東口界隈
ABN 長野朝日放送
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・