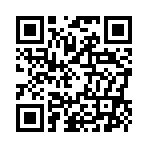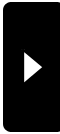2010年07月07日
長野難聴「聞こえの相談会」関先生の資料から
難聴者へのコミュニケーションの配慮(1)
1.難聴者への注意をひいてから話を始める。
2.顔を見ながら話す。
3.ゆっくり話す。
4.補聴器を使っている人には「普通の声でゆっくりと」話す。
補聴器を使っていない人には「やや大きめの声でゆっくりと」話す。
5.近づいて話す。
1.に関して
呼びかけをする。(難聴者のほうへ)身を乗り出す。顔を近づける。近づいて身体にふれる。
その場の状況・難聴者との関係を考慮した注意のひき方をする。
2.に関して
耳に口を近づけて話す方法は、望ましくない。
難聴者に向かって話さないと声が補聴器に入りづらい。
3.に関して
高齢難聴者が最も分かりにくい話し方は「早口」である。
言葉のまとまりで、自然に、分かりやすく。
また、一音ずつ話すのはききとりにくい。
(良い例) 今晩の ごはんは なににしましょうか
(悪い例) こ・ん・ば・ン・の・ご・は・ん・は・・・・・
4.に関して
大きすぎる声は、音声が割れてしまいかえって聞き取りにくい。
大きすぎる声は、怒鳴りつけられているようで難聴者はつらい。
5.に関して
補聴器のマイクは、3m以上離れると言葉が入りにくくなる。
to be continued
1.難聴者への注意をひいてから話を始める。
2.顔を見ながら話す。
3.ゆっくり話す。
4.補聴器を使っている人には「普通の声でゆっくりと」話す。
補聴器を使っていない人には「やや大きめの声でゆっくりと」話す。
5.近づいて話す。
1.に関して
呼びかけをする。(難聴者のほうへ)身を乗り出す。顔を近づける。近づいて身体にふれる。
その場の状況・難聴者との関係を考慮した注意のひき方をする。
2.に関して
耳に口を近づけて話す方法は、望ましくない。
難聴者に向かって話さないと声が補聴器に入りづらい。
3.に関して
高齢難聴者が最も分かりにくい話し方は「早口」である。
言葉のまとまりで、自然に、分かりやすく。
また、一音ずつ話すのはききとりにくい。
(良い例) 今晩の ごはんは なににしましょうか
(悪い例) こ・ん・ば・ン・の・ご・は・ん・は・・・・・
4.に関して
大きすぎる声は、音声が割れてしまいかえって聞き取りにくい。
大きすぎる声は、怒鳴りつけられているようで難聴者はつらい。
5.に関して
補聴器のマイクは、3m以上離れると言葉が入りにくくなる。
to be continued
2010年07月13日
長野難聴「聞こえの相談会」関先生の資料から
難聴者へのコミュニケーションの配慮(2)
難聴者と会話をするときは
1.周囲の騒音をできるだけ避ける
2.分からないときにはいつでも聞きなおせる雰囲気をつくる。
3.理解の確認をする。
1.に関して
・テレビやラジオを消す、窓を閉める、難聴者の座る位置(壁際がよい)、など。
・補聴器は言葉だけでなく周囲の雑音も大きくします。雑音が入ると言葉の聞き取りが低下します。
2.に関して
・難聴者は聞き返しをしていやな顔をされたりした経験から聞き返すことに気後れする場合があります。
・難聴者は「相手に迷惑をかけたくない」との思いから聞き返しを遠慮する場合があります。
3.に関して
・難聴者は聞きとれないのに「わかったふりをする」場合があります。
・重要な点は髪に書いて手渡したりして確認をすることが大切です。
難聴者と会話をするときは
1.周囲の騒音をできるだけ避ける
2.分からないときにはいつでも聞きなおせる雰囲気をつくる。
3.理解の確認をする。
1.に関して
・テレビやラジオを消す、窓を閉める、難聴者の座る位置(壁際がよい)、など。
・補聴器は言葉だけでなく周囲の雑音も大きくします。雑音が入ると言葉の聞き取りが低下します。
2.に関して
・難聴者は聞き返しをしていやな顔をされたりした経験から聞き返すことに気後れする場合があります。
・難聴者は「相手に迷惑をかけたくない」との思いから聞き返しを遠慮する場合があります。
3.に関して
・難聴者は聞きとれないのに「わかったふりをする」場合があります。
・重要な点は髪に書いて手渡したりして確認をすることが大切です。
2010年07月15日
長野難聴「聞こえの相談会」関先生の資料から
難聴者へのコミュニケーションの配慮(3)
話し方の一般的配慮
1.話題を共有する
2.短い文で会話する(長い文は避ける)
3.一語での会話は避ける
1.に関して
・何の話をしているのか難聴者にわかるように。
・話題が変わったら、何の話に替わったのかを難聴者に伝えましょう。
・複数者の場合、話題がどんどん変わって行くと会話への参加が困難になります。
2.に関して
・高齢難聴者は一度にたくさん話すとはじめのほうを忘れてしまいます。
・一度に一つのことを話しましょう。
3.に関して
・難聴者は、話の流れや前後の言葉から聞き取りにくい言葉を推測しています。
一語だけだと推測の手がかりがなくて分かりにくくなります。
(悪い例) 「イチゴは?」
(よい例) 「昨日 もらった イチゴは?」
話し方の一般的配慮
1.話題を共有する
2.短い文で会話する(長い文は避ける)
3.一語での会話は避ける
1.に関して
・何の話をしているのか難聴者にわかるように。
・話題が変わったら、何の話に替わったのかを難聴者に伝えましょう。
・複数者の場合、話題がどんどん変わって行くと会話への参加が困難になります。
2.に関して
・高齢難聴者は一度にたくさん話すとはじめのほうを忘れてしまいます。
・一度に一つのことを話しましょう。
3.に関して
・難聴者は、話の流れや前後の言葉から聞き取りにくい言葉を推測しています。
一語だけだと推測の手がかりがなくて分かりにくくなります。
(悪い例) 「イチゴは?」
(よい例) 「昨日 もらった イチゴは?」
2010年07月18日
長野難聴「聞こえの相談会」関先生の資料から(最終回)
難聴者がコミュニケーションにつまづいたときの配慮
1.言い方を替える
2.手がかりになる言葉を入れる
3.サインや身振りを活用する
4.通じにくい単語を書く
1.に関して
難聴者は何回聞いても聞きとれないときがある。
同じ言葉を繰り返しても聞きとれないときには、言い方を替える。
(例) 「一日中」→「朝から晩まで」
「行って来る」→「でかけてくる」 など。
2.に関して
・ 人の名前のとき
(例) 「岸川さん」→「目黒の岸川さん」
・ 食べ物などのとき
(例) 「梨」→「冷蔵庫にしまってある梨」
3.に関して
・ 数字は指で示す。
・ 実物を示す。(指差す)
・ 動作や形の模倣(身振りで)
4.に関して
・ 単語だけを書いて示す。
・ 筆記用具がないときは、指でテーブルや掌に書くのも有効。
concluded
1.言い方を替える
2.手がかりになる言葉を入れる
3.サインや身振りを活用する
4.通じにくい単語を書く
1.に関して
難聴者は何回聞いても聞きとれないときがある。
同じ言葉を繰り返しても聞きとれないときには、言い方を替える。
(例) 「一日中」→「朝から晩まで」
「行って来る」→「でかけてくる」 など。
2.に関して
・ 人の名前のとき
(例) 「岸川さん」→「目黒の岸川さん」
・ 食べ物などのとき
(例) 「梨」→「冷蔵庫にしまってある梨」
3.に関して
・ 数字は指で示す。
・ 実物を示す。(指差す)
・ 動作や形の模倣(身振りで)
4.に関して
・ 単語だけを書いて示す。
・ 筆記用具がないときは、指でテーブルや掌に書くのも有効。
concluded
2010年07月29日
学習シリーズ:障害者権利条約(1)
障害者権利条約 (メモ1)
参考資料:日本障害フォーラム編「障害者権利条約」など
この条約は2006年に国際連合の総会で決議された国際条約。
この条約は、障害者のために新しい権利を作り出すものではなく、人としてあたりまえの権利と自由を障害のある人にもない人にも同じように認め、障害者が社会の一員として尊厳をもって生活することを目的としたもの。
世界保健機構(WHO)の推計では、世界の10%の人々がなんらかの障害をもつと言われている。
世界の多くの障害者は、あたりまえの権利が認められない、厳しい状況にあることから、特にこの条約が、各国の話し合いによって作られたもの。
国際条約だから、批准されると普通の法律よりも上に(憲法と普通の法律の中間に)位置することになる。
したがって、この条約は、「ああ、よいことでございます」と、ただ形式的に批准すればそれで済むというものではなく、(下位に来る)法律を変えて、この条約と整合性のあるものにしておかないと、あまり意味がない。
わが国ではまだ批准されていない。
参考資料:JDF発行「障害者権利条約」(”みんなちがって みんな一緒!)
参考資料:日本障害フォーラム編「障害者権利条約」など
この条約は2006年に国際連合の総会で決議された国際条約。
この条約は、障害者のために新しい権利を作り出すものではなく、人としてあたりまえの権利と自由を障害のある人にもない人にも同じように認め、障害者が社会の一員として尊厳をもって生活することを目的としたもの。
世界保健機構(WHO)の推計では、世界の10%の人々がなんらかの障害をもつと言われている。
世界の多くの障害者は、あたりまえの権利が認められない、厳しい状況にあることから、特にこの条約が、各国の話し合いによって作られたもの。
国際条約だから、批准されると普通の法律よりも上に(憲法と普通の法律の中間に)位置することになる。
したがって、この条約は、「ああ、よいことでございます」と、ただ形式的に批准すればそれで済むというものではなく、(下位に来る)法律を変えて、この条約と整合性のあるものにしておかないと、あまり意味がない。
わが国ではまだ批准されていない。
参考資料:JDF発行「障害者権利条約」(”みんなちがって みんな一緒!)
2010年07月31日
障害者権利条約(2)
学習シリーズ:障害者権利条約 (メモ2)
障害者権利条約は、全部で50条からなっている。
第1条~第9条 条約の骨格となる一般的規定について
第10条~第30条 個別の権利などについて
第31条~第40条 条約を実施することについて
第41条~第50条 条約を結ぶ手続きについて
この条約では、障害者を憐れみの対象としてみるのではなく、障害者が自分の人生について決める力があり、社会の一員として生活する主人公ととらえている。
(以上JDF資料より引用)
たしかに、私達障害者が一番いやな言葉は「お気の毒に」という言葉。
その言葉のこそ、自分は安全地帯にいて、障害者を下に見下している言葉にほかならない。
人間は死ぬ時には、みんな障害者になるのにね。(Roku)
障害者権利条約は、全部で50条からなっている。
第1条~第9条 条約の骨格となる一般的規定について
第10条~第30条 個別の権利などについて
第31条~第40条 条約を実施することについて
第41条~第50条 条約を結ぶ手続きについて
この条約では、障害者を憐れみの対象としてみるのではなく、障害者が自分の人生について決める力があり、社会の一員として生活する主人公ととらえている。
(以上JDF資料より引用)
たしかに、私達障害者が一番いやな言葉は「お気の毒に」という言葉。
その言葉のこそ、自分は安全地帯にいて、障害者を下に見下している言葉にほかならない。
人間は死ぬ時には、みんな障害者になるのにね。(Roku)
2010年08月02日
障害者権利条約(3)
学習シリーズ:障害者権利条約(3)
「障害」とは何か。「障害者」とは何か。
これまで「障害」とは、目が見えない、歩けないなど、
その人が持っている性質から生ずると多くの場合考えられてきた。
障害者権利条約では、それだけではなく、
そうした個人の性質のために、働けなかったり、
様々な活動に参加できなかったりするような
社会の仕組み(人々の偏見、建物の制度など)にも問題がある。
そのような社会と人との関わりから「障害」が生じている、
という考え方である。 (以上 JDF資料より)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「障害」とは何か。「障害者」とは何か。
これまで「障害」とは、目が見えない、歩けないなど、
その人が持っている性質から生ずると多くの場合考えられてきた。
障害者権利条約では、それだけではなく、
そうした個人の性質のために、働けなかったり、
様々な活動に参加できなかったりするような
社会の仕組み(人々の偏見、建物の制度など)にも問題がある。
そのような社会と人との関わりから「障害」が生じている、
という考え方である。 (以上 JDF資料より)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2010年08月06日
障害者権利条約(4)
学習シリーズ:障害者権利条約 (メモ4)
差別とは何か
直接的差別:
障害があるからといって、会社に雇わない、学校に入学させないなど、
障害のある人と違った不利な扱いをすること。
間接的差別:
たとえば入社試験や学校の入学試験を行うとき、
「会話による面接ができること」
「点字ではない手書きや活字の問題用紙が読めること」
などの条件をつくり、結果として障害者が不利になることなど。
さらに、この条約では「合理的配慮を行わないこと」も差別としてとらえている。
(続く)
差別とは何か
直接的差別:
障害があるからといって、会社に雇わない、学校に入学させないなど、
障害のある人と違った不利な扱いをすること。
間接的差別:
たとえば入社試験や学校の入学試験を行うとき、
「会話による面接ができること」
「点字ではない手書きや活字の問題用紙が読めること」
などの条件をつくり、結果として障害者が不利になることなど。
さらに、この条約では「合理的配慮を行わないこと」も差別としてとらえている。
(続く)
2010年08月07日
障害者権利条約(5)
学習シリーズ:障害者権利条約(5)
「「合理的配慮」」 とは
障害者が、ほかの人と同じように働くことができるように、たとえば、
◇職場の入り口の段差をなくす。
◇仕事の資料を点字にする。
◇会議に手話通訳や要約筆記(文字による通訳)を置く。
◇仕事の手順を分かりやすくする。
◇働く時間をほかの人より短くする・・・・
政府や会社、周りの人々などが、このように障害者一人一人の必要を考えて、その状況に応じた変更や調整などを、お金や労力などの負担がかかりすぎない範囲で行うことが、合理的配慮である。
(JDF資料より)
「「合理的配慮」」 とは
障害者が、ほかの人と同じように働くことができるように、たとえば、
◇職場の入り口の段差をなくす。
◇仕事の資料を点字にする。
◇会議に手話通訳や要約筆記(文字による通訳)を置く。
◇仕事の手順を分かりやすくする。
◇働く時間をほかの人より短くする・・・・
政府や会社、周りの人々などが、このように障害者一人一人の必要を考えて、その状況に応じた変更や調整などを、お金や労力などの負担がかかりすぎない範囲で行うことが、合理的配慮である。
(JDF資料より)
2010年08月11日
障害者権利条約(6)
学習シリーズ:障害者権利条約(6)
障害者権利条約に盛られた内容について、ポイントは6つ。
1.障害とは何か
2.差別とは何か
3.「合理的配慮」とは
4.法的能力について
5.参加とインクルージョン
6.手話は言語である
上記の1~3の項目については、すでに掲載しました。
今回は 4の法的能力について解説を掲載します。
物や財産を売り買いしたり、裁判に参加したりする行為は、法律に基づいて行われる。
障害者権利条約では、すべての障害者にはそのような行為をする法律上の能力があるとしている。
仮にそれが難しい場合であっても
「代わりに、してあげる」という考えかたではなく、
障害者が自分で行動するために、人からの支援を、
「自ら選んで受ける権利がある」
としている。
障害者権利条約に盛られた内容について、ポイントは6つ。
1.障害とは何か
2.差別とは何か
3.「合理的配慮」とは
4.法的能力について
5.参加とインクルージョン
6.手話は言語である
上記の1~3の項目については、すでに掲載しました。
今回は 4の法的能力について解説を掲載します。
物や財産を売り買いしたり、裁判に参加したりする行為は、法律に基づいて行われる。
障害者権利条約では、すべての障害者にはそのような行為をする法律上の能力があるとしている。
仮にそれが難しい場合であっても
「代わりに、してあげる」という考えかたではなく、
障害者が自分で行動するために、人からの支援を、
「自ら選んで受ける権利がある」
としている。
2010年12月28日
「障害者自立支援法改正案」について
みなさんご存知の通り、「障害者自立支援法改正法案」が12月、あっと言う間に国会を通ってしまいました。
この法案は、「つなぎ法案」とはいえ、「障がい者制度改革推進会議」で行われている議論の方向を全く反映しない法案です。
NOTHING ABOUT US,WITHOUT US!
(私達のことを私達のいないところで決めないで!)
のスローガンのもと、「障害者自立支援法」そのものを廃棄するという運動を盛り上げていきましょう。
参考資料(「月刊障害制度関係ニュース」12月号より。<長野難聴事務局配信>
平成22年12月3日、参議院厚生労働委員会にて「障害者自立支援法改正法案」(衆議院厚生労働委員会委員長提案:障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案)が可決されました。その後、同日開催された参議院本会議にて採決され、賛成多数で可決し、法案は成立となりました。
法案は、6月の第174回通常国会で廃案になった内容をそのままの形(施行日一部修正)で継承したものであり、平成22年11月17日、衆議院厚生労働委員会において、委員長提案として提出され、委員会で可決し、その後、11月18日に開催された衆議院本会議にて可決されています。
主な内容は、①利用者負担の見直し、②障害者の範囲の見直し、③相談支援の充実(自立支援協議会を法律上位置づけ等)、④障害児支援の強化、⑤地域における自立した生活のための支援の充実(グループホーム・ケアホーム利用の際の助成の創設 等)等です。施行日は、①平成24年4月1日、②公布日、③平成24年4月1日までの政令で定める日から施行の3つに分かれています。
また、衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会において法案が可決される際に、①平成25年8月までの実施を目指して、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すなど検討すること、②指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成する際に、障害者等の希望等を踏まえて作成するよう努めるようにすることの2点が附帯決議として盛り込まれています。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案の概要
① 趣旨(公布の日)
- 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策の見直すまでの間における障害者等の地域生活支援のための法改正であることを明記
② 利用者負担の見直し(平成24年4月1日までの政令で定める日から施行)
- 利用者負担について、応能負担を原則に
- 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減
③ 障害者の範囲の見直し(公布の日)
- 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化
④ 相談支援の充実(平成24年4月1日 ※自立支援協議会については、平成24年4月1日までの政令で定める日から施行)
- 相談支援体制の強化(市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置づけ、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化)
- 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大
この法案は、「つなぎ法案」とはいえ、「障がい者制度改革推進会議」で行われている議論の方向を全く反映しない法案です。
NOTHING ABOUT US,WITHOUT US!
(私達のことを私達のいないところで決めないで!)
のスローガンのもと、「障害者自立支援法」そのものを廃棄するという運動を盛り上げていきましょう。
参考資料(「月刊障害制度関係ニュース」12月号より。<長野難聴事務局配信>
平成22年12月3日、参議院厚生労働委員会にて「障害者自立支援法改正法案」(衆議院厚生労働委員会委員長提案:障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案)が可決されました。その後、同日開催された参議院本会議にて採決され、賛成多数で可決し、法案は成立となりました。
法案は、6月の第174回通常国会で廃案になった内容をそのままの形(施行日一部修正)で継承したものであり、平成22年11月17日、衆議院厚生労働委員会において、委員長提案として提出され、委員会で可決し、その後、11月18日に開催された衆議院本会議にて可決されています。
主な内容は、①利用者負担の見直し、②障害者の範囲の見直し、③相談支援の充実(自立支援協議会を法律上位置づけ等)、④障害児支援の強化、⑤地域における自立した生活のための支援の充実(グループホーム・ケアホーム利用の際の助成の創設 等)等です。施行日は、①平成24年4月1日、②公布日、③平成24年4月1日までの政令で定める日から施行の3つに分かれています。
また、衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会において法案が可決される際に、①平成25年8月までの実施を目指して、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すなど検討すること、②指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成する際に、障害者等の希望等を踏まえて作成するよう努めるようにすることの2点が附帯決議として盛り込まれています。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案の概要
① 趣旨(公布の日)
- 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策の見直すまでの間における障害者等の地域生活支援のための法改正であることを明記
② 利用者負担の見直し(平成24年4月1日までの政令で定める日から施行)
- 利用者負担について、応能負担を原則に
- 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減
③ 障害者の範囲の見直し(公布の日)
- 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化
④ 相談支援の充実(平成24年4月1日 ※自立支援協議会については、平成24年4月1日までの政令で定める日から施行)
- 相談支援体制の強化(市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置づけ、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化)
- 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大
2011年06月25日
障害者虐待防止法案が可決されました
<全社協生涯福祉関連ニュース平成23年度第4号から>
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案」が成立
平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案」が参議院本会議にて可決し、成立しました。
障害者虐待防止法案は、平成21年11月25日、議員立法として第173回臨時国会に提出され、継続審議となっていました。今国会では、継続審議となっていた法案をもとに衆議院厚生労働委員長提案が提出され、平成23年6月14日、衆議院本会議で可決され、その後、参議院での審議を経て成立に至りました。
法案では、「障害者」を障害者基本法に規定する障害者、「障害者虐待」を①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待、と定義しています。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待については、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に市町村等への通報義務、通報等を受けた場合の市町村及び都道府県の措置等を定めることとしています。
また、障害者虐待の通報窓口等として「市町村障害者虐待防止センター」、「都道府県障害者権利擁護センター」が市町村及び都道府県に設置されることになります。
なお、学校や病院等における虐待の取り扱いについては今回の法律の対象とされず、3年後の法の見直しの際の検討課題として附則に盛り込まれています。
法律は、平成24年10月1日から施行されます。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701016.htm
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701016.htm
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案」が成立
平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案」が参議院本会議にて可決し、成立しました。
障害者虐待防止法案は、平成21年11月25日、議員立法として第173回臨時国会に提出され、継続審議となっていました。今国会では、継続審議となっていた法案をもとに衆議院厚生労働委員長提案が提出され、平成23年6月14日、衆議院本会議で可決され、その後、参議院での審議を経て成立に至りました。
法案では、「障害者」を障害者基本法に規定する障害者、「障害者虐待」を①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待、と定義しています。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待については、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に市町村等への通報義務、通報等を受けた場合の市町村及び都道府県の措置等を定めることとしています。
また、障害者虐待の通報窓口等として「市町村障害者虐待防止センター」、「都道府県障害者権利擁護センター」が市町村及び都道府県に設置されることになります。
なお、学校や病院等における虐待の取り扱いについては今回の法律の対象とされず、3年後の法の見直しの際の検討課題として附則に盛り込まれています。
法律は、平成24年10月1日から施行されます。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701016.htm
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701016.htm
2011年06月27日
障害福祉関係ニュースから
<障害福祉関係ニュース平成23年度4号から>
2.「障害者基本法改正法案」が衆議院本会議で可決される
平成23年6月16日、「障害者基本法改正法案」が衆議院本会議で可決されました。
法案には、東日本大震災を受けて、国及び地方公共団体の防災対策の義務付けが修正案として盛り込まれています。
また、修正案では、「教育」に関して、障害者である児童、生徒、その保護者に対して十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないことが明記されています。
[衆議院]
(提出時法案)障害者基本法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705059.htm
(修正案)障害者基本法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_7382.htm
2.「障害者基本法改正法案」が衆議院本会議で可決される
平成23年6月16日、「障害者基本法改正法案」が衆議院本会議で可決されました。
法案には、東日本大震災を受けて、国及び地方公共団体の防災対策の義務付けが修正案として盛り込まれています。
また、修正案では、「教育」に関して、障害者である児童、生徒、その保護者に対して十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないことが明記されています。
[衆議院]
(提出時法案)障害者基本法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705059.htm
(修正案)障害者基本法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_7382.htm
2011年07月19日
障がい者制度改革推進会議差別禁止部会
学習資料<障害福祉関係ニュース平成23年度4号から>
内閣府「第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」が開催される
平成23年6月10日、「第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」が開催され、
①差別禁止に関する諸外国の法制度に関するヒアリング、
②差別禁止法制の必要性等の論点に関する検討が行われました。
差別禁止に関する諸外国の法制度に関するヒアリングでは、
「障害のあるアメリカ人に関する法律」(ADA)における障害差別禁止法理について、植木 淳 氏(北九州市立大学 准教授)から報告がありました。
また、差別禁止法制の必要性等の論点に関する検討については、下記の論点について各委員からの事前意見をもとに協議が進められました。
次回は、7月8日に開催され、「直接差別」を中心に検討が進められる予定です。
<第5回差別禁止部会において論ずべき点>
① 差別禁止法制の必要性
② 差別禁止の分野における「障害」をどうとらえるか
③ 機能障害について、すべての機能障害を対象とすべきか、何らかの制限(例えば、期間、程度)を加えるべきか
④ 障害が、現在存在している場合だけに限るか、過去に障害の履歴を有する場合や将来発生する蓋然性がある場合、さらには、誤解などで障害があるとみなされた場合も含めるか
⑤ 障害に、必ずしも機能障害が伴わない外貌やその他心身の特徴を含めるべきか
⑥ 差別禁止法の適用対象
・ 障害者について、ADAは一定の分野の差別に関して、障害者について「有資格」という限定をつけているが、かような限定をつけるべきか、つけないとしたら一般的例外規定ないしは差別に該当するのかという判断などの場面で対処する方法があるか
・ 障害のない人が、身内や友人など、その関係する障害のある人の障害を理由に差別を受けた場合、差別禁止法の適用対象に含めるべきかについて
[内閣府]
第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_5/index.html
第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 動画配信
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin36.html
内閣府「第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」が開催される
平成23年6月10日、「第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」が開催され、
①差別禁止に関する諸外国の法制度に関するヒアリング、
②差別禁止法制の必要性等の論点に関する検討が行われました。
差別禁止に関する諸外国の法制度に関するヒアリングでは、
「障害のあるアメリカ人に関する法律」(ADA)における障害差別禁止法理について、植木 淳 氏(北九州市立大学 准教授)から報告がありました。
また、差別禁止法制の必要性等の論点に関する検討については、下記の論点について各委員からの事前意見をもとに協議が進められました。
次回は、7月8日に開催され、「直接差別」を中心に検討が進められる予定です。
<第5回差別禁止部会において論ずべき点>
① 差別禁止法制の必要性
② 差別禁止の分野における「障害」をどうとらえるか
③ 機能障害について、すべての機能障害を対象とすべきか、何らかの制限(例えば、期間、程度)を加えるべきか
④ 障害が、現在存在している場合だけに限るか、過去に障害の履歴を有する場合や将来発生する蓋然性がある場合、さらには、誤解などで障害があるとみなされた場合も含めるか
⑤ 障害に、必ずしも機能障害が伴わない外貌やその他心身の特徴を含めるべきか
⑥ 差別禁止法の適用対象
・ 障害者について、ADAは一定の分野の差別に関して、障害者について「有資格」という限定をつけているが、かような限定をつけるべきか、つけないとしたら一般的例外規定ないしは差別に該当するのかという判断などの場面で対処する方法があるか
・ 障害のない人が、身内や友人など、その関係する障害のある人の障害を理由に差別を受けた場合、差別禁止法の適用対象に含めるべきかについて
[内閣府]
第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_5/index.html
第5回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 動画配信
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin36.html
2011年08月02日
障害者基本法改正案成立
<全難聴からの配信です>
障がい者制度改革推進会議だより(No.35) 2011.8.1
障がい者制度改革推進会議構成員全難聴常務理事新谷友良
障害者基本法改正案成立!
【障害者基本法国会審議の経過】
障害者基本法の改正については、「推進会議だより」34 号で、6 月14 日衆院内閣委員会で可決、16日の衆院本会議を経て参議院に送られたところまでご報告しました。
その後国会は70 日間の会期延長があり、障害者基本法改正案は成立確実とされていながら、混迷する国会情勢のなか、参議院での審議はなかなか始まりませんでした。
漸く、7 月26 日に法案の趣旨説明が行われ、28日の参議院内閣委員会で2時間10分の審議を行い、全会一致で可決、翌29 日の参議院本会議で可決成立しました。
障害者制度改革が始まって、最初の成果ともいうべき障害者基本法改正ですが、当事者団体などからの歓迎声明は見当たりません。
「可能な限り」という表現に象徴されるように、障害者制度改革第1 段ロケットの推進力に対する不安感がぬぐえない状況です。
【参議院での審議】
7 月28 日の参議院内閣委員会の審議を傍聴しました。政府よりは細野内閣府担当大臣、福山副長官、園田政務官が出席、それに加えて修正案の提案者である民主党の西村議員、公明党の高木議員も答弁に立ちました。
審議では、精神障害の社会的入院の問題、特別支援教育に必要とされる経費、震災での要援護者名簿のありかたなどの質疑がありましたが、自民党の衛藤議員は「権利が前面に出て、福祉向上の規定が削られたのは問題」と質問、これに対し細野大臣は「推進会議の意見を取り入れ、政府案として決定した。」と答弁しました。
また、何人かの議員が「可能な限り」の文言の意味について質問しましたが、細野大臣は「最大限の努力をするという意味」と答弁しました。
審議で注目すべき点は、基本法改正案にある「障害者政策委員会」の構成についてで、委員からは「施設関係者、事業者なども含めた中立・公平なものとすべき」との意見と「委員会構成については、制度改革推進会議の経過を尊重すべき。」との意見が出て、細野大臣は「最終的には首相が決めるが、今までの経緯は尊重したい。」と答弁しました。
法案の採決の後、付帯決議が採択され、衆院段階ではなかった「障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。」という項目が入りました。
「障害者を過半数に」というJDF の要望は無視された形で、後退した付帯決議です。
(註:赤字の強調部分は長野難聴ブログ編集部による強調です)
障がい者制度改革推進会議だより(No.35) 2011.8.1
障がい者制度改革推進会議構成員全難聴常務理事新谷友良
障害者基本法改正案成立!
【障害者基本法国会審議の経過】
障害者基本法の改正については、「推進会議だより」34 号で、6 月14 日衆院内閣委員会で可決、16日の衆院本会議を経て参議院に送られたところまでご報告しました。
その後国会は70 日間の会期延長があり、障害者基本法改正案は成立確実とされていながら、混迷する国会情勢のなか、参議院での審議はなかなか始まりませんでした。
漸く、7 月26 日に法案の趣旨説明が行われ、28日の参議院内閣委員会で2時間10分の審議を行い、全会一致で可決、翌29 日の参議院本会議で可決成立しました。
障害者制度改革が始まって、最初の成果ともいうべき障害者基本法改正ですが、当事者団体などからの歓迎声明は見当たりません。
「可能な限り」という表現に象徴されるように、障害者制度改革第1 段ロケットの推進力に対する不安感がぬぐえない状況です。
【参議院での審議】
7 月28 日の参議院内閣委員会の審議を傍聴しました。政府よりは細野内閣府担当大臣、福山副長官、園田政務官が出席、それに加えて修正案の提案者である民主党の西村議員、公明党の高木議員も答弁に立ちました。
審議では、精神障害の社会的入院の問題、特別支援教育に必要とされる経費、震災での要援護者名簿のありかたなどの質疑がありましたが、自民党の衛藤議員は「権利が前面に出て、福祉向上の規定が削られたのは問題」と質問、これに対し細野大臣は「推進会議の意見を取り入れ、政府案として決定した。」と答弁しました。
また、何人かの議員が「可能な限り」の文言の意味について質問しましたが、細野大臣は「最大限の努力をするという意味」と答弁しました。
審議で注目すべき点は、基本法改正案にある「障害者政策委員会」の構成についてで、委員からは「施設関係者、事業者なども含めた中立・公平なものとすべき」との意見と「委員会構成については、制度改革推進会議の経過を尊重すべき。」との意見が出て、細野大臣は「最終的には首相が決めるが、今までの経緯は尊重したい。」と答弁しました。
法案の採決の後、付帯決議が採択され、衆院段階ではなかった「障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。」という項目が入りました。
「障害者を過半数に」というJDF の要望は無視された形で、後退した付帯決議です。
(註:赤字の強調部分は長野難聴ブログ編集部による強調です)
2011年08月22日
第34回障がい者制度改革推進会議
<全難聴からの配信です>
障がい者制度改革推進会議だより(No.36) 2011.8.19
障がい者制度改革推進会議構成員全難聴常務理事新谷友良
第34 回制度改革推進会議
お盆休みでご報告が遅れています。第34 回制度改革推進会議が8 月8 日に開催されました。障害者基本法の改正が終わり8 月5 日に施行されたので、少しテーマが空いてしまった推進会議ですが、総合福祉部会は障害者総合福祉法(仮称)に対する骨格提言のまとめの正念場に入っています。今回の制度改革推進会議はこの骨格提言素案に対する討議となりました。
【会議の様子】
総合福祉法は廃止の決まっている障害者自立支援法に代わる障害者福祉サービスに係る法律です。総合福祉部会の提言は8 月30 日までにまとめられて、そのあと厚生労働省のもとで4 カ月ぐらいかけて法案を作成来年の通常国会に提出、成立を目指します。
討議の冒頭、佐藤部会長、尾上副部会長が総合福祉法骨格提言素案について概要を説明しました。素案は完成形ではなく「法の理念、目的、範囲」、「新法制定までの道程」、「関連する他の法律との関係」は未だ
準備出来ていないとのことでした。また、今日の推進会議での議論は翌日(8 月9 日開催予定)の総合福祉部会の議論に反映したいと発言がありました。
素案についての議論はさまざまでしたが、「障害の定義」について、基本法と素案の定義が違っているこ
とが議論になりました。部会長よりは、「基本法で議論しきれなかったものを織り込んだ」と説明がありましたが、「定義が異なっていると現場は混乱する」、「基本法にある継続、相当な制限はどうなったか?」などの意見が出ました。
新谷よりは「受給資格が手帳にとどまらず医師の診断書、意見書保持者などにまで広げられているが、身体障害者福祉法などが規定する手帳の仕組みについての議論は?」と質問しましたが、手帳制度との関連は議論できていないとの回答でした。私たちが求める「デシベルダウン」、身体障害者福祉法別表の改定は障害者福祉サービスに大きく影響しますが、この辺りの議論が進んでいないのは気になります。
その他、サービスの支給体系については、「自立支援法の仕組みから脱却を目指したい。個別給付・地域生活支援事業の区別ではなく全国共通の仕組みで提供される支援と地域の実情に応じて提供される支援に分ける。」と部会の考え方の説明がありました。
コミュニケーション支援は全国共通の仕組みで提供される支援とされています。この考え方が整理されて、コミュニケーション支援事業での地域格差の解消、広域派遣の実現、利用者の範囲の制限緩和・撤廃の方向が出てくるかどうか注意したいと思います。
総合福祉部会では8 月9 日の部会の後も精力的な意見の整理が進められています。どのような骨格提言がまとめられるか、皆さんと一緒に注目していきたいと思います。
障がい者制度改革推進会議だより(No.36) 2011.8.19
障がい者制度改革推進会議構成員全難聴常務理事新谷友良
第34 回制度改革推進会議
お盆休みでご報告が遅れています。第34 回制度改革推進会議が8 月8 日に開催されました。障害者基本法の改正が終わり8 月5 日に施行されたので、少しテーマが空いてしまった推進会議ですが、総合福祉部会は障害者総合福祉法(仮称)に対する骨格提言のまとめの正念場に入っています。今回の制度改革推進会議はこの骨格提言素案に対する討議となりました。
【会議の様子】
総合福祉法は廃止の決まっている障害者自立支援法に代わる障害者福祉サービスに係る法律です。総合福祉部会の提言は8 月30 日までにまとめられて、そのあと厚生労働省のもとで4 カ月ぐらいかけて法案を作成来年の通常国会に提出、成立を目指します。
討議の冒頭、佐藤部会長、尾上副部会長が総合福祉法骨格提言素案について概要を説明しました。素案は完成形ではなく「法の理念、目的、範囲」、「新法制定までの道程」、「関連する他の法律との関係」は未だ
準備出来ていないとのことでした。また、今日の推進会議での議論は翌日(8 月9 日開催予定)の総合福祉部会の議論に反映したいと発言がありました。
素案についての議論はさまざまでしたが、「障害の定義」について、基本法と素案の定義が違っているこ
とが議論になりました。部会長よりは、「基本法で議論しきれなかったものを織り込んだ」と説明がありましたが、「定義が異なっていると現場は混乱する」、「基本法にある継続、相当な制限はどうなったか?」などの意見が出ました。
新谷よりは「受給資格が手帳にとどまらず医師の診断書、意見書保持者などにまで広げられているが、身体障害者福祉法などが規定する手帳の仕組みについての議論は?」と質問しましたが、手帳制度との関連は議論できていないとの回答でした。私たちが求める「デシベルダウン」、身体障害者福祉法別表の改定は障害者福祉サービスに大きく影響しますが、この辺りの議論が進んでいないのは気になります。
その他、サービスの支給体系については、「自立支援法の仕組みから脱却を目指したい。個別給付・地域生活支援事業の区別ではなく全国共通の仕組みで提供される支援と地域の実情に応じて提供される支援に分ける。」と部会の考え方の説明がありました。
コミュニケーション支援は全国共通の仕組みで提供される支援とされています。この考え方が整理されて、コミュニケーション支援事業での地域格差の解消、広域派遣の実現、利用者の範囲の制限緩和・撤廃の方向が出てくるかどうか注意したいと思います。
総合福祉部会では8 月9 日の部会の後も精力的な意見の整理が進められています。どのような骨格提言がまとめられるか、皆さんと一緒に注目していきたいと思います。
2012年01月27日
カード・ブレイン・ストーミング
Eテレの「白熱教室」(日曜午後6時~)が面白い。
今、やっているのは、スタンフォード大学の人気教室、ブレインストーミングの手法。
5回連続で、先週はその3回目。
ブレイン・ストーミングとは、集団(グループ)によるアイデア発想法の1つ。会社の研修などではブレストと省略して呼ばれているらしい。
参加しているメンバー各自が「脳みそ」(brain)から、嵐(storm)のように自由奔放にアイデアを出しあって、互いの発想の違いを利用して、新しいアイデアを発見します。
短時間にできるだけ多くのアイデアを出すために、参加者めいめいがカードに書いて、ホワイトボードに貼るという方式もあり、これは「カード・ブレイン・ストーミング」と呼ばれています。
通常6~7名のグループで実施し、下記の4つのルールが決められており、参加するメンバー(ストーマー)は、このルールに従わなければならない。
1.自由奔放(奔放な発想を歓迎し、とっぴな意見でもかまわない)
2.批判厳禁(どんな意見が出てきても、それを批判してはいけない)
3.量を求む(数で勝負する。量の中から質の良いものが生まれる)
4.便乗発展(出てきたアイデアを結合し、改善して、さらに発展させる)
「カードに書いてアイデアを出す」というやり方を応用して、難聴者の会でも、カード・ブレイン・ストーミングの手法が用いられることがあります。
長野難聴の定例会でも過去に複数回、この手法を採用したことがあり、いろいろなアイデアや夢がたくさん出されて楽しかった記憶があります。
== posted by ROKU ==
今、やっているのは、スタンフォード大学の人気教室、ブレインストーミングの手法。
5回連続で、先週はその3回目。
ブレイン・ストーミングとは、集団(グループ)によるアイデア発想法の1つ。会社の研修などではブレストと省略して呼ばれているらしい。
参加しているメンバー各自が「脳みそ」(brain)から、嵐(storm)のように自由奔放にアイデアを出しあって、互いの発想の違いを利用して、新しいアイデアを発見します。
短時間にできるだけ多くのアイデアを出すために、参加者めいめいがカードに書いて、ホワイトボードに貼るという方式もあり、これは「カード・ブレイン・ストーミング」と呼ばれています。
通常6~7名のグループで実施し、下記の4つのルールが決められており、参加するメンバー(ストーマー)は、このルールに従わなければならない。
1.自由奔放(奔放な発想を歓迎し、とっぴな意見でもかまわない)
2.批判厳禁(どんな意見が出てきても、それを批判してはいけない)
3.量を求む(数で勝負する。量の中から質の良いものが生まれる)
4.便乗発展(出てきたアイデアを結合し、改善して、さらに発展させる)
「カードに書いてアイデアを出す」というやり方を応用して、難聴者の会でも、カード・ブレイン・ストーミングの手法が用いられることがあります。
長野難聴の定例会でも過去に複数回、この手法を採用したことがあり、いろいろなアイデアや夢がたくさん出されて楽しかった記憶があります。
== posted by ROKU ==
2012年05月18日
障害者雇用率2%へ引き上げ
マスコミの報道によると、
厚生労働省は17日、民間企業に義務付けている障害者の雇用率を現在の1・8%から2・0%に引き上げる方針を固め、来年度から実施する。(信濃毎日新聞5月17日)
昨年3月の定例会(松川村)で学習したように、 国・地方自治体・企業は障害者雇用を一定パーセント法律で義務付けられいる。義務付けられていても実行されなければ意味がない。
企業や国、自治体が「障害者に対する合理的配慮」を怠り、採用をしないのは差別である。
厚生労働省は17日、民間企業に義務付けている障害者の雇用率を現在の1・8%から2・0%に引き上げる方針を固め、来年度から実施する。(信濃毎日新聞5月17日)
昨年3月の定例会(松川村)で学習したように、 国・地方自治体・企業は障害者雇用を一定パーセント法律で義務付けられいる。義務付けられていても実行されなければ意味がない。
企業や国、自治体が「障害者に対する合理的配慮」を怠り、採用をしないのは差別である。
2012年07月06日
全社協障害関係ニュースから
<全社協より障害関係ニュース(NO.3)が配信されてきました。長野難聴の協会員で配信を希望する方は事務局へ連絡してください。メールを転送いたします。役員の方々には役員メールで転送済みです。(事務局・窪田)
<20ページ以上の大量データーですので、このブログには全部載せきれません。
聴覚障害者に関連のある部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。
(広報部・ブログ担当)>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案の概要(平成24年3月13日 閣議決定)
1.趣 旨
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため、関係法律の整備について定めるものとする。
2.概 要
1.題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。
2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念に新たに掲げる。
3.障害者の範囲
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。(児童福祉法における障害児の範囲も同様に対応。)
4.障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大(「重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるもの」とする)
② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
③ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、手話通訳者等を養成する事業等)
5.サービス基盤の計画的整備
① 基本指針・障害福祉計画について、定期的な検証と見直しを法定化
② 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
③ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
6.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)
① 常時介護を要する者に対する支援、移動の支援、就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対
する支援の在り方
※ 上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。
3.施行期日
平成25年4月1日(ただし、4.①及び②については、平成26年4月1日)
・・・・・・・・・
「障害者総合支援法」と呼ばれている法律は、正式には
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
というのですね。
長い名前ですね。
「寿限無」みたい。(ROKU)
<20ページ以上の大量データーですので、このブログには全部載せきれません。
聴覚障害者に関連のある部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。
(広報部・ブログ担当)>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案の概要(平成24年3月13日 閣議決定)
1.趣 旨
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため、関係法律の整備について定めるものとする。
2.概 要
1.題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。
2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念に新たに掲げる。
3.障害者の範囲
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。(児童福祉法における障害児の範囲も同様に対応。)
4.障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大(「重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるもの」とする)
② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
③ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、手話通訳者等を養成する事業等)
5.サービス基盤の計画的整備
① 基本指針・障害福祉計画について、定期的な検証と見直しを法定化
② 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
③ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
6.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)
① 常時介護を要する者に対する支援、移動の支援、就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対
する支援の在り方
※ 上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。
3.施行期日
平成25年4月1日(ただし、4.①及び②については、平成26年4月1日)
・・・・・・・・・
「障害者総合支援法」と呼ばれている法律は、正式には
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
というのですね。
長い名前ですね。
「寿限無」みたい。(ROKU)
2012年07月06日
「障害者総合支援法」
新しい法律について
広報部長 佐藤和弘
障害者自立支援法に代わる新しい法律が成立しました。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」と言います。
要約筆記に関して、大きな問題といえば、
事業としては”意思疎通支援”の中の1つに位置づけられています。
また、派遣だけではなく”養成”も基本的には市町村の事業に位置づけられたことです。
しかし規模の小さな自治体では養成は無理でしょう。
また、県と市町村との連携や、団体利用についても法律の付帯決議で明記されています。
広報部長 佐藤和弘
障害者自立支援法に代わる新しい法律が成立しました。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」と言います。
要約筆記に関して、大きな問題といえば、
事業としては”意思疎通支援”の中の1つに位置づけられています。
また、派遣だけではなく”養成”も基本的には市町村の事業に位置づけられたことです。
しかし規模の小さな自治体では養成は無理でしょう。
また、県と市町村との連携や、団体利用についても法律の付帯決議で明記されています。