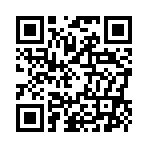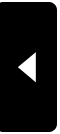2012年07月07日
;「障害者総合支援法」に対する共同声明
<全難聴からの配信です。事務局・窪田>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2012年6月29日
「障害者総合支援法」に対する共同声明
聴覚障害者制度改革推進中央本部 本部長 石野 富志三郎
構成団体
財団法人全日本ろうあ連盟
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
社会福祉法人全国盲ろう者協会
一般社団法人全国手話通訳問題研究会
一般社団法人日本手話通訳士協会
特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会
6月20日、参議院本会議にて「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が十分な審議のないまま採択され、同法が成立しました。
同法の内容は、障害者自立支援法の一部改正に留まるもので、私たち聴覚障害者制度改革推進中央本部が4月25日に発表した「『障害者総合支援法』案に対する声明」で表明したように、
一、障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会がまとめた骨格提言を踏まえたものになっていないこと、
二、障害者自立支援法違憲訴訟の原告団と国(厚生労働省)により締結された基本合意文書に反していること、
このことにより、強く遺憾の意を表します。
また、コミュニケーション支援事業関連の規定については、都道府県事業に「派遣」が広域派遣対応とともに入ったこと、市町村と都道府県の事業の両方に「養成」が明記されたこと、基幹相談支援センターの連携の範囲に意思疎通支援事業の関係者が入ったことなど、私たちが長年にわたって要望してきた事項の一部が規定されていますが、「意思疎通支援」では情報や職場・地域等への参加支援、暮らしの支援、相談支援等と一体になったコミュニケーション支援が抜け落ちてしまう懸念があり、本来ならば「コミュニケーション支援」として入れるべきものです。また、市町村事業と都道府県事業の役割分担を明確に決めておかないと現場が混乱します。財源についても従来通りの統合補助金の枠組みに変わりはなくまったく不充分なものです。
私たちの要望は、総合福祉部会の骨格提言や「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格提言で求めている、
・ 聴覚障害の定義・範囲を見直すこと、
・ 聴覚障害者の生活に関わる情報アクセス・コミュニケーションを権利として保障し、相談支援にかかる情報・コミュニケーションのバリアを解消すること
・ コミュニケーション支援及び通訳・介助支援を全国一律の仕組みとして地域格差を解消すること、
・手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助員の身分を保障すること
等の実現のためには制度設計の根本的な改革が必要です。
「すべての聴覚障害者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める要望書」全国116万人余の署名運動、「We Love コミュニケーション」パンフ普及の取り組みが示すとおり、情報アクセス・コミュニケーションの権利保障を求める私たちの要求は、幅広い国民の理解と支持を得ております。
私たちは、あらためて、障害者総合福祉法の骨格に関する提言と、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法律の実現を強く求め、国(厚生労働省)と国会に対して、以下のことを強く求めます。
記
1.障害者総合支援法が、「障害者総合福祉法の骨格に関する提言」と障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法となるよう、障害当事者と国(厚生労働省)との協議を早急に開始すること、十二分に協議をしないまま省令、実施要項等を出さないこと、また内閣府に設置された障害者政策委員会を障害当事者の視点を充分に尊重して運営させていくこと。
2.聴覚障害者、盲ろう者の情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障し、そのために必要な支援体系を構築すること、そして情報アクセスとコミュニケーションにバリアを抱えるすべての障害者とそれに係わる人々のための「情報・コミュニケーション法(仮称)」を実現すること。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2012年6月29日
「障害者総合支援法」に対する共同声明
聴覚障害者制度改革推進中央本部 本部長 石野 富志三郎
構成団体
財団法人全日本ろうあ連盟
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
社会福祉法人全国盲ろう者協会
一般社団法人全国手話通訳問題研究会
一般社団法人日本手話通訳士協会
特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会
6月20日、参議院本会議にて「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が十分な審議のないまま採択され、同法が成立しました。
同法の内容は、障害者自立支援法の一部改正に留まるもので、私たち聴覚障害者制度改革推進中央本部が4月25日に発表した「『障害者総合支援法』案に対する声明」で表明したように、
一、障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会がまとめた骨格提言を踏まえたものになっていないこと、
二、障害者自立支援法違憲訴訟の原告団と国(厚生労働省)により締結された基本合意文書に反していること、
このことにより、強く遺憾の意を表します。
また、コミュニケーション支援事業関連の規定については、都道府県事業に「派遣」が広域派遣対応とともに入ったこと、市町村と都道府県の事業の両方に「養成」が明記されたこと、基幹相談支援センターの連携の範囲に意思疎通支援事業の関係者が入ったことなど、私たちが長年にわたって要望してきた事項の一部が規定されていますが、「意思疎通支援」では情報や職場・地域等への参加支援、暮らしの支援、相談支援等と一体になったコミュニケーション支援が抜け落ちてしまう懸念があり、本来ならば「コミュニケーション支援」として入れるべきものです。また、市町村事業と都道府県事業の役割分担を明確に決めておかないと現場が混乱します。財源についても従来通りの統合補助金の枠組みに変わりはなくまったく不充分なものです。
私たちの要望は、総合福祉部会の骨格提言や「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格提言で求めている、
・ 聴覚障害の定義・範囲を見直すこと、
・ 聴覚障害者の生活に関わる情報アクセス・コミュニケーションを権利として保障し、相談支援にかかる情報・コミュニケーションのバリアを解消すること
・ コミュニケーション支援及び通訳・介助支援を全国一律の仕組みとして地域格差を解消すること、
・手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助員の身分を保障すること
等の実現のためには制度設計の根本的な改革が必要です。
「すべての聴覚障害者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める要望書」全国116万人余の署名運動、「We Love コミュニケーション」パンフ普及の取り組みが示すとおり、情報アクセス・コミュニケーションの権利保障を求める私たちの要求は、幅広い国民の理解と支持を得ております。
私たちは、あらためて、障害者総合福祉法の骨格に関する提言と、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法律の実現を強く求め、国(厚生労働省)と国会に対して、以下のことを強く求めます。
記
1.障害者総合支援法が、「障害者総合福祉法の骨格に関する提言」と障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法となるよう、障害当事者と国(厚生労働省)との協議を早急に開始すること、十二分に協議をしないまま省令、実施要項等を出さないこと、また内閣府に設置された障害者政策委員会を障害当事者の視点を充分に尊重して運営させていくこと。
2.聴覚障害者、盲ろう者の情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障し、そのために必要な支援体系を構築すること、そして情報アクセスとコミュニケーションにバリアを抱えるすべての障害者とそれに係わる人々のための「情報・コミュニケーション法(仮称)」を実現すること。
2012年08月14日
障害福祉関係ニュース(全社協)1
<学習資料>
障害福祉関係ニュース (その1)
全社協 高年・障害福祉部発行)平成24年度第4号(通算287号)
Ⅰ.障害福祉制度・施策関連情報
1.内閣府「障害者政策委員会」(第1回)を開催
委員長に石川准氏(静岡県立大学国際関係学部教授)が就任
内閣府は平成24 年7 月23 日、「障害者政策委員会」(第1 回)を開催しました。改正障害者基本法(平成23 年7 月29 日成立、8 月5 日公布)により内閣府に置かれることとされた障害者政策委員会は、中央障害者施策推進協議会と障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)が改組されたもので、障害者基本計画について調査審議し、内閣総理大臣をはじめ各大臣への意見、また勧告を行うことができます。
同委員会の開催に伴い、推進会議、また同会議下に置かれた総合福祉部会及び差別禁止部会は7 月24 日をもって廃止され、差別禁止部会は新たに障害者政策委員会の下に設置されることとなりました。
第1 回会合には野田内閣総理大臣が出席し、「政権交代後、障害福祉施策には一貫して重要課題として取り組んできた。道半ばだが共生社会の実現を目指して着実に進んできたと認識している」とした上で、「“Nothing About Us Without Us”-私たちのことを私たち抜きに決めないで-。施策等の議論に障害当事者が参画するスタイルが確立されてきた。新たな障害者基本計画策定が委員会の最初の課題であり、大所高所から議論を深めてほしい。一人でも多くの方にぬくもりを感じてもらえるようなものに仕上げてもらいたい」という趣旨の挨拶がありました。
委員長には石川准氏(静岡県立大学国際関係学部教授)が選出されました。石川委員長は、障害者権利条約の批准国は現在117 か国であること、日本は先進国中、数少ない未批准国であることにふれ「一刻も早く批准のための国内法整備などを進めたい」と挨拶しました。
委員長職務の代理者の指名、また委員長を補佐する副委員長の指名は、後日事務局を介して報告し、第2 回委員会で正式承認を行うこととなりました。
障害者政策委員会運営規則(案)の協議では、欠席委員からの要望を受け、難解なことば等に対するイエローカードやレッドカードの使用を情報保障の観点から了承すること、門川委員(盲ろう重複障害、指点字を介して議論に参加)の要望を受け、同委員を補佐し発言権を有するオブザーバとして福島智(さとし)東京大学教授が参画すること、等を了承しました。
差別禁止部会の設置にあたっては、石川委員長より、委員の棟居快行(むねすえとしゆき)氏(大阪大学大学院高等司法研究科教授)が引き続き部会長として指名されました。関連して、委員から障害者総合支援法の検討規定にあるコミュニケーション支援について部会等を設けて検討してほしいという意見があり、これには委員長が、小委員会で議論の柱として取り上げることを提案し、その方向性が確認されました。
現行の障害者基本計画は平成15~24 年度の10 か年度を期間としており、今後、障害者政策委員会では、平成25 年度からの障害者基本計画策定のため、小委員会(委員はいずれかに所属、所属委員と座長は委員の希望を踏まえ委員長が指名)を設け、月1~2 回の開催で議論を進めていきます。
第1 回差別禁止部会は7 月27 日に、次回の障害者政策委員会は8 月20 日に開催されます。
今後のスケジュール(案)
平成24 年
8月20日 第2 回委員会:新たな障害者基本計画の全体像や総論的な議論
9月~10月 小委員会(前半グループ)
9月目途 差別禁止部会の調査検討終了、結果を委員会に報告
10月~11月 小委員会(後半グループ)
12月後半 小委員会での議論を踏まえた全体的な検討
※委員は前半・後半の各グループの小委員会に1 ずつ参加の予定
障害福祉関係ニュース (その1)
全社協 高年・障害福祉部発行)平成24年度第4号(通算287号)
Ⅰ.障害福祉制度・施策関連情報
1.内閣府「障害者政策委員会」(第1回)を開催
委員長に石川准氏(静岡県立大学国際関係学部教授)が就任
内閣府は平成24 年7 月23 日、「障害者政策委員会」(第1 回)を開催しました。改正障害者基本法(平成23 年7 月29 日成立、8 月5 日公布)により内閣府に置かれることとされた障害者政策委員会は、中央障害者施策推進協議会と障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)が改組されたもので、障害者基本計画について調査審議し、内閣総理大臣をはじめ各大臣への意見、また勧告を行うことができます。
同委員会の開催に伴い、推進会議、また同会議下に置かれた総合福祉部会及び差別禁止部会は7 月24 日をもって廃止され、差別禁止部会は新たに障害者政策委員会の下に設置されることとなりました。
第1 回会合には野田内閣総理大臣が出席し、「政権交代後、障害福祉施策には一貫して重要課題として取り組んできた。道半ばだが共生社会の実現を目指して着実に進んできたと認識している」とした上で、「“Nothing About Us Without Us”-私たちのことを私たち抜きに決めないで-。施策等の議論に障害当事者が参画するスタイルが確立されてきた。新たな障害者基本計画策定が委員会の最初の課題であり、大所高所から議論を深めてほしい。一人でも多くの方にぬくもりを感じてもらえるようなものに仕上げてもらいたい」という趣旨の挨拶がありました。
委員長には石川准氏(静岡県立大学国際関係学部教授)が選出されました。石川委員長は、障害者権利条約の批准国は現在117 か国であること、日本は先進国中、数少ない未批准国であることにふれ「一刻も早く批准のための国内法整備などを進めたい」と挨拶しました。
委員長職務の代理者の指名、また委員長を補佐する副委員長の指名は、後日事務局を介して報告し、第2 回委員会で正式承認を行うこととなりました。
障害者政策委員会運営規則(案)の協議では、欠席委員からの要望を受け、難解なことば等に対するイエローカードやレッドカードの使用を情報保障の観点から了承すること、門川委員(盲ろう重複障害、指点字を介して議論に参加)の要望を受け、同委員を補佐し発言権を有するオブザーバとして福島智(さとし)東京大学教授が参画すること、等を了承しました。
差別禁止部会の設置にあたっては、石川委員長より、委員の棟居快行(むねすえとしゆき)氏(大阪大学大学院高等司法研究科教授)が引き続き部会長として指名されました。関連して、委員から障害者総合支援法の検討規定にあるコミュニケーション支援について部会等を設けて検討してほしいという意見があり、これには委員長が、小委員会で議論の柱として取り上げることを提案し、その方向性が確認されました。
現行の障害者基本計画は平成15~24 年度の10 か年度を期間としており、今後、障害者政策委員会では、平成25 年度からの障害者基本計画策定のため、小委員会(委員はいずれかに所属、所属委員と座長は委員の希望を踏まえ委員長が指名)を設け、月1~2 回の開催で議論を進めていきます。
第1 回差別禁止部会は7 月27 日に、次回の障害者政策委員会は8 月20 日に開催されます。
今後のスケジュール(案)
平成24 年
8月20日 第2 回委員会:新たな障害者基本計画の全体像や総論的な議論
9月~10月 小委員会(前半グループ)
9月目途 差別禁止部会の調査検討終了、結果を委員会に報告
10月~11月 小委員会(後半グループ)
12月後半 小委員会での議論を踏まえた全体的な検討
※委員は前半・後半の各グループの小委員会に1 ずつ参加の予定
2012年08月15日
障害福祉関係ニュース(全社協)その2
<学習資料>
障害福祉関係ニュースから(その2)
2.内閣府「差別禁止部会」を開催
~部会意見の取りまとめに向けて議論~
内閣府は平成24 年7 月13 日、7 月27 日に差別禁止部会(部会長:棟居 快行(むねすえ としゆき)大阪大学大学院高等司法研究科教授)を開催し、「障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等」に関する差別禁止部会の意見(以下、部会意見)の取りまとめに向けた議論が行われました。なお、7月13 日の部会は障がい者制度改革推進会議の下で第21 回となるものであり、7 月27 日の部会は障害者政策委員会の下で第1 回となるものです。
7 月27 日の部会では、組織が改められたことから、会議の冒頭、事務局の 東 俊裕 障害者制度改革担当室長より部会委員の紹介が行われ、推進会議下での委員構成から新たに 植木 淳 委員(北九州市立大学法学部准教授)、大野 更紗 委員(作家)、加納 恵子 委員(関西大学社会学部教授)が加わったことが説明されました。なお、推進会議下で委員であった 松井 亮輔 氏(法政大学名誉教授)は今回委員とはなっていません。また、7 月23 日開催の障害者政策委員会で、石川委員長から差別禁止部会長に、推進会議下から引き続きとなる棟居委員が指名されたことが報告されました。
続いて、棟居部会長から副部会長の選任が諮られ、こちらも推進会議下から引き続き、伊東 弘泰 委員(特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会会長)と 竹下 義樹 委員(社会福祉法人日本盲人会連合会長)が務めることが承認されました。また、オブザーバーとして引き続き、遠藤 和夫 氏(日本経済団体連合会労働政策本部主幹)、高山 祐志郎 氏(日本商工会議所産業政策第二部担当副部長)が参加することも承認されました。
その後、部会意見のまとめに関するスケジュールが以下のとおり示され、9 月14 日の取りまとめを目指すことなどが確認されました。なお、これまで差別禁止部会の取りまとめの名称は「骨格提言」「部会提言」等とされてきましたが、これらの名称は総合福祉部会で使われている印象が強く混乱を生む恐れがあるということから、今後は『「障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等」に関する差別禁止部会の意見』、略して「部会意見」と呼ぶことが今回確認されています。
部会意見のまとめに関するスケジュール
7月13日(金)(総論1)(第21 回として開催)はじめに、目的、理念、障害と差別の定義
7月27日(金)(総論2)国等の責務、その他(ハラスメント、欠格条項、複合差別)、 救済のあり方
8月17日(金)(各論1)①雇用、就労、②司法手続、③政治参加(選挙等)、④公共的施設及び交通施設、⑤情報
8月31日(金)(各論2)⑥教育、⑦商品、役務、不動産の利用、⑧医療、⑨資格取得(欠格事由)、⑩婚姻、妊娠、出産、
養育
9月14日(金)まとめ
9月28日(金)予備日
障害福祉関係ニュースから(その2)
2.内閣府「差別禁止部会」を開催
~部会意見の取りまとめに向けて議論~
内閣府は平成24 年7 月13 日、7 月27 日に差別禁止部会(部会長:棟居 快行(むねすえ としゆき)大阪大学大学院高等司法研究科教授)を開催し、「障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等」に関する差別禁止部会の意見(以下、部会意見)の取りまとめに向けた議論が行われました。なお、7月13 日の部会は障がい者制度改革推進会議の下で第21 回となるものであり、7 月27 日の部会は障害者政策委員会の下で第1 回となるものです。
7 月27 日の部会では、組織が改められたことから、会議の冒頭、事務局の 東 俊裕 障害者制度改革担当室長より部会委員の紹介が行われ、推進会議下での委員構成から新たに 植木 淳 委員(北九州市立大学法学部准教授)、大野 更紗 委員(作家)、加納 恵子 委員(関西大学社会学部教授)が加わったことが説明されました。なお、推進会議下で委員であった 松井 亮輔 氏(法政大学名誉教授)は今回委員とはなっていません。また、7 月23 日開催の障害者政策委員会で、石川委員長から差別禁止部会長に、推進会議下から引き続きとなる棟居委員が指名されたことが報告されました。
続いて、棟居部会長から副部会長の選任が諮られ、こちらも推進会議下から引き続き、伊東 弘泰 委員(特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会会長)と 竹下 義樹 委員(社会福祉法人日本盲人会連合会長)が務めることが承認されました。また、オブザーバーとして引き続き、遠藤 和夫 氏(日本経済団体連合会労働政策本部主幹)、高山 祐志郎 氏(日本商工会議所産業政策第二部担当副部長)が参加することも承認されました。
その後、部会意見のまとめに関するスケジュールが以下のとおり示され、9 月14 日の取りまとめを目指すことなどが確認されました。なお、これまで差別禁止部会の取りまとめの名称は「骨格提言」「部会提言」等とされてきましたが、これらの名称は総合福祉部会で使われている印象が強く混乱を生む恐れがあるということから、今後は『「障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等」に関する差別禁止部会の意見』、略して「部会意見」と呼ぶことが今回確認されています。
部会意見のまとめに関するスケジュール
7月13日(金)(総論1)(第21 回として開催)はじめに、目的、理念、障害と差別の定義
7月27日(金)(総論2)国等の責務、その他(ハラスメント、欠格条項、複合差別)、 救済のあり方
8月17日(金)(各論1)①雇用、就労、②司法手続、③政治参加(選挙等)、④公共的施設及び交通施設、⑤情報
8月31日(金)(各論2)⑥教育、⑦商品、役務、不動産の利用、⑧医療、⑨資格取得(欠格事由)、⑩婚姻、妊娠、出産、
養育
9月14日(金)まとめ
9月28日(金)予備日
2012年08月16日
障害者福祉関係ニュース(全社協) その3
<学習資料>
差別禁止部会<続き>
その後は、「国等の責務」「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」「総則(「理念」「目的」「障害と差別の定義」等)」の3 つのコーナーについて、部会三役の原案をもとに、部会意見の取りまとめに向けた議論が行われました。いずれのコーナーにおいても多岐にわたる意見があがり、棟居部会長は部会三役で改めて検討し、次回以降の部会で引き続き議論する方向性を示しています。
【「国等の責務」について】
部会三役の原案では、国の基本的責務として、
◇差別防止に向けた調査、啓発等の取り組み、
◇情報提供と(不均等待遇や合理的配慮に関する)ガイドラインの作成、
◇関係機関の連携の確保、
◇円滑な救済の仕組み(差別事案が発生した場合の簡易で迅速な解決の仕組み)の
運用と状況報告(受理事案の概要の公表と政策委員会での検証)、
◇(関係機関の職員等に対する)研修及び人材育成、
が挙げられました。
また、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域として、
◆障害女性(複合的な困難を取り除くための適切な措置)、
◆障害に基づくハラスメント(いじめや嫌がらせ等)、
◆欠格条項(資格を取得する上で求められる要件や能力に関わる
制限の必要性を踏まえた検証と措置)、
が挙げられました。
そして、地方公共団体の責務は、国の取組に準じた取組に努めること、国民の責務は、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めることとされました。
委員からは、「国と地方の責務として、合理的配慮に対する財政等の支援を盛り込むべき」といった意見が多くあがりました。これに対し、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、「そもそも合理的配慮がなされないことが差別である以上、国等の支援ありきになってはいけない。アメリカでは、合理的配慮にはガイドラインさえあれば多くの財政出動は必要ないといった声もある。国は第一にガイドラインでの周知徹底に努めるべき」といった認識を示しました。
他にも、「国民の中でも特に事業者の責務を明記すべき」「ジェンダーの視点を反映すべき」などの意見がありました。
<続く>
差別禁止部会<続き>
その後は、「国等の責務」「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」「総則(「理念」「目的」「障害と差別の定義」等)」の3 つのコーナーについて、部会三役の原案をもとに、部会意見の取りまとめに向けた議論が行われました。いずれのコーナーにおいても多岐にわたる意見があがり、棟居部会長は部会三役で改めて検討し、次回以降の部会で引き続き議論する方向性を示しています。
【「国等の責務」について】
部会三役の原案では、国の基本的責務として、
◇差別防止に向けた調査、啓発等の取り組み、
◇情報提供と(不均等待遇や合理的配慮に関する)ガイドラインの作成、
◇関係機関の連携の確保、
◇円滑な救済の仕組み(差別事案が発生した場合の簡易で迅速な解決の仕組み)の
運用と状況報告(受理事案の概要の公表と政策委員会での検証)、
◇(関係機関の職員等に対する)研修及び人材育成、
が挙げられました。
また、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域として、
◆障害女性(複合的な困難を取り除くための適切な措置)、
◆障害に基づくハラスメント(いじめや嫌がらせ等)、
◆欠格条項(資格を取得する上で求められる要件や能力に関わる
制限の必要性を踏まえた検証と措置)、
が挙げられました。
そして、地方公共団体の責務は、国の取組に準じた取組に努めること、国民の責務は、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めることとされました。
委員からは、「国と地方の責務として、合理的配慮に対する財政等の支援を盛り込むべき」といった意見が多くあがりました。これに対し、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、「そもそも合理的配慮がなされないことが差別である以上、国等の支援ありきになってはいけない。アメリカでは、合理的配慮にはガイドラインさえあれば多くの財政出動は必要ないといった声もある。国は第一にガイドラインでの周知徹底に努めるべき」といった認識を示しました。
他にも、「国民の中でも特に事業者の責務を明記すべき」「ジェンダーの視点を反映すべき」などの意見がありました。
<続く>
2012年08月17日
障害者福祉関係ニュースから(その4)
<学習資料>
差別禁止部会
【「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」について】
部会三役の原案では、差別の判断の物差しの提供により差別等の紛争が事前に回避されることが望ましいが、紛争が発生した場合に備えて、司法的解決のほか、紛争の性質に即した簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組みが用意される必要があるとされました。
紛争解決の仕組みに求められる機能としては、
◇相談機能(障害者、家族、障害及び障害者に理解のある専門家などの相談担当者
によるピア・カウンセリング的手法が重要)、
◇調整機能(相談担当者による相手方との関係の調整)、
◇調停もしくは斡旋機能(障害者の権利擁護の専門家を含む
中立・公平な機関によるもの)、
◇仲裁機能(紛争当事者が、第三者の判断に解決を委ねることを予め合意することを
条件に、中立・公平な第三者の判断により紛争の解決を図る)、
◇裁定機能(第三者による裁定等に委ねるか、司法による解決に委ねるか、
法施行後の状況も見つつ検討)、
◇実効性の担保(勧告ないし公表など)、
が示され、
紛争解決に当たる組織の在り方については、
◆相談及び調整を行う機関であれば、市町村が設置する基幹相談支援センター、
都道府県の条例等において独自に設置された広域の相談支援センター等、
◆調停、斡旋、仲裁等を行う機関であれば、障害者基本法に基づいて
都道府県が設置する審議会その他の合議制の機関、
都道府県により障害者の権利擁護を図るために設置された委員会等、
◆中央に置かれる機関であれば、障害者政策委員会等、
が具体的に挙げられ、こうした既存の組織の活用も含め検討されるべきとされました。
委員からは、
「中央で人権救済にあたる調整機関を新たに設けるべき」
といった意見がいくつか挙がりましたが、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、
「過剰な介入を生むとの世間の評価もあり、リスクもある。簡易迅速な裁判外紛争解決を重視している」
とこたえました。
また、相談担当者について
「家族を含めるべきではない。本人の自立を妨げる。本人の『痛み』ではなく人権擁護の視点からの支援が必要」
といった意見もいくつかありました。
差別禁止部会
【「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」について】
部会三役の原案では、差別の判断の物差しの提供により差別等の紛争が事前に回避されることが望ましいが、紛争が発生した場合に備えて、司法的解決のほか、紛争の性質に即した簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組みが用意される必要があるとされました。
紛争解決の仕組みに求められる機能としては、
◇相談機能(障害者、家族、障害及び障害者に理解のある専門家などの相談担当者
によるピア・カウンセリング的手法が重要)、
◇調整機能(相談担当者による相手方との関係の調整)、
◇調停もしくは斡旋機能(障害者の権利擁護の専門家を含む
中立・公平な機関によるもの)、
◇仲裁機能(紛争当事者が、第三者の判断に解決を委ねることを予め合意することを
条件に、中立・公平な第三者の判断により紛争の解決を図る)、
◇裁定機能(第三者による裁定等に委ねるか、司法による解決に委ねるか、
法施行後の状況も見つつ検討)、
◇実効性の担保(勧告ないし公表など)、
が示され、
紛争解決に当たる組織の在り方については、
◆相談及び調整を行う機関であれば、市町村が設置する基幹相談支援センター、
都道府県の条例等において独自に設置された広域の相談支援センター等、
◆調停、斡旋、仲裁等を行う機関であれば、障害者基本法に基づいて
都道府県が設置する審議会その他の合議制の機関、
都道府県により障害者の権利擁護を図るために設置された委員会等、
◆中央に置かれる機関であれば、障害者政策委員会等、
が具体的に挙げられ、こうした既存の組織の活用も含め検討されるべきとされました。
委員からは、
「中央で人権救済にあたる調整機関を新たに設けるべき」
といった意見がいくつか挙がりましたが、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、
「過剰な介入を生むとの世間の評価もあり、リスクもある。簡易迅速な裁判外紛争解決を重視している」
とこたえました。
また、相談担当者について
「家族を含めるべきではない。本人の自立を妨げる。本人の『痛み』ではなく人権擁護の視点からの支援が必要」
といった意見もいくつかありました。
2012年08月19日
ハラスメント
<理論・学習資料>
(障害福祉関係ニュース平成24年第2号より)
ハラスメントに関する論点
第1、「ハラスメント」と差別は行為の類型として同じか、それとも、異なるのか。
※仮に両者が行為の類型として異なるのであれば、
「ハラスメント」を差別の一類型として規定することは困難となる。
その場合、「ハラスメント」を差別以外のものとして規定するという考え方もあるが、
まずは議論の出発点として、
「ハラスメント」と差別の関係をどのように考えるかという観点からの論点。
仮に両者が行為の類型として同じで、
差別の中に「ハラスメント」が入るとすると、次の論点にもあるとおり、
「ハラスメント」の定義が困難であることから、
差別の概念があいまいになってしまうのではないかという別の論点が生じる。
第2、障害者差別禁止法案の検討に当たって、「ハラスメント」の禁止・防止も差別禁止法案の内容とするかどうか。
※「ハラスメント」の禁止・防止を差別禁止法案の内容とするとしても、
「ハラスメント」が刑法上の暴行罪や侮辱罪とどう異なるのか、
「ハラスメント」は力の上下関係を前提としたものかどうか、
といったことが論者によって異なるため、
禁止・防止の対象となる「ハラスメント」を定義することが困難であるという観点からの論点。
第3、仮に、「ハラスメント」の禁止・防止を差別禁止法案の内容とする場合、障害者差別禁止法案と障害者虐待防止法との関係をどのように考えるか。
※障害者虐待防止法では、「障害者虐待」を
「養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。」
と定義していることから、障害者虐待防止法と障害者差別禁止法案の包含関係をどのように考えるのかという観点からの論点。
(障害福祉関係ニュース平成24年第2号より)
ハラスメントに関する論点
第1、「ハラスメント」と差別は行為の類型として同じか、それとも、異なるのか。
※仮に両者が行為の類型として異なるのであれば、
「ハラスメント」を差別の一類型として規定することは困難となる。
その場合、「ハラスメント」を差別以外のものとして規定するという考え方もあるが、
まずは議論の出発点として、
「ハラスメント」と差別の関係をどのように考えるかという観点からの論点。
仮に両者が行為の類型として同じで、
差別の中に「ハラスメント」が入るとすると、次の論点にもあるとおり、
「ハラスメント」の定義が困難であることから、
差別の概念があいまいになってしまうのではないかという別の論点が生じる。
第2、障害者差別禁止法案の検討に当たって、「ハラスメント」の禁止・防止も差別禁止法案の内容とするかどうか。
※「ハラスメント」の禁止・防止を差別禁止法案の内容とするとしても、
「ハラスメント」が刑法上の暴行罪や侮辱罪とどう異なるのか、
「ハラスメント」は力の上下関係を前提としたものかどうか、
といったことが論者によって異なるため、
禁止・防止の対象となる「ハラスメント」を定義することが困難であるという観点からの論点。
第3、仮に、「ハラスメント」の禁止・防止を差別禁止法案の内容とする場合、障害者差別禁止法案と障害者虐待防止法との関係をどのように考えるか。
※障害者虐待防止法では、「障害者虐待」を
「養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。」
と定義していることから、障害者虐待防止法と障害者差別禁止法案の包含関係をどのように考えるのかという観点からの論点。
2012年09月10日
内閣府「障害者政策委員会 差別禁止部会」
学習資料 <福祉関係ニュースから②>
2.内閣府「障害者政策委員会 差別禁止部会」(第2回)を開催
~各論(前半)における障害を理由とする差別の禁止について検討~
内閣府は平成24年8月17日、障害者政策委員会の下では第2回となる差別禁止部会(部会長:棟居 快行(むねすえ としゆき) 大阪大学大学院高等司法研究科教授)を開催し、部会意見の取りまとめに向けた検討を行いました。
今回の部会では、部会三役により、
①「はじめに」と、
②各論前半として
「雇用」
「司法手続き」
「政治参加(選挙等)」
「公共的施設及び交通機関の利用」
「情報とコミュニケーション」に関する部会意見案、
またこれまでの検討を踏まえた
③「総則」
「国等の責務」
「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」
に関する部会意見修正案が示されました。
このうち、②各論前半の検討に多くの時間が割かれたため、①「はじめに」と③「総則」「国等の責務」「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」については十分な議論が行われず、委員からは後日文書で意見が求められることとなっています。
②各論前半に関する部会三役の原案では、各分野における、差別の禁止が求められる対象範囲、不均等待遇、合理的配慮とその不提供を正当化する事由に関する考え方や具体例などが示されました。
「雇用」においては、福祉的就労について、いわゆる就労継続支援A型事業で働く障害者はもちろんのこと、B型事業で働く障害者であっても実体として労働者性が認められる場合には差別禁止法の対象とすべきとされました。
棟居部会長からは「各論については各省庁の所管に基づいてまとめており、あくまで個別の施策に対する意見としての書きぶりにしている。差別禁止部会は縦割り行政への対応に向けた組織ではあるが、各省庁の所管というハードルが差別禁止法の制定に向け最大の難関となるだろう」とコメントしました。
また、事務局の東障害者制度改革担当室長からは「各論は総論で述べている障害者の権利性などを踏まえている」との説明がありました。
次回の第3回部会は8月31日(金)に開催され、各論後半「教育」「商品、役務、不動産の利用」「医療」「資格取得(欠格事由)」「婚姻、妊娠、出産、養育」などについて検討が行われる予定です。
なお、部会意見は9月14日(金)に開催される第4回部会での取りまとめが目指されており、そこでまとまらない場合に備えて9月28日(金)が予備日となっています。
[内閣府]第2回障害者政策委員会 差別禁止部会 資料等
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/b_2/index.html
障害者政策委員会 差別禁止部会 ←動画配信が確認できます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#bu
2.内閣府「障害者政策委員会 差別禁止部会」(第2回)を開催
~各論(前半)における障害を理由とする差別の禁止について検討~
内閣府は平成24年8月17日、障害者政策委員会の下では第2回となる差別禁止部会(部会長:棟居 快行(むねすえ としゆき) 大阪大学大学院高等司法研究科教授)を開催し、部会意見の取りまとめに向けた検討を行いました。
今回の部会では、部会三役により、
①「はじめに」と、
②各論前半として
「雇用」
「司法手続き」
「政治参加(選挙等)」
「公共的施設及び交通機関の利用」
「情報とコミュニケーション」に関する部会意見案、
またこれまでの検討を踏まえた
③「総則」
「国等の責務」
「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」
に関する部会意見修正案が示されました。
このうち、②各論前半の検討に多くの時間が割かれたため、①「はじめに」と③「総則」「国等の責務」「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」については十分な議論が行われず、委員からは後日文書で意見が求められることとなっています。
②各論前半に関する部会三役の原案では、各分野における、差別の禁止が求められる対象範囲、不均等待遇、合理的配慮とその不提供を正当化する事由に関する考え方や具体例などが示されました。
「雇用」においては、福祉的就労について、いわゆる就労継続支援A型事業で働く障害者はもちろんのこと、B型事業で働く障害者であっても実体として労働者性が認められる場合には差別禁止法の対象とすべきとされました。
棟居部会長からは「各論については各省庁の所管に基づいてまとめており、あくまで個別の施策に対する意見としての書きぶりにしている。差別禁止部会は縦割り行政への対応に向けた組織ではあるが、各省庁の所管というハードルが差別禁止法の制定に向け最大の難関となるだろう」とコメントしました。
また、事務局の東障害者制度改革担当室長からは「各論は総論で述べている障害者の権利性などを踏まえている」との説明がありました。
次回の第3回部会は8月31日(金)に開催され、各論後半「教育」「商品、役務、不動産の利用」「医療」「資格取得(欠格事由)」「婚姻、妊娠、出産、養育」などについて検討が行われる予定です。
なお、部会意見は9月14日(金)に開催される第4回部会での取りまとめが目指されており、そこでまとまらない場合に備えて9月28日(金)が予備日となっています。
[内閣府]第2回障害者政策委員会 差別禁止部会 資料等
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/b_2/index.html
障害者政策委員会 差別禁止部会 ←動画配信が確認できます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#bu
2013年04月12日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(1)<学習資料>
全難聴からの情報です。
厚労省から下記の文書が出ておりま す。
学習資料としてください。
(膨大な文書ですので、数回に分けて掲載します)
厚労省から下記の文書が出ておりま す。
学習資料としてください。
(膨大な文書ですので、数回に分けて掲載します)
障企自発0327第1号
平成25年3月27日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中 核 市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室長
(公 印 省 略)
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
障害者自立支援法における地域生活支援事業で実施してきた手話通訳等を行う者の派遣又は養成を行う事業については、市町村と都道府県が行う事業の専門性の差異が明確ではなく、市町村と都道府県の役割分担が明確でないこと、広域的な派遣等について都道府県の関与が明確ではなかったこと等の課題があった。
このため、平成25年4月1日から施行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」(以下「障害者総合支援法」という。)における地域生活支援事業では、これらの課題を解消する観点から、意思疎通支援の強化を図ることとしている。
特に市町村及び都道府県が行う意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者の派遣に関する主な内容については、下記のとおりとなるので、意思疎通支援を行う者の派遣に係る事業を実施の際は、本通知で示す意思疎通支援事業実施要綱を参考に事業実施を検討されたい。
貴職におかれては御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に対する周知につきご配慮願いたい。
記
1 市町村が実施する意思疎通支援を行う者の派遣について
市町村においては、地域生活支援事業の必須事業として、少なくとも手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行う事業を実施することになる。
事業の実施方法については、地域における事業実施の差異を解消する観点から、別紙1の区市町村意思疎通支援事業実施要綱を参考に実施するように努められたい。
また、別添では、区市町村意思疎通支援事業実施要綱の解釈等について記載しているので、実施要綱を作成する際の参考にされたい。
2 都道府県が実施する意思疎通支援を行う者の派遣等について
意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者の派遣は、市町村地域生活支援事業の必須事業であるため、原則、市町村が実施することになる。都道府県では、市町村相互間の連絡調整等を経てもなお、市町村が手話通訳者及び要約筆記者の派遣を実施できない場合等に手話通訳者及び要約筆記者の派遣事業を実施する必要がある。
平成25年4月1日から施行される障害者総合支援法における地域生活支援事業では、「専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣」及び「意思疎通支援を行う者(手話通訳者及び要約筆記者)の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」が新たに都道府県地域生活支援事業の必須事業となることから、都道府県意思疎通支援事業実施要綱を別紙2のとおり作成したので、本実施要綱を参考に事業を実施するように努められたい。
また、別添の区市町村意思疎通支援事業実施要綱の解釈等についても、実施要綱を作成する際に参考となると考えられることから活用されたい。
2013年04月13日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(2)<学習資料>
<学習資料>
(続く)
○○市(区市町村)意思疎通支援事業実施要綱。
平成〇〇年〇月〇日
○○区市町村長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 前条の目的を達成するため、○○市(区市町村)意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者(第6条第3項の規定により○○市(区市町村)意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)のうち、手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務
(4) 前2号及び3号を行う連絡調整業務等担当者の設置
(5) 意思疎通支援事業が円滑に行われるよう運営委員会の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は○○市(区市町村)とする。
(市町村の責務)
第4条 市(区市町村)長はこの事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない
(続く)
2013年04月15日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(4)<学習資料>
意思疎通支援を行う者の派遣等について(4)<学習資料>を連載中です。
(派遣の対象者等)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、○○市(区市町村)内に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、他の市(区市町村)長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市(区市町村)の聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、○○市(区市町村)内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする○○市(区市町村)外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
(派遣の内容等)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 市(区市町村)長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 市(区市町村)長が、公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域及び時間)
第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、○○県(都道府県)内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を○○県(都道府県)外に派遣することができるものとする。ただし、市(区市町村)長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前○○時から午後○○時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。
(派遣の申請)
第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第9条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体
(4)不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市(区市町村)長が必要と認めるもの
2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の○日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、○○市(区市町村)意思疎通支援者派遣申請書(様式例第7号。以下「派遣申請書」という。)により、市(区市町村)長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の決定)
第13条 市(区市町村)長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、○○市(区市町村)意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式例第8号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市(区市町村)長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、○○市(区市町村)手話通訳・要約筆記依頼書(様式例第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第15条 市(区市町村)長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎
5
通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに○○市(区市町村)意思疎通支援者派遣業務報告書(様式例第10号。以下「業務報告書」という。)を作成し、市(区市町村)長が指定する日までに市(区市町村)長に提出しなければならない。
(派遣の報酬等)
第17条 市(区市町村)長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、第11条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
2013年04月16日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(3)<学習資料>
意思疎通支援を行う者の派遣等について(3)<学習資料>
編集ミスにより、(3)のアップが(4)の後にきてしまいました。
編集ミスにより、(3)のアップが(4)の後にきてしまいました。
(事業の委託及び監督等)
第5条 1市町村長は、第2条に規定する業務を市町村長が適当と認めた法人(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。
2 市町村長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による市町村長の監督を受け、市町村長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(意思疎通支援者の登録)
第6条 ○○市(区市町村)意思疎通支援者としての登録を希望する者は、○○市(区市町村)意思疎通支援者登録申請書(様式例第1号)に、手話通訳者については次の第1号から第3号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を、又は要約筆記者については次の第4号から第5号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を添付して、市(区市町村)長に申請するものとする。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) ○○県(都道府県)手話通訳者登録試験の合格者
(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者
(4) ○○県(都道府県)要約筆記者登録試験の合格者
(5) 前号で規定するものと同等と認められる者
2 市(区市町村)長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、その旨を○○市(区市町村)意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式例第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市(区市町村)長は、前項の規定により○○市(区市町村)意思疎通支援者として決定したときは、○○市(区市町村)意思疎通支援者登録台帳(様式例第3号)に登録するものとする。
(意思疎通支援者証)
第7条 市(区市町村)長は、意思疎通支援者に○○市(区市町村)意思疎通支援者証(様式例第4号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。ただし、○○県(都道府県)意思疎通支援者証を所持している場合は交付を省略できるものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、○年とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに○○市(区市町村)意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式例第5号)を、市(区市町村)長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに○○市(区市町村)意思疎通支援者登録事項変更届(様式例第6号)を、市(区市町村)長に提出しなければならない。
6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を市(区市町村)長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
2013年04月17日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(5)<学習資料>
※全難聴からの配信を5回にわたり掲載してきました。
今回でおしまいです。
意思疎通支援を行う者の派遣等について(5)<最終回>
今回でおしまいです。
意思疎通支援を行う者の派遣等について(5)<最終回>
(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第18条 市(区市町村)長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。
(頸肩腕障害に関する健康診断)
第19条 市(区市町村)長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。
(運営委員会)
第20条 市(区市町村)長は、○○市(区市町村)意思疎通支援事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、事業の効率的な運営を図るものとする。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者によって構成するものとする。
(1) 聴覚障害者団体から選出された者又は聴覚障害者等
(2)意思疎通支援者
(3)前2号に掲げるもののほか、市(区市町村)長が必要と認める者
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市(区市町村)長が別に定める。
2013年05月11日
障害者差別解消法案
【学習資料】(障害福祉関係ニュースから)
「障害者差別解消法案」を閣議決定、国会に提出(政府)
政府は平成25年4月26日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害者差別解消法案/旧仮称:障害者差別禁止法)を閣議決定し、開会中の国会(第183回常会)に提出しました。法律案では、法の施行は平成28年4月1日とされています。
法制化に向けては、平成24年9月14日に障害者政策委員会・差別禁止部会が「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」をとりまとめ、内閣府がパブリックコメントを行った結果が3月14日に公表されています。
差別禁止部会がまとめた意見と、国会提出法案との大きな違いは3点、①差別の定義がないこと、②合理的配慮の提供義務が公的機関に限られ、民間事業者は努力義務と規定されていること、③紛争解決の手段は相談が主で調停等の体制整備が想定されていないこと(即訴訟になることも考えられること)です。法案には施行後3年で必要な見直しを行う規定が設けられており、改善に向けての取り組みが求められるところです。
なお、法律案要綱では、行政機関等の職員のための対応要領(ガイドライン)の策定は、国等には義務とされていますが、地方公共団体や地方独立行政法人には「努力義務」とされました。
このことに関連して、閣議決定後の同日4月26日に行われた政党(自民党および公明党/開催時刻順)の説明会では、内閣府の伊奈川大臣官房審議官は、何が差別であるかはガイドラインで例示すること、ガイドラインの策定にあたっては、障害者その他の関係者の意見を反映させるための必要な措置を講ずること、国民への啓発の中で、「行政において障害者支援施設の認可に際して住民の同意を求めないことが考えられる」との内容を盛り込むと述べるとともに、地方分権の関係上、地方公共団体には義務づけできないと説明しました。
関連箇所は、下記内閣府URLから、法律案要綱:「第三 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置」の「三 国等職員対応要領」「四 地方公共団体等職員対応要領」をご覧ください。
一方、障害者政策委員会は平成24年12月17日に、『新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見』をまとめていますが、平成25年からの新たな障害者基本計画は未だ閣議決定をみていません。併せて障害者権利条約批准の動きも注視してまいります。
[内閣府]
第183回 通常国会提出法案
http://www.cao.go.jp/houan/183/index.html(概要、要綱、提出理由等)
[電子政府の総合窓口]
パブリックコメント結果:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121140&Mode=2
「障害者差別解消法案」を閣議決定、国会に提出(政府)
政府は平成25年4月26日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害者差別解消法案/旧仮称:障害者差別禁止法)を閣議決定し、開会中の国会(第183回常会)に提出しました。法律案では、法の施行は平成28年4月1日とされています。
法制化に向けては、平成24年9月14日に障害者政策委員会・差別禁止部会が「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」をとりまとめ、内閣府がパブリックコメントを行った結果が3月14日に公表されています。
差別禁止部会がまとめた意見と、国会提出法案との大きな違いは3点、①差別の定義がないこと、②合理的配慮の提供義務が公的機関に限られ、民間事業者は努力義務と規定されていること、③紛争解決の手段は相談が主で調停等の体制整備が想定されていないこと(即訴訟になることも考えられること)です。法案には施行後3年で必要な見直しを行う規定が設けられており、改善に向けての取り組みが求められるところです。
なお、法律案要綱では、行政機関等の職員のための対応要領(ガイドライン)の策定は、国等には義務とされていますが、地方公共団体や地方独立行政法人には「努力義務」とされました。
このことに関連して、閣議決定後の同日4月26日に行われた政党(自民党および公明党/開催時刻順)の説明会では、内閣府の伊奈川大臣官房審議官は、何が差別であるかはガイドラインで例示すること、ガイドラインの策定にあたっては、障害者その他の関係者の意見を反映させるための必要な措置を講ずること、国民への啓発の中で、「行政において障害者支援施設の認可に際して住民の同意を求めないことが考えられる」との内容を盛り込むと述べるとともに、地方分権の関係上、地方公共団体には義務づけできないと説明しました。
関連箇所は、下記内閣府URLから、法律案要綱:「第三 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置」の「三 国等職員対応要領」「四 地方公共団体等職員対応要領」をご覧ください。
一方、障害者政策委員会は平成24年12月17日に、『新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見』をまとめていますが、平成25年からの新たな障害者基本計画は未だ閣議決定をみていません。併せて障害者権利条約批准の動きも注視してまいります。
[内閣府]
第183回 通常国会提出法案
http://www.cao.go.jp/houan/183/index.html(概要、要綱、提出理由等)
[電子政府の総合窓口]
パブリックコメント結果:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121140&Mode=2
2013年10月10日
10・5信毎社説のどこが問題か
信濃毎日新聞10月5日社説の問題点
この件について、ろぜっと山口さんのブログに的確な指摘がありました。
URLを張り付けてありますから、何時でも読めるわけですが、
ここでもう一度、当ブログとして整理しておきたいと思います。
正確を期するため、信濃毎日新聞の10月5日社説の問題個所を引用します。
ろぜっと山口さんのご指摘(ブログより引用)
ろぜっと山口さんのご指摘のとおりなのですが、
当ブログとして、補足と言うか蛇足かもしれませんが、一言述べておきたい。
1.「速記」ねえ! 懐かしい用語です。非常に特殊な「速記記号」を使った「速記術」。
現今では、なぜか国会の両院で(のみ)用いられています。
ちなみに私は学生の頃「早稲田式速記術」に興味を持ったことがあります。
2.「映写」ねえ! これも子供の頃、「幻灯」とか「映写機」って、あったなあ。
3.「手話と併せて必要な通訳」ねえ! 手話と併せて文字を読む?!
そんな器用な人が居るんでしょうか。
極めつけは最後の文章。
「これを選挙運動で行うと公職選挙法に違反することが分かり・・・結果的に法改正には結び付かず」(A)
という文章のあとに、突如として
「このころ各地の議場で盛んに見られた手話・要約筆記通訳も、今では少なくなっている」(B)
と続けている。
(A)と(B)とは、全く次元の異なる話で、公職選挙法の「文書・図画」の話と、
各地の議場での傍聴とが、ごっちゃになっています。
(A)だから(B)という結論付けには必然性がなく、
記者の勝手な妄想
に過ぎない。
「記者の」と書きましたが、これは記者の署名記事ではなくて「社説」ですぞ。
編集会議を通して文章が練られるはずの、社の英知・知性を代表するはずの「社説」とは到底思えない。
(六万石)
この件について、ろぜっと山口さんのブログに的確な指摘がありました。
URLを張り付けてありますから、何時でも読めるわけですが、
ここでもう一度、当ブログとして整理しておきたいと思います。
正確を期するため、信濃毎日新聞の10月5日社説の問題個所を引用します。
長野県でも10年ほど前、耳の不自由な人たちの権利保障に向けた運動が起きた。手話と併せて必要な通訳に、話し手の言葉を速記してスクリーンなどに映写する「要約筆記」がある。これを選挙運動で行うと公職選挙法に違反することが分かり、県内20の議会が、法改正を求める意見書を国に送った。結果的に法改正には結び付かず、このころ各地の議場で盛んに見られた手話・要約筆記通訳も、今では少なくなっている。
ろぜっと山口さんのご指摘(ブログより引用)
(・・・前略)こういうデタラメな記事を書かれると、要約筆記者として、非常に困る。
1.要約筆記は速記しているのではない。
2.「映写」という表現も、映像のようなイメージを与え、誤解のもと。
3.手話と合わせなくても、それ単体で必要としている人はかなりの数に上るということ。
(中略)
手話言語条例を取り上げただけでも“拍手”ですけど…取材不足のデタラメは許せませんねicon08
各地の議場で盛んに見られた手話・要約筆記通訳も、今では少なくなっている。
という表現もあるが…手話や要約筆記が少なくなってきたのではない!
議会が退屈でつまらないものになっているため、聴覚障害者の議会傍聴が減少しているのだ!!
関連の議題があれば、聴覚障害者も傍聴に行くだろう。
そうなれば、通訳も当然つく。
問題なのは、聴覚障害者が興味を持てないような議会が問題なのだ!
「少なくなって」いない。登録者数は明らかに増えている。
そういうところの取材も不足している。
話題性のあるところに食いつくのは良いが、
その話を展開させていくための取材・調査はもっとしっかり行ってもらいたい。
いい加減なレベルの話を書かれると、要約筆記の利用者減少にもつながりかねない。
だいたいもとから少ないのに…減っていることの、速記だことの、
映像みたいに流れていくことの…と
違ったイメージを植え付けられたら…たまらんicon08
(後略)
ろぜっと山口さんのご指摘のとおりなのですが、
当ブログとして、補足と言うか蛇足かもしれませんが、一言述べておきたい。
1.「速記」ねえ! 懐かしい用語です。非常に特殊な「速記記号」を使った「速記術」。
現今では、なぜか国会の両院で(のみ)用いられています。
ちなみに私は学生の頃「早稲田式速記術」に興味を持ったことがあります。
2.「映写」ねえ! これも子供の頃、「幻灯」とか「映写機」って、あったなあ。
3.「手話と併せて必要な通訳」ねえ! 手話と併せて文字を読む?!
そんな器用な人が居るんでしょうか。
極めつけは最後の文章。
「これを選挙運動で行うと公職選挙法に違反することが分かり・・・結果的に法改正には結び付かず」(A)
という文章のあとに、突如として
「このころ各地の議場で盛んに見られた手話・要約筆記通訳も、今では少なくなっている」(B)
と続けている。
(A)と(B)とは、全く次元の異なる話で、公職選挙法の「文書・図画」の話と、
各地の議場での傍聴とが、ごっちゃになっています。
(A)だから(B)という結論付けには必然性がなく、
記者の勝手な妄想
に過ぎない。
「記者の」と書きましたが、これは記者の署名記事ではなくて「社説」ですぞ。
編集会議を通して文章が練られるはずの、社の英知・知性を代表するはずの「社説」とは到底思えない。
(六万石)
2014年09月17日
聴障者ねらいの詐欺注意
松本市内(伊勢町通り) Photo by T.Sato
中央奥にみえるのが美ヶ原
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
詐欺に要注意!!
最近、聴覚障害者を狙った詐欺被害が続出しています。
こんなお話しにはご注意を!
・「販売や入会の勧誘を目的とした、説明会がある」
・「お金を投資すると、高額な利益がある」
・「会員を増やすと、褒賞としてお金をもらえる」
など。
長野県聴覚障害者情報センターHPから引用
手話通訳付きのケースも多いと書いてあります。。
要注意ですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年02月17日
団体派遣の法的根拠
≪学習資料≫
意思疎通支援事業の広域派遣、団体派遣の法的根拠
障害者総合支援法における主な改正点
(1) 市町村と都道府県の役割分担の明確化
障害者総合支援法の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則において、市町村と都道府県の具体的な役割分担を明確に区分できるよう規定しています。
これにより、市町村と都道府県が行う意思疎通支援を行う者の養成については、市町村と都道府県の必須事業となっており、その役割分担については以下のとおりです。
市町村は、手話奉仕員の養成
都道府県は、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成
また、市町村と都道府県が行う意思疎通支援を行う者の派遣についても、市町村と都道府県の必須事業となっており、その役割分担については以下のとおりです。
市町村は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣(点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を含む)
都道府県は、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣のほか、複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等や専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合などにおける手話通訳者及び要約筆記者の派遣
(2) 広域的な対応が必要なものの都道府県事業の必須化
市町村域又は都道府県域を越えた広域的な派遣については、市町村では派遣することができない場合がある等の課題があったため、以下の事業を新たに都道府県の必須事業としています。
特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業
意思疎通支援を行う者(手話通訳者及び要約筆記者)の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
ここで、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業は、(1)で述べたとおり、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣のほか、手話通訳者及び要約筆記者の派遣において複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等や専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合などへの派遣を想定しています。
また、都道府県が手話通訳者及び要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を担うことにより、市町村域を越えた派遣が市町村において適切に実施されると考えています。
これらの改正により、市町村で実施が難しかった市町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣や専門性の高い分野などへの派遣が可能となり、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立と社会参加が一層促進することになると考えています。
参考文献(厚生労働省)→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sanka/shien.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪会員ブログから≫
「うつくしの湯」(上田市武石地区(旧武石村))

日帰り温泉施設です。
名前の通り美ヶ原のふもとにあります。
入浴料は500円です・・・
続けて記事を読む→http://alps8.blog.fc2.com/blog-entry-727.html
会員ブログ「信州の隠れ家より」から引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
意思疎通支援事業の広域派遣、団体派遣の法的根拠
障害者総合支援法における主な改正点
(1) 市町村と都道府県の役割分担の明確化
障害者総合支援法の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則において、市町村と都道府県の具体的な役割分担を明確に区分できるよう規定しています。
これにより、市町村と都道府県が行う意思疎通支援を行う者の養成については、市町村と都道府県の必須事業となっており、その役割分担については以下のとおりです。
市町村は、手話奉仕員の養成
都道府県は、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成
また、市町村と都道府県が行う意思疎通支援を行う者の派遣についても、市町村と都道府県の必須事業となっており、その役割分担については以下のとおりです。
市町村は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣(点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を含む)
都道府県は、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣のほか、複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等や専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合などにおける手話通訳者及び要約筆記者の派遣
(2) 広域的な対応が必要なものの都道府県事業の必須化
市町村域又は都道府県域を越えた広域的な派遣については、市町村では派遣することができない場合がある等の課題があったため、以下の事業を新たに都道府県の必須事業としています。
特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業
意思疎通支援を行う者(手話通訳者及び要約筆記者)の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
ここで、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業は、(1)で述べたとおり、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣のほか、手話通訳者及び要約筆記者の派遣において複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等や専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合などへの派遣を想定しています。
また、都道府県が手話通訳者及び要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を担うことにより、市町村域を越えた派遣が市町村において適切に実施されると考えています。
これらの改正により、市町村で実施が難しかった市町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣や専門性の高い分野などへの派遣が可能となり、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立と社会参加が一層促進することになると考えています。
参考文献(厚生労働省)→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sanka/shien.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪会員ブログから≫
「うつくしの湯」(上田市武石地区(旧武石村))

日帰り温泉施設です。
名前の通り美ヶ原のふもとにあります。
入浴料は500円です・・・
続けて記事を読む→http://alps8.blog.fc2.com/blog-entry-727.html
会員ブログ「信州の隠れ家より」から引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年03月05日
ノーマライゼーション

Photo by LEGACY
庭先に現れた、かわいい小鹿・・・
本当は、木の芽や樹皮などの食害にさらされている庭にとっては”害獣”なのですが・・・
写真を見ると、とってもカワユイので許してあげたくなります。
続けて読む → http://alps8.blog.fc2.com/blog-entry-743.html
会員ブログ「信州の隠れ家より」(3/4記事)
===========================
≪学習記事≫
ノーマライゼーション Normalization とは
..................................................
社会的支援を必要としている人々を
『いわゆるノーマルな人にすることを目的としているのではなく、『ノーマライゼーション原理とは何か』河東田博(2009)より
その障害を共に受容することであり、
彼らにノーマルな生活条件を提供すること』
..............................................
庄司和史(まさし)先生講演(耳の日フェスティバル 3/1)より
============================
2015年03月10日
差別の事例

早春の常念岳 (松本市 赤木地籍より)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪学習記事≫
差別の事例
耳の日フェスティバル3/1 庄司和史(まさし)先生講演から
・重度の障害者の病院を訪ねて
「ああいう人に人格はあるの?」
(元東京都知事,1999年)
・認知症でひとりで出かけられなくなった人を見て
「ああなっちゃ おしまいだね」
「そうだね」
という会話。
・新生児聴覚スクリーニングで「難聴の疑いがあります」と告知された孫について、
「誰にも言っちゃダメだよ」
と母親に指示した話。
関連記事 → http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1674761.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.3.10