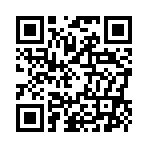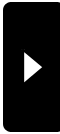2014年09月30日
要約筆記が命綱

塩尻市(郷原) Photo by T.Sato
レタス畑の向こう、左右から山が迫っているところにが、
木曽谷への入り口。(JR中央西線が通る)
木曾御嶽は、ここからは見えません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
要約筆記が命綱
ちょっとだけ手話を勉強している、
という難聴者は多い。
私も、その「ちょっとだけ」組である。
たとえちょっとだけでも、
それは楽しくて、
日常のちょっとした会話ができてうれしい。
しかし、各種研修会や講演会で、
手話通訳のスピードについていけるというと、
そんなわけにはいかない。
手話は、「読み取り」がすごく難しい。
私にとって、情報保障は、
やっぱり、
要約筆記が命綱だ。
(R)
2014年09月29日
松本市登録要約筆記者研修会
☆御嶽山噴火で県総合防災訓練が中止になったことに伴い
予定していた10月定例会は中止となりました。
☆松本市役所障害・生活支援課より、集会への参加依頼がきております。
定例会に準ずるものとして下記の集会に、ふるって参加しましょう。
第2回松本市登録要約筆記者研修会
・期 日 平成26年10月18日(土)
・時 間 午前10時~12時
・場 所 松本市総合社会福祉センター 大会議室
・内 容 要約筆記
・主 催 松本市役所 障害・生活支援課
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
予定していた10月定例会は中止となりました。
☆松本市役所障害・生活支援課より、集会への参加依頼がきております。
定例会に準ずるものとして下記の集会に、ふるって参加しましょう。
第2回松本市登録要約筆記者研修会
・期 日 平成26年10月18日(土)
・時 間 午前10時~12時
・場 所 松本市総合社会福祉センター 大会議室
・内 容 要約筆記
・主 催 松本市役所 障害・生活支援課
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年09月29日
2014年09月29日
「口話」と「読話」

塩尻市(郷原) Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<トリビア万華鏡>
「口話」と「読話」
【読話(どくわ)】『三省堂 大辞林』より引用。
相手の口の動きや表情から音声言語を読み取り理解すること。
聴覚障害者のコミュニケーション方法の一。
【口話(こうわ)】
聴覚障害者が,相手の音声言語を読話によって理解し,
自らも発話により音声言語を用いて意思伝達を行うこと。
「口話」は、ろう者の場合に使う用語。
たとえば、
「ろう学校では手話ではなくて、口話である」
「ろう学校で、口話教育で発声指導を受けた」
等のように、用います。
中途失聴者場合は、
発声はもともと出来るわけだから
「口話」ではなく、
「読話」という用語を使うべきでしょうね。
(R)
三省堂「大辞林」
2014年09月28日
聴障者の災害時着用ビブス

昭和の風景(松本市、中央三) Photo by T.Sato
松本市内の、高砂通りの近く。
市のど真ん中に、
昭和の時代の、そのままに営業中。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
災害時のビブスの文字表現
多くの自治体で、聴覚障害者が災害時に着用するビブスを支給するようになっている。
同時にまた、要約筆記者用、手話通訳者用のビブスもある。
大変ありがたい。
ちょっと、気になるのは、ビブスの
「聞こえません」
という表現。
この表現は、ろう者団体の主導のものではないだろうか。
日本語を第一言語とする私たち中途失聴・難聴者には抵抗があります。
「耳が不自由です」
という、表現にしてもらいたい。
逆に、手話を第一言語としている聾者にとっては、
「不自由」という用語の方がむしろ、あいまいで抵抗がある、
とも聞いている。
それはそれでよい。
聴障者が抵抗感なく着用できるように、行政は、、
「聞こえません」
「耳が不自由です」
の二種類を作成して、
聴障者が選べるようにしていただければ、一番ありがたい。
全難聴の「耳マーク」の表現でも、
「耳が不自由です」
となっている。
(R)
2014年09月27日
2014年09月26日
気付いてほしい

松本市内(千歳橋)
美ケ原が見えています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪つぶやき≫
ある日突然、間こえなくなつた私たち
人生の途中から、だんだんと聞きとりにくくなつた私たち
知ってほしい
気付いてほしい
難聴者・中途失聴者のこと
要約筆記のこと
(R)
2014年09月25日
災害時の難聴者への対応

長野市内 Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
災害時における難聴者への対応について
1.難聴者はどこにもいます
身体障害者手帳を所持している者(聴力70デシベル以上損失者)は全国で約36万人。
そのうち、ろう者(手話を第一言語とする者)は、約6万人。
WHO(世界保健機関)による基準(聴力40デシベル以上損失)の難聴者は推定600万人。
補聴器店の統計では1000万人をこえています。
一つの町内に難聴者が、平均、複数名以上いるということです。
そしてそのほとんどは、手話ができません。
2.補聴器は避難所では十分に機能するとは限りません
補聴器は、静かなところでの1対1の会話では有効ですが、
避難所のようなところでは、あまり機能しません。
高性能の補聴器でも、3メートル以上離れると、会話が成り立ちません。
後ろから呼ばれても気が付きません。
ことに放送の音声は、補聴器では割れてしまい、
言葉として聞き取れません。
3.まず、文字情報掲示板
緊急避難場所が設定されたら、掲示板を設置することが第一です。
放送の内容は、逐一、掲示板に示されないと、伝わりません。
この最も簡単な伝達方法がもっとも対応が遅くなるのを、
今まで、地域の防災訓練で私たちは、何度も経験してきています。
4.耳が不自由であることを示すビブスなどが必要です。
聴障者がこれをつけていれば ボランティアや関係者だけでなく、どなたにも一目瞭然です。
また、要約筆記者、手話通訳者も、一目でわかるようなビブスを着用することが必要です。
すでに支給されている自治体もありますが、
県内のすべての自治体で支給することが喫急の課題です。
5.筆談は、誰でもできます
要約筆記者でなくても筆談はできます。
いつでも、だれでも、どこでも使用できるように、
筆談用具を避難所にも備えておくことが必要です。
筆記グループが考案・作成した「筆談ホワイトボードノート」などの活用が望まれます。
6.情報機器の設置
難聴者にとってラジオはまったく機能しません。
テレビも、字幕がついていないと機能しません。
避難所には、災害行政無線・文字表示機の設置が必要です。
(編集部)
Posted by 六万石 at
17:51
│Comments(0)
2014年09月24日
♪淡紅の秋桜が

Photo by T.Sato
♪ 淡紅の秋桜が
秋の日の何気ない陽溜りに
揺れている・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 稲刈り日和
稲刈り日和