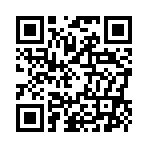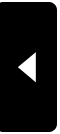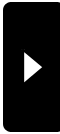2014年08月22日
異様な!土の臭い

2014.8.22 Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
『異様な!土の臭い』
広島の土砂崩れ災害で地元住民らは、
異常な音と同時に、
「あたりに異様な土の臭いが立ち込めていた」
と証言しています。
『異様な!土の臭い』
とは、どんな臭いなのだろうか。
昨年の県防災訓練(諏訪市)では、
『土砂崩れ体験コーナー』
が、あり、
大きく揺れる椅子と
3D(スリーD)の映像で、
目の前に土砂が迫りくる、
という疑似体験をした。
当然、音響効果も付いていただろうが、
私には聞こえなかった。
県災害訓練の体験コーナーでは今後、、
異様な『土の臭い』を出す装置
というようなものを考案・導入して
嗅覚体験もできるように工夫してもらいたいものだ。
(ROKU)
2014年08月21日
災害と難聴者
2014.8.21(木) Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<つぶやき万華鏡>
広島で大きな土砂崩れがあり、
多数の死者や行方不明者が出た。
被災者へのインタビューでは
「深夜、ものすごい雨音に目が覚めて2階へ移動した」
とか、
「山全体が、異常に大きな音がした」
とか、
結局、音が聞こえて
早逃げして助かったということだ。
今回のような場合、
文字情報もへったくれもなかったのではないか。
大きな災害の、究極の混乱時には、
みんな自分の命を守ることに精いっぱいで
誰も書いてなんかくれないのではないか。
そうなっては困るので私たちは、
地域のなかで、日頃から、、
身振りでもなんでもいいから一刻も早く伝えてほしいことを
大いにアッピールしておく必要があると思います。
(ROKU)
2014年08月20日
要約筆記を利用して社会参加を(PR)

Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
聴こえについて悩んでいる方
一人で悩まないで!
要約筆記を利用して、
積極的に社会参加をしよう!
当協会は、あなたのご入会を
何時でもお待ちしております。
詳しくは長野難聴ホームページをご覧ください。
→ http://nagano-nancho.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年08月19日
中途失聴・難聴者にとって手話とは
「やまびこドーム」(於 信州スカイパーク) Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014.8.19
<つぶやき万華鏡(投稿記事)>
中途失聴・難聴者にとって手話とは
聴覚障害者に関するいくつかの誤解のうち
「聴覚障害者=手話」
という誤解は、世の中の誤解(迷信)の最たるものであろう。
実際には、聴覚障害者のなかで、手話を第一言語とする者の割合は非常に少ない。
中途失聴・難聴者の大多数は手話ができない。
「手話ができない」
というよりも
「手話をやらない」。
実際に、中途失聴・難聴者が現実の社会・職場でやっていくなかで、、
「手話ができなければ困る」
という場面は、(特別なケースを除いては)ありえない。
「手話でなければ通じない病院」
とか、
「手話でなければ通じない役所」
などの話は、
現実には聞いたこともない。
地域や隣近所でも、手話は使われない。
家庭でも、ことに中途失聴・難聴者の家庭では、
家族が手話を使えない。
中途失聴・難聴者にとって手話は、
手話通訳(ろう者との仲介)をするためのものではなく、
仲間同士の、
コミュニケーションの手がかりとしての一手段にすぎない。
手話は、
中途失聴・難聴者が必ず学ばなければならないというものではない。
いくらかでも手話を知っていれば、
難聴者仲間同士の、
とりわけ、手話ができる聴者とのコミュニケーションで、
やはり便利で、
楽しいものであることを、、
私も大いに実感しています。
ただし、それは、私にとって、あくまで、
非日常
である。
手話は、
やらなきゃやらないでもすむことである。
手話は、(もしやるなら)
むしろ、遊び半分に、
大いに楽しめばいいと思う。
(ROKU)
2014年08月18日
8月18日の記事
今日から2学期(広丘小学校) Photo by T.Sato
【掲示板】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第16回 関東ブロック女性部一泊研修 11月8日(土)~9日(日)

会場:片倉館 http://www.katakurakan.or.jp/index.php
宿泊:上諏訪温泉・朱白 http://www.suhaku.co.jp/
只今申込受付中
定員50名(先着順)
詳細は、サイドバーのカテゴリ「関東ブロック女性部一泊研修」をクリックしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Posted by 六万石 at
07:48
│Comments(0)
2014年08月17日
ベル先生(2)
本日大気不安定 (塩尻GAZAから) 8.17 Photo by T.Sato
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
<トリビア万華鏡>(投稿記事)
☆ 8/15記事「ベル先生」の元ネタをご紹介します。
なんと、平成24年度の長野県高校入試問題。
画面の関係で写真では前半だけをご紹介しましたが、
文章の後半にはヘレンケラーにサリバン先生を紹介した話もでてきます。
(ROKU)
2014年08月16日
難聴入門講座・ヘルツ
2014.8.16 Photo by T.Sato
<難聴入門講座(4)>
ヘルツ
オージオグラムの横軸となっているのが周波数(振動数)で、
ヘルツ(Hz)という単位を使う。
1秒間に1回振動すれば1ヘルツ、
1秒間に100回振動すれば100ヘルツ.。
音の高さは振動数だけて決まる。
値が小さいほど低音、大きいほど高音」となる。
オージオグラムのメモリ(横軸)は
125,250,500,1000,2000,4000,8000 (Hz)
まで。
人が聞くことのできるのはだいたい20ヘルツから2万ヘルツ.
それ以上の音は超音波、イルカやコウモリの世界である。
コウモリは5万~6万ヘルツの超音波を出して物体にあてて反射させ、
その方向や強さから、
物体の距離や大きさ、動いている速さまで感じ取れるという。
超音波を利用した医療機器(エコー)がある。
松本清張の 砂の器 では、
超音波が殺人の道具として使われた。
(ROKU)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※オージオグラムの読み方 ↓
http://www20.big.or.jp/~ent/kikoe/odiogram.htm
Posted by 六万石 at
07:44
│Comments(0)
2014年08月15日
ベル先生
今朝の東の空 8/15 Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<トリビア万華鏡>
ベル先生
<誰でもこたえられる簡単なクイズ>
電話を発明した人は誰でしょうか?
その名は、グラハム・ベル。
・・・・超簡単なクイズでした。
川栄でもこたえられる。
グラハム・ベルは電話の発明者として有名である。
このベル先生、実はろう者の先生としても有名です。
ちなみにベルのお父さんは言語学者で、指文字の発案者。
ベル先生は電話発明の10年後、
6歳の少女と出会った。
その名はヘレンケラー。
ヘレンケラーにサリバン先生を紹介したのはベル先生。
ベル先生はその後も聴覚障害児(者)に深くかかわり、
晩年には、ご自分で発明した電話機を
「こんなものは要らない!」
と、おっしゃったとか。
(この記事は過去ログからのリメークです)
(ROKU)
2014年08月14日
アルプス85号発行
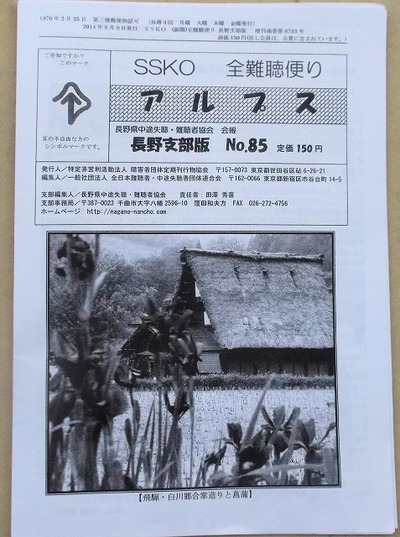
長野難聴の機関紙「アルプス」85号が発行されました。
・定例会レポート
・県要約筆記者養成講座レポート
・その他、レポートや投稿記事
など、充実した内容です。
頒価1部150円
購読会員(年会費1,000円)も募集しております。
お問い合わせは、長尾難聴事務局 FAX 026-272-4756 (窪田)
(編註) 県要約筆記養成講座などの講義内容は、
当ブログでは掲載しておりません。
講演会や講義の著作権は講演者にあり、
NETにのせることができません。
ぜひ、「アルプス」でご覧ください。
2014年08月13日
コミュニケーション講座(東京)

Photo by T.Sato
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ 5分のために3時間かけて
<コミュニケーション講座(東京)に参加>
東京都難聴者協会主催のコミ講座に応募しました。
一回4時間全5回の講座ということす。
長野県ではこの講座を開いているところが無いので
どんな講座か知りたくて応募してみました。
申し込み時に作文を付けることになっていて、
さらに面接まであるのです。
一人5分ほどの面接。
この5分のために3時間かけて行きました。
これから週一で始まる講座への参加をどうしたものかと
帰りの電車の中で考えながら帰ってきました。
( 浜 )
Posted by 六万石 at
06:36
│Comments(0)